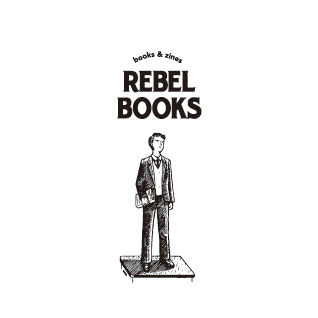-

そいつはほんとに敵なのか | 碇雪恵【予約受付中:3/18ごろ再入荷予定】
¥1,870
予約商品
★ただいま重版中、3/18ごろ再入荷予定です。予約を受け付けます。 本書で著者の碇さんが参政党支持者に会いに行く章があるのですが、ここに大きなヒントがある気がしました。つまり、話してみないとわからないということ。 ーーー SNSを捨て、喧嘩を始めよう。 “合わない人”を遠ざける人生は、心地いいけどつまらない。 もっと沸き立ちたいあなたに送る、現代人必読の〈喧嘩入門エッセイ〉誕生! 駅でキレているおじさん、写真を撮りまくる観光客、理解できない政党と支持者、疎遠になった友だち、時にすれ違う家族や恋人……。 「敵」と決めつけて遠ざけるより、生身の体でかれらと出会い直し、逃げずにコミュニケーションをとりたい。 ZINE『35歳からの反抗期入門』が口コミで大ヒット中の書き手・碇雪恵による、待望の商業デビュー作。 憎みかけた「そいつ」と共に生きていくための思考と実践の記録をまとめた14編を収録。 ー 【目次】 喧嘩がしたい 純度の高い親切 友情の適正体重 悪意に顔があったーー映画『ルノワール』を観て 反抗期、その後 誰の場所でもない 身内をつくる(ひとりで考えてみた編) 身内をつくる(実践スタート編) 対戦じゃなくて協力モードで ティンプトンから始まるーー映画『ナミビアの砂漠』にみる恋愛と喧嘩 自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(準備編) 自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(実践編) ほんとは敵じゃない 時折自分を引き剥がすーー映画『旅と日々』を観て ーーー 四六判 ソフトカバー 176ページ 送料:300円
-

社会主義都市ニューヨークの誕生 | 矢作弘
¥2,420
2025年のニューヨーク市長選で民主社会主義者でムスリムのゾーラン・マムダニが当選。その背景を解き明かす本。私も今読んでますが非常に面白い。格差の拡大で本当に困った市民たちの切実な声と、その声に耳を傾けるマムダニ。世界のどの都市にも当てはまる市民生活と政治の普遍的な課題と取り組みが見えてくる。これからのニューヨークがどうなるかも興味深いですが、この本を読んでおくとかなり解像度が上がるはず。 ーーー グローバル資本主義の首都ニューヨークの市長に、急進左派の!?民主社会主義者、ゾーラン・マムダニ氏が就任へ!生活苦の労働者・若者の支持を集める背景や氏の人物像、家賃凍結/公共バスや子供保育の無償化/市所有スーパーマーケットの展開/富裕層・大企業増税等の政策を解剖し、他都市やワシントン政治への影響を展望。 ーーー 四六判 ソフトカバー 188ページ 送料:300円
-

「あの選挙」はなんだったのか 2024衆院選・2025参院選を読み解く | 荻上チキ編著
¥2,200
思いのほかすぐに「あの選挙」の次の選挙が来てしまいました。「この選挙」が終わっても、「あの選挙」について考えることには大きな意味があるはず。 ーーー 2024年衆院選と2025年参院選、「あの選挙」は一体なんだったのか? 民主党政権を挟みながらも、自公政権が長く続いてきた日本政治。2024年の衆院選では、与党が過半数を割るという大きな変化が起こった。この変化は、期待されていたような「政権交代への作用」を実際に生み出したのだろうか。驚きや戸惑い、さらには予想外の熱気など、様々な反応がみられるなかで、「あの選挙」の結果と過程から何を学び、どのように理解すべきなのか。その全体像はいまだにみえていない。 国民民主党の躍進、立憲民主党の伸び悩み、日本維新の会の凋落、参政党の急速な伸長、多様化する少数政党、そして自民党と公明党の連立与党の衆参両院での過半数割れによって生まれた新たな政権の枠組み。いまの政治状況は、本当に国民が望んだものであり、「民意」が反映された結果なのだろうか。 ・「あの選挙」で起こったこと/起こらなかったこと ・「あの選挙」で変わってしまったこと/変わらなかったこと ・「あの選挙」で届いた声/届かなかった声…… 選挙のたびに入れ替わる、注目政党や選挙手法のトレンド。目まぐるしく変わる状況を前に一度立ち止まり、考え、対話するための土台となる知見を、政治学、データ分析、アメリカ政治、ジェンダー平等、SNSマーケティング、ジャーナリズム、哲学対話の専門家たちがそれぞれの視点から解説。そして、そこからみえる「民意」の本当の姿とは。 「あの選挙」から「次の選挙」へ進んでいくために。 いまだからこそ知っておきたい、すべての世代に向けた選挙の新しい入門書の第2弾。 ーーー A5判 272ページ ソフトカバー 送料:300円
-

POSSE vol.61 特集:選挙以外で社会を変える/ネット以外で社会を変える
¥1,760
SOLD OUT
今こそ読みたい特集内容。私も買って読んでます。どの記事も学びが多いですが、冒頭のナンシー・フレイザーのインタビューを読むだけでも充分価値があると思います。 ーーー 「小さな声と大きな変革をつなぐ雑誌」POSSEが、デザインを新たにリニューアル! 特集:選挙以外で社会を変える/ネット以外で社会を変える 第二特集:「働いて働いて働く」発言のどこが問題なのか? 世界は選挙(だけ)では決まらない──。 選挙のたび無力感に苛まれているすべての人に。 ーーー A5 ソフトカバー 174ページ 送料:300円
-

僕らは戦争を知らない 世界中の不条理をなくすためにキミができること ハンディ版
¥1,760
すごく良い。戦争って何なの?なぜ起きるの?様々な疑問にわかりやすい解説と図解で答える本。必要なテーマを網羅している、とても勉強になる。内容も公平。小学校高学年以上が対象だけど大人にも勧めたい。親子で考えるのも良い。 ※元々2024年1月に主に学校図書館向けに刊行された本で、大きな反響を受けて一般書店でも買えるようハンディ版として発売されたもの。2025年3月時点での世界情勢を盛り込んで増補加筆し、2025年7月刊行。 ーーー 【目次】 ◆第1章 なぜ戦争は起こるの?~ロシアとウクライナを例に考える~ ・マンガ 第1話 僕らは戦争を知らない ・なぜ戦争は起こるの? ・ロシアってどんな国? ・ウクライナってどんな国? ・ロシアとアメリカは仲が悪いの? ・なぜロシアはウクライナに攻め込んだの? ・正しいのはどっち? ・攻め込まれた地域はどうなってしまったの? ・ロシアの国民はどう考えているの? ・なぜ国民が戦わないといけないの? ・話し合いで解決できないの? ・周りの国はどう思っているの? ・核兵器って何? ・インターネット上の攻撃もあるの? ・ロシアとウクライナの戦争はいつ終わるの? ・僕らの生活にも影響が出ているの? ・他の国や地域でも戦争が起こっているの? ◆第2章 戦争は遠い国の話じゃない ・マンガ 第2話 日常が奪われる不条理 ・日本も昔は戦争をしていたの? ・どうやって戦争が終わったの? ・敗戦後の日本はどうなったの? ・日本は悪いことをしたの? ・日本は軍隊をもっているの? ・軍隊なしでどうやって国の安全を守るの? ・日本にはどれくらい米軍基地があるの? ・なぜ日本は核兵器を持たないの? ・なぜ北朝鮮はミサイルを発射するの? ・日本の領土はどこまで? ・日本の防衛費が増えているってホント? ・日本で戦争が起こる可能性はあるの? ◆第3章 争いのない世界のために ・マンガ 第3話 僕らにできること ・平和って何? ・国連って何? ・SDGsって何? ・平和のために日本政府は何をしているの? ・日本の企業や団体はどんな活動をしているの? ・若い世代の人たちは何をしているの? ・戦争のことを調べるにはどうすればいいの? ・日本にいながらできることはあるの? ・戦争を起こした国を許していいの? ・争いのない世界のために何ができるの? ◆第4章 今日も戦争は続くけれど ・マンガ 平和への希望 ・ウクライナとロシアの戦争は終わるの? ・ロシアは約束を守ったの? ・ガザで何が起こっているの? ・世界は平和に近づいているの? ◆インタビュー ・広島の被爆体験証言者 小倉桂子さん ・ウクライナからの避難民 マテウィ・ホンチャレンコさん ◆戦争と平和について学ぶための おすすめの本 ◆さくいん ーーー A5変型 ソフトカバー 152ページ 送料:300円
-

ニッポンの移民——増え続ける外国人とどう向き合うか | 是川夕
¥1,012
ーーー 移民で日本はどう変わるのか? 増え続ける外国人に対し不安の声は多い。この国の未来を冷静に議論するために、第一人者がデータに基づいた基礎知識を伝授する。 ー 少子高齢化による労働力不足や、流動的な世界情勢を受け、 近年日本に多くの外国人がやってくるようになった。2070年には、人口の約10%に達するとも言われる。それに対し、 治安や社会保障に関する不安の声は多く、 排外主義も台頭している。 移民は日本にとって救世主なのかリスクなのか? 日本は欧米のように分断されるのか? 移民なしではこの国はもたないのか? 第一人者が、エビデンスを基に、 移民政策の歴史と未来について考察。移民をめぐる議論に一石を投じる。 ーーー 新書 256ページ 送料:300円
-

ハンナ・アーレント、三つの逃亡 | ケン・クリムスティーン
¥3,960
ユダヤ人として戦争の世紀に生まれ落ち、現実に向かって“なぜ?”と問いつづける。不世出の政治哲学者ハンナ・アーレントの生涯を描いたグラフィックノベル。 22.2 x 16.5 x 2.3 cm 送料:300円
-

政治的に無価値なキミたちへ | 大田比路
¥1,650
政治のことがわからない人でもこれを読むうちに政治的論点を持ち、自らの政治的立場を把握できるようになるという本。早稲田大学の政治入門講義を書籍化したもの。 序盤で問いに答えていくと自分が「リベラル」「リバタリアニズム」「共同体主義」「保守主義」のどれに近いのかがわかる。 個別の論点で言うと例えば話題の東大授業料値上げ、「まあお金はかかるし昔とは違うしな」と思った方もいるかもしれない。この本では教育の項で「国公立大学の初年度納付額」や「教育予算額の対GDP比率」のデータを用い、日本が先進国の中でも最悪の部類に入る「教育弱小国」であることを示す。 すべての項目で具体的なデータ(のグラフ)を用いて解説しておりよく理解できる。 政治は生活と直結し、自分の人生に直接的な影響を及ぼす。 次の選挙までにたくさんの人に読んでほしい一冊。 おすすめです。 四六判 ソフトカバー 320ページ 送料:300円
-

現場から社会を動かす政策入門――どのように政策はつくられるのか、どうすれば変わるのか | 西川貴清
¥2,640
ーーー (出版社による紹介) 政策をもっと身近に、よりよい仕組みをともに。 日常生活やビジネスでぶつかる課題を「みんなの声」として届けるには?近くて遠い政策のオモテとウラを、元官僚の「政策翻訳家」が分かりやすく解説。ニュースの読み解きから政策提案まで対応する必携の一冊。 [目次] はじめに 序章 政策と向き合うときの二つの心構え 第1章 「みんなの声」は届いているか 第2章 商品との比較から考える政策の本質 第3章 意外と知らない七つの政策ツール 第4章 政策が大きく動くとき 第5章 官僚の得意分野とは 第6章 政治家の三つの立場 第7章 省庁のスタンスの違い 第8章 実は明確に決まっている政策スケジュール 第9章 世論やメディアが持つ大きな力 第10章 鍵となる地方自治体での政策実現 第11章 政策提案の勘所――四つのケーススタディ 付録 もっと学びたい人のために ーーー A5変形判 ソフトカバー 288ページ 送料:300円
-

絵本戦争 禁書されるアメリカの未来 | 堂本かおる
¥2,970
アメリカで近年「保守派の親や政治家が理想とする<古き良きアメリカ>にとって都合の悪い、子ども向けの本」が多数禁書指定されているという現実に迫る一冊。トランプ再選後の悪夢を見ているとある意味納得するとともに、対岸の火事と思わない方がいいとも思います。 ※特典ペーパー「『絵本戦争』の絵本リスト」が付きます。 ーーー (出版元による紹介) アメリカではいま、保守派による禁書運動が暴走している。黒人、LGBTQ、アジア系、アメリカ先住民…マイノリティを描いた絵本がなぜ禁書されてしまうのか。NY在住ライターが禁書となった数々の絵本を通して見る、アメリカの姿。 非営利団体「ペン・アメリカ」によると2023-2024学校年度に、前学校年度の2.7倍にあたる4231種類の本が禁書指定された。アメリカでいま、何が起きているのか。 この禁書運動は2021年に突如として始まった。ターゲットになっているのは、禁書運動を推進する保守派の親や政治家が理想とする<古き良きアメリカ>にとって都合の悪い、子ども向けの本たちだ。 黒人、LGBTQ、女性、障害、ラティーノ/ヒスパニック、アジア系、イスラム教徒、アメリカ先住民……8つのトピックにわけて、禁書運動の犠牲となった数々の絵本を一冊ずつ見ていくことで、マイノリティの苦難の歴史と、その中で力強く生きる姿、そして深刻化している政治的な対立<文化戦争>の最前線を知る。いま、必読の一冊。 ーーー 四六判 ソフトカバー 200ページ 送料:300円
-

若者の戦争と政治 20代50人に聞く実感、教育、アクション
¥1,870
戦争と政治に無関心な人間が増えれば増えるほど「戦争を仕掛ける国」になる可能性が高まると思います。若者も若者じゃない人も、あらためて考えるきっかけに。 ーーー (出版元による紹介) 「社会や政治に無関心な若者」は、こうして生まれたー 1994〜2004年生まれ、20代50人に聞いた、戦争と政治。 「慰安婦」の文字が教科書から消され、戦争における加害の歴史を学ばなかった。 性教育がバッシングされ、激しいジェンダーバックラッシュが起こった。 生きづらさを自己責任で丸め込まれ、「ゆとり」や「さとり」と後ろ指をさされる。第2次安倍政権下で義務教育期を過ごしたかれらは、当時の政治や教育にどう影響され、何を感じてきたのか。 生まれ育った1994〜2024年の政治、教育、文化、社会の動きを年表で振り返るとともに、若者たちの声を聞く1冊。 戦争を起こさないようにするのは誰か。問われなければいけないのは政治だ。 (寄稿 武田砂鉄) * 戦争や政治と聞いた時、どんなものを思い浮かべますか? 小学校〜高校までに学んだ戦争、政治について、印象に残っていること、記憶していることを教えてください。 【戦争】 日露戦争とか、日清戦争などの単語と年号。受験頻出のことばかり覚えている。なんで起こったのかとかは覚えていない(23歳) 土地や資源を奪い合って人が死ぬ行為、ぐらいの想像力しか持てない(24歳、男) 「慰安婦」という言葉は教科書にも書かれていなかったし、聞いたこともなかった(26歳) 日本が受けた被害については印象に残っているのに、日本が他の国や地域に対して行ってきたことについてはさらりと済まされていたような気がします(28歳) 【政治】 腐敗だらけでゴミだけど、世の中も同じくらいダメなところがあるから、変えようがないもの。「お上」。中高年男性。居眠り(22歳) 政治についていくにはエネルギーが必要で、日々の生活に精いっぱいのときには簡単ではない(22歳) 選挙権を得た年に、有権者として初めて公約をチェックした際、自分の住んでいる地域では若者にとって魅力的な候補者がほとんどいないことに驚きました(26歳) 政治についてもっと声を上げていい、批判して、何なら怒ってもいい、私たちにはその権利があるということをもう少し早く知っておきたかった(29歳) ーーー 新書判変型(173mm×110mm)・並製・232ページ 送料:300円
-

FIFTYS PROJECT ZINE
¥1,200
政治分野のジェンダー不平等解消を掲げて活動するFIFTYS PROJECTによるzine。毎月のニュースレターに掲載している、メンバーがそれぞれの活動の報告や時事ニュースについて考えたことを書いたコラムをまとめたもの。 「「個人的なことは政治的なこと」という言葉があるように、私たちが活動する背景には、この社会に生きている一人の人間として、女性として、女性として見られる存在として直面する理不尽や日々感じるモヤモヤ、不安、怒りがあります。このZINEを通して、少し勇気がもらえたり仲間がいるという安心を感じてもらえたらとても嬉しいです。そして、政治分野におけるジェンダー平等を求める人の輪が広がることを願っています」 ★FIFTYS PROJECTは「政治分野のジェンダー不平等、わたしたちの世代で解消を」と掲げ、2022年の夏に設立した団体で、20代・30代の女性(シス/トランス)、Xジェンダー、ノンバイナリーの地方議会議員への立候補を呼びかけ、一緒に支援するムーブメントです。 182x115mm ソフトカバー 105ページ 送料:300円
-

普通の奴らは皆殺し | アンジェラ・ネイグル
¥2,420
ーーー (出版社による紹介) なぜリベラルは敗北するのか? なぜトランプは大統領になれるのか? オルタナ右翼はリベラルが生み出したモンスターである。オルタナ右翼を正しく理解せずに、リベラルの勝利はない。 ー オルタナ右翼・トランプ主義者研究の最重要書 本書は、2010年代初頭に起こったインターネット文化戦争を忠実に記録し、それが2016年のドナルド・トランプ大統領誕生に大きな役割を果たした「オルタナ右翼」となって発展する道行きをマッピングする。オルタナ右翼の特徴が、60年代カウンターカルチャーに由来する「侵犯的な反道徳スタイル」だとしたら? 本来リベラルであったインターネットのサブカルチャーは、どのように右傾化し、メインストリームを征服していったのか? ー 「中流階級が自己懲罰として自らを鞭打ち、それが危険な荒波となってリベラル左派を飲み込み、道を見失わせる。アンジェラ・ネイグルはそのなかで、灯台守となってわたしたちに出口を示す。彼女の分析は容赦ないが、決して残酷ではない。疎外と敗北に慣れすぎた多くの左派とは異なり、ますます残酷になる世界を変える唯一の方法として政治を信じている。彼女はわたしが待ち望んでいた作家であり社会評論家だ」――コナー・キルパトリック「ジャコバン・マガジン」 「ネイグルは世界でもっとも輝かしい光のひとりであり、知的同調からの独立を宣言した新世代の左翼作家・思想家である」――キャサリン・リュー(作家・アメリカ文化理論家) 「わたしたちの時代の混沌のただなかで、頼るべき人としてアンジェラ・ネイグルのような聡明で恐れ知らずの批評家がいることは救いになる。彼女は右翼のサブカルチャーの出現とその重要性を適切に説明することができないリベラルの陳腐な教義で我慢することを好まず、インターネットの洞窟のもっとも汚れた場所まで降りて、鋭く冷静な分析をわたしたちに与えようとする唯一の存在だ」——アンバー・アリー・フロスト「チャポ・トラップ・ハウス」 「アンジェラ・ネイグルは、有害なレイシズムとミソジニーが先端的なカウンターカルチャーのパッケージとして現れたとき、それに対してダブルスタンダードを用いることを一貫して拒否した、数少ない書き手のひとりである。本書は、ウェブ上のニヒリズムとファシズムがもつ新しい一面に関する見事な解説であり、この新しいニヒリズムとファシズムは、もはや「(笑)」をつけておけばよいのだと言って逃げることはできない」——デイビッド・ゴロンビア(『ビットコインのポリティクス:過激な右翼としてのソフトウェア』著者) ー [もくじ] 序章 希望からゴリラのハランベに 第1章 リーダーなきデジタル反革命 第2章 侵犯のオンライン政治 第3章 オルト・ライトのグラムシ主義者たち 第4章 ブキャナンからヤノプルスまでの保守派文化戦争 第5章 Tumblrから大学キャンパスでの戦争へ:ウェブ上の正しさのエコノミーに飢餓状態を創り出すこと 第6章 マノスフィア(男性空間)に入会すること 第7章 つまらないビッチ、ノーマルな連中、そして絶滅寸前メディア 結論 あの冗談はもう面白くない——文化戦争はオフラインへ [著者] アンジェラ・ネイグル ANGELA NAGLE 1984年、アメリカ・テキサス州生まれ、アイルランド・ダブリン在住の作家・社会評論家。オルタナ右翼の専門家として「ニューヨーカー」「バッフラー」「ジャコバン」「アイリッシュ・タイムズ」ほか多くの雑誌に寄稿している。反フェミニストのオンライン・サブカルチャーに関する研究で博士号を取得。2017年に刊行した『KILL ALL NORMIES』は、白人至上主義のオルタナ右翼の起源に迫るドキュメンタリー『Trumpland: Kill All Normies』の原作となった。著書に『緊縮財政下のアイルランド 新自由主義の危機と解決策』 (コリン・コールターとの共著)など。 ーーー 新書版 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

みんなの「わがまま」入門 | 富永京子
¥1,925
当店で常備していて、コンスタントに売れている本。身近な「わがまま」と社会をゆるやかにつなげ、意見の異なる人々と社会をつくるための入門書です。 ーーー (出版社による紹介) “権利を主張する”は自己中? 言っても何も変わらない? デモや政治への違和感から、校則や仕事へのモヤモヤまで、意見を言い、行動することへの「抵抗感」を、社会学の研究をもとにひもといていく、中高生に向けた5つの講義。 【目次】 ◎1時間目 私たちが「わがまま」言えない理由 わがまま=自己中? 日本が30人の教室だったら/「ふつう幻想」が「ずるい」をつくる/わがままは自己中ではない 意見を言うと浮いてしまう? ふつうと平等はどこへ消えた?/グローバル化で「ばらばら」に/私のわがままはみんなの「それな!」/今のわがまま・昔のわがまま/違いからはじめて同じ根っこを探す/私、別に「かわいそう」じゃないし… エクササイズ1 その人になってみる エクササイズ2 あだ名ワークショップ ◎2時間目 「わがまま」は社会の処方箋 「わがまま」批判はどこからくるの? わがまま下手な日本人/「批判するからには、別の案があるんだよね?」/「社会のためとか、意識高いよね(笑)」/「社会運動って、迷惑じゃないですか?」/「価値観の押し付けでしょ?」/「自己責任じゃないですか?」 それで、結局意味あるの? わがままはきっかけづくり/自己満足でもいい/「わがまま」はアイドルの出待ち?/長い目で見てみる エクササイズ3 20年前と今を比べてみる エクササイズ4 変化を説明してみる ◎3時間目 「わがまま」準備運動 どこまで「わがまま」言ってもいいの? アウトなわがまま・セーフなわがまま/わがままの背景を考える/わがままの落とし所? 伝え方が悪いと、話を聞く気になりません 過激な表現にひるまない/「おうち語」化に気をつける 「〇〇派」を超えて言葉を伝えよう 知らない人に教えてみる/イベントを大事にする/いろんな大人に会う/大学に行ってみよう/「中立」も「偏り」も、そんなにこだわることじゃない/「うちの地元に大学はねえよ」/人をカテゴライズしない エクササイズ5 「おうち語」を翻訳する ◎4時間目 さて、「わがまま」言ってみよう! 社会的「わがまま」のススメ モヤモヤで「わがまま」キックオフ/わがままは、直接相手に言わない/伝えるための工夫/趣味の雑誌を読もう もっと気軽にできる方法はありませんか?(やっぱり恥ずかしいし) ちょっと文化系なわがままが好きな人に/代わりのものをつくってみる/買う・選ぶもわがままのうち/こっそりやってみる 気が向かないときはやめてみる 遠くに行ってやってみる/うまく行かなくても気にしない/自分をカテゴライズしない エクササイズ6 モヤモヤするものを探す エクササイズ7 署名を呼びかけてみる! ◎5時間目 「わがまま」を「おせっかい」につなげよう ーーー 四六判 ソフトカバー 276ページ 送料:300円
-

選挙との対話
¥1,980
ーーー (出版社による紹介) 「あなたにとって選挙とは?」 「政治参加の手段?」「民主主義の根幹?」、 それとも「行っても/行かなくても変わらないもの……?」 近年、国内外を問わず、選挙のあり方そのものが問われる事態が相次いで起こっている。こうした状況のなかで、選挙に関して「科学的に」わかっていることはなんなのか。またそれを知ることは、私たちの生活にどのように関係してくるのだろうか。 2009年以降、自民党の勝利が続く日本の国政選挙について、政治学やデータ分析の専門家たちはどのように見ているのか。国際的にみて女性の社会進出が遅れているといわれている日本の現状は? またそれを取り巻くメディアの状況は? そして、若い世代が感じている日本の選挙のリアルとは? 科学的な分析に加え、杉並区長へのインタビューやお互いの話を聴き合いながら思索を深める哲学対話から、選挙を、そして政治をより身近にたぐり寄せるためのさまざまなヒントをちりばめた、すべての世代に向けた選挙の新しい入門書。 【目次】 まえがき 荻上チキ 第1章 なぜ自民党は強いのか?――政治に不満をもつのに与党に投票する有権者 飯田 健 1 自民党の強さ 2 自民党の強さの原因 3 政治に不満をもつにもかかわらず自民党に投票する有権者 4 自民党が負けるシナリオ? 第2章 選挙制度は日本の政治にどう影響しているのか?――自民党一党優位の背景を説明する 菅原 琢 1 自民党の「強さ」の謎 2 もくろみが外れた衆院選挙制度改革 3 小選挙区比例代表並立制が促す終わらない政界再編 4 並立制の解は政党間の協力 5 自民党一党優位は絶対ではない 第3章 なぜ野党は勝てないのか?――感情温度や政党間イメージについて 秦 正樹 1 「野党はふがいない」と言われ続ける理由 2 世論の野党への認識:1――感情温度を用いた分析 3 世論の野党への認識:2――イデオロギーを用いた分析 4 世論の野党への認識:3――政権担当能力評価 5 野党の今後を考える 第4章 なぜ女性政治家は少ないのか?――政治とジェンダー、政治家のメディア表象について 田中東子 1 新聞はどのように女性政治家を報じてきたのか 2 ポピュラー文化と女性リーダーの表象 3 「すべての女性たち」が政治の場で活躍できる社会とは 第5章 政治家にとって対話とは何か?――杉並区長・岸本聡子インタビュー 岸本聡子(聞き手:永井玲衣/荻上チキ) 第6章 私たちはどうやって投票先を決めているのか?――日本の有権者についてわかっていること、データからわかること 大村華子 1 私たちの投票は何によって決まっているのか 2 日本の有権者の投票は何によって決まっているのか 3 データを使ったら、どんなことがわかるのか 第7章 私たちにとって選挙とは何か?――選挙をめぐる哲学対話 永井玲衣/荻上チキ あとがき 荻上チキ ーーー A5 ソフトカバー 180ページ 送料:300円
-

選挙活動、ビラ配りからやってみた。「香川1区」密着日記 | 和田静香
¥1,760
『時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか? 国会議員に聞いてみた。』で小川淳也と1年間対話(ときどきバトル)を繰り広げた和田靜香が、今度は選挙に密着!2021年衆院選。映画で注目の選挙区「香川1区」で、“選挙のリアル”を追った14日間のこと。 ーーー 「何が分からないのかも分からないんです」と永田町に乗り込んでから1年。相撲・音楽ライターの和田靜香がパワーアップして戻ってきた!街宣、ビラ配り、電話かけを実際に体験して感じた、日本の選挙へのギモン。「物言う市民」の立場から、パワフルな問いが炸裂! 街宣から帰ってきた小川淳也に「何してるん?」と聞かれ、渋々「電話かけ」のボランティア。「案内はメールでいいじゃん?」「選挙ビラになんでわざわざ1枚1枚シールを貼るの?」。謎の公職選挙法にボヤきながら休むことなく動き続けて、究極の「選挙ハイ」発動。そして気づく。「選挙にはなんで休みがないのか」。選挙事務所では女性ボランティアのなかに溶け込んで「選挙で使われる言葉ってたいがいマッチョ!」とワイワイおしゃべり。そして投票日直前、ジェンダーにまつわる「匿名のタスキ」問題をめぐって、小川淳也とまさかの衝突……!? ーーー 四六判 ソフトカバー 208ページ 送料:300円
-

世界に学ぶミニ・パブリックス くじ引きと熟議による民主主義のつくりかた
¥2,970
ーーー 代議制民主主義の限界が露呈するなか、無作為抽出による少人数グループが十分な専門的情報を得て熟議を行い、提言を策定して公共政策の検討過程へ反映させるミニ・パブリックスと呼ばれる取組みが拡大している。世界289事例の分析をふまえ、成功のための原則、既存の制度に熟議を埋め込む方法をまとめた初の活用ガイドライン。 ーーー 【目次】 はじめに 謝辞 読者への手引き 本書の概要 ■Chapter 1 熟議とガバナンスの新しい形 1.1 なぜ現代の民主主義は危機にあるのか 1.2 本書が熟議とガバナンスの新たな形態を取り上げる理由 1.3 なぜ代表性と熟議なのか 1.4 抽選代表による熟議プロセスをいつ用いるべきか、用いるべきではないのか ■Chapter 2 熟議プロセスの様々なモデル 2.1 本章の対象 2.2 12のモデルの概要 2.3 政策課題に対する十分な情報に基づく市民提言 ・市民議会(Citizens’ Assembly) ・市民陪審/パネル(Citizens’ Jury/Panel) ・コンセンサス会議(Consensus Conference) ・計画細胞(Planning Cell) 2.4 政策課題に関する市民の意見を把握するためのモデル ・G1000 ・市民カウンシル(Citizens’ Council) ・市民ダイアローグ(Citizens’ Dialogues) ・討論型世論調査(Deliberative Poll/Survey) ・世界市民会議(World Wide Views) 2.5 住民投票にかけられる法案の評価モデル ・市民イニシアティブ・レビュー(Citizens’ Initiative Review) 2.6 常設型の抽選代表による熟議機関モデル ・東ベルギーモデル(Ostbelgien Model) ・市民監視委員会(City Observatory) 2.7 抽選代表による熟議のモデルをどう選択するか 2.8異なるモデルの機能を組み合わせる ■Chapter 3 熟議プロセスをめぐる世界のトレンド 3.1 世界のトレンドを概観するための7つの視点 3.2 調査結果の概要 3.3 OECD加盟国における熟議プロセスの導入状況 3.4 熟議プロセスの利用に対して繰り返し高まる関心の波を時系列で見る 3.5 政府・自治体のレベルごとに見た熟議プロセスの導入状況 3.6 多様な熟議モデルとその普及状況 3.7 熟議プロセスが導入された政策課題のタイプ 3.8 抽選代表による熟議プロセスの平均的なコスト 3.9 熟議プロセスの実施を委託された組織の種類 ■Chapter 4 成功する熟議プロセスとは?―エビデンスから考える 4.1 熟議の評価原則 4.2 主な調査結果の概要 4.3 公正な手続きと認められるための条件 101 ・検討課題の範囲 ・無作為選出の方法 ・さまざまな無作為選出の方法 ・参加への障壁を克服する ・熟議プロセスの重要性、参加者に求められるコミットメント、および期待される結果についての明確なコミュニケーション ・実施期間 ・意思決定者のコミットメント 4.4 適切な熟議と判断を可能にする要素 ・情報提供と学習 ・専門家とステークホルダーの選択 ・ファシリテーション ・熟議プロセスの中での意思決定 4.5 影響力のある提言とアクション ・抽選代表による熟議プロセスのアウトプット ・市民の提言への応答 ・市民提言に基いた政策の実行過程 ・モニタリングと評価 4.6 広く社会に影響を与える方法 ・公衆の学習ツールとしてのパブリックコミュニケーション ・参加型手法と抽選代表による熟議プロセスの組み合わせ ■Chapter 5 公共的意思決定のための熟議プロセス成功の原則 5.1 成功原則をまとめるにあたって 5.2 調査方法 5.3 公共的意思決定のための熟議プロセス成功の原則 ■Chapter 6 民主主義を再構築する―なぜ、どのように熟議を埋め込むか 6.1 熟議プロセスの制度化 6.2 制度化の定義 6.3 主な調査結果の概要 6.4 なぜ制度化するのか? 6.5 制度化に向けたさまざまなアプローチ ・常設または継続的な組織の創設 ・熟議プロセスを組織するための要件 ・市民が抽選代表による熟議プロセスを要求することを認める規則の制定 6.6 一時的な取り組みから制度化された実践への移行―その要件、障害、戦略 ・適切な制度設計 ・政治家による支援 ・行政職員による支援 ・一般市民やメディアからの支持 ・法的整備による支援 ・政府内外の十分なキャパシティ ・十分な資金 6.7 制度化の限界 ■Chapter7 その他の注目すべき熟議の実践 7.1 本章の対象 7.2 世界における熟議の動向 ・アフリカにおける討論型世論調査 ・中南米における熟議のさまざまな実践 ・インドの村落における民主主義 ・国際的・多国間熟議のプロセス 7.3 その他の創造的な熟議プロセスの活用例 ・社会運動への応答としての熟議 ・新たな民主主義の姿をデザインするための熟議 ・憲法起草プロセスにおける熟議と共創.アイスランドとチリ ・デモクラシーフェスティバル ・21世紀タウンミーティング ■Chapter 8 結論 8.1 本書の目的と得られた主な知見 8.2 データの限界 8.3 行動に向けた提案 8.4 今後の検討課題 付属資料A 熟議モデルの諸原則 付属資料B 調査方法 付属資料C 熟議プロセスに関する参考資料 ーーー A5判 ソフトカバー 240頁 送料:300円
-

WORLD WITHOUT WORK AI時代の新「大きな政府」論 | ダニエル・サスキンド
¥4,620
ーーー (出版社による紹介) 「本書は、現代における最大の経済的試練の一つをテーマとしている。迫り来る驚くべき技術革新によって、働いて稼ぎを得るということを全員が全員行なえるわけではない世界が来たら、その先はどうするのか。…この先に待ち構える根幹的な難問、それは分配の問題だ。技術進歩は人類全体をかつてないほどにゆたかにしているかもしれないが、富を分配する従来の方法――労働に対して賃金を払う――が過去のような効果を示さなくなるのだとすれば、そのゆたかさをどうやって分かち合っていけばいいのだろう」 「技術進歩は僕たちを、人間がする仕事が足りない世界へと連れていく。僕たちの祖先を悩ませていた経済問題は消滅し、かわりに3つの新たな問題と入れ替わっていく。1つめは不平等の問題。2つめは政治的支配力の問題。そして3つめは人生の意味の問題だ。…21世紀の僕たちは、新しい時代を築いていかなければならない。安定をもたらす基盤として、もはや有償の仕事には頼らない時代だ」(本書より) イギリスの新進気鋭の経済学者が、21世紀の〈所得分配国家〉〈資本分配国家〉〈労働者支援国家〉を描き出す。 ーーー 四六判 ハードカバー 400ページ 送料:300円
-

人を動かすルールをつくる 行動法学の冒険 | ベンヤミン・ファン・ロイ アダム・ファイン
¥3,960
ーーー (出版社による紹介) 「行動科学が法律を理解する際になくてはならないことを気づかせてくれる、見事な書だ」 ロバート・チャルディーニ(アリゾナ州立大学名誉教授|『影響力の武器』) 「才気あふれ、根源的で、しかも書きぶりは美しく、人の心をつかんで離さないこの本は、ずっと前から必要だった運動のきっかけになるだろう…現状のシステムはあまりに不公正だ。本書はシステムをもっと公正にする明確な道筋を示している」 ローレンス・レッシグ(ハーヴァード大学ロースクール教授|『CODE』) 死刑の効果から、税務コンプライアンスまでを科学する。 「なぜ法律は、人間の行動を改善できないのだろうか。… 紙のうえの法律がどのように行動を形作るのか理解するためには、視点を変えなければならない。…細かいルールをいちいち目で確認するのではなく、人々がルールにどのような反応を示すかという点に注目しなければならない。そうすると、まったく異なるコードが見えてくる。それは行動のメカニズムに関するコード、すなわち行動コードだ。… 私たちの法律を改善して効率を高めるためには、この行動コードを理解しなければならない。ここでは社会科学が大いに役立つ。この分野での数十年にわたる研究の結果、法的ルールに対する人間の反応を形作る行動メカニズムが、いまでは明らかになった。目に見えない行動コードも、科学のおかげで見えるようになった。… 人間の行動を理解してこそ、法律は機能を十分に発揮して私たちの安全が守られるのだ」(本文) 従来の法学を超えた視点から、新たな規範と道徳の可能性を示した、行動法学へのいざない。 ーーー 四六判 ハードカバー 352ページ 送料:300円
-

家族、この不条理な脚本 家族神話を解体する7章 | キム・ジヘ
¥1,980
当店でもロングセラーを続けている『差別はたいてい悪意のない人がする』著者の第二作です。 ーーー (出版社による紹介) LGBTの権利や性教育を認めれば「家族が崩壊」する?私たちを無意識に拘束する「健全」な家族という虚像が作りだす抑圧や差別、排除を可視化する。 [目次] プロローグ 家族という脚本 第1章 どうして嫁が男じゃいけないの? 第2章 結婚と出産の絶対公式 第3章 望まれない誕生、許されざる出産 第4章 役割は性別によって平等に分業できる? 第5章 家族の脚本を学ぶための性教育 第6章 不平等な家族の脚本 第7章 脚本のない家族 エピローグ マフィアゲーム 解説 空気のような存在としての家族、問題の因子としての家族(梁・永山聡子) ★各分野識者が絶賛! 日本の私たちもまったく同じ風景を見ている、同じ滅びの道を辿っている…と何度も思った。 「家族という脚本」を強制し続けることによって個人が抑圧され、幸せに生きていけない社会。 そんなところにいたくないと思う人に、ぜひ届いてほしい。 ――太田啓子(弁護士、『これからの男の子たちへ』著者) 「正常な家族」がある限り、「異常な家族」という烙印(スティグマ)は残り続ける。 家族というシナリオには、女性差別や同性愛差別、優生思想や外国人嫌悪が流れ込んでいる。 いま「家族」を再考するための、最良の一冊。 ――高井ゆと里(群馬大学准教授、『トランスジェンダー入門』著者) ーーー 四六判 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

復刻新装版 憲法と君たち | 佐藤功
¥1,320
日本を代表酢する憲法学者が1955年に書いた、憲法とは何かを最も平易に書いた本。その新装復刻版(2016年刊行)。木村草太さんによる解説も非常にわかりやすく、成立の経緯や憲法の本質までよくわかる。 ふつうの法律ならそれを破る人に対しては警察官や裁判官といった「権力者」が強制的に法律を守らせる。憲法は権力者自身を縛るものであり、権力者自身が憲法を破ろうとするとき、権力を使って憲法を強制的に守らせることはできない。では誰が権力者に憲法を守らせるのか?それは「君たち」だと佐藤功は説く。 四六判 ハードカバー 204ページ 送料:300円
-

ロシア反体制派の人々 | 藤崎蒼平,セルゲイ・ペトロフ
¥3,300
現在のロシアにも戦争に反対する人々がいる。反体制派の人々のプロフィールを通してロシアの現状を知ることができる。解説コラムも充実。著者はペンネームで執筆したとのこと。命懸けの仕事。 ーーー (出版社による紹介) 戦争反対を表明できないでいる何百万ものロシア人―― 彼らの声を代弁する反体制派64名の活動の軌跡と発言、その背後の特殊な社会状況とは? ロシア語の情報源から厳選紹介! 64名の政治家、ジャーナリストのプロフィール、事態を理解するために重要な20のトピックと用語一覧。 ーーー 四六判 ハードカバー 284ページ 送料:300円
-

第七の男 | ジョン・バージャー(著)ジャン・モア(写真)
¥3,080
小説家、批評家、ジャーナリスト、詩人として活躍したジョン・バージャーが、欧州の移民の実情を描き出し、新自由主義的資本主義の問題点に迫る。素晴らしい写真と編集の妙で、良質なドキュメンタリー映画の味わいもある一冊。原著刊行は1975年ながら、英国では2010年に新版が刊行され、今なお読み継がれているという名著。REBELな本です。 A5変型判 ソフトカバー 256ページ 送料:300円
-

2022年のモスクワで反戦を訴える | マリーナ・オフシャンニコワ
¥1,980
モスクワの政府系テレビ局の番組中に乱入して反戦ポスターを掲げたニュース編集者が、その後の逆境を経て国外に脱出するまでの7ヶ月間。民主主義を失い、全体主義へと陥ってしまったロシアからのメッセージ。 ーーー (出版社による紹介文) ロシアのウクライナ侵攻後まもない2022年3月14日。モスクワの政府系テレビ局・チャンネル1のニュース番組中にスタジオに乱入し、反戦ポスターを掲げた女性。この映像は瞬く間に全世界に配信され、一躍時の人となったマリーナ・オフシャンニコワ。しかし彼女の行動は、欧米での賞賛の一方、母親はじめ国内の多数派からは「裏切者」のレッテルを張られ、激しいバッシングの対象に。 同局のニュース編集者として何不自由ない暮らしをしていた彼女をこの行動に駆り立てた理由とは?そして、彼女の周辺のメディア関係者は、ごく少数の支援者の強まる言論統制のなかでどのような行動をとっていたのか?反戦行動後、逮捕・失職・親権制限・自宅軟禁など、次々とやってくる逆境。最終的には娘を連れて決死の国外脱出に成功するまでの激動の7ヵ月間を描く。 ーーー 四六判 ソフトカバー 296ページ 送料:300円