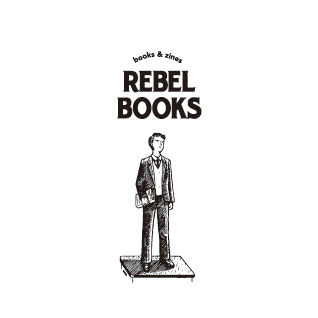-

つくられた日本の自然 「日本の自然」はどのように語られてきたか | 大貫恵美子
¥3,520
ーーー 「日本の自然」は自然の実態そのものではない。それは自然を表象したものであり、長い歴史のなかで文化的に構築されてきたものである。それはいかにしてつくられてきたのだろうか。 古代日本では稲こそが自然であり、収穫の秋はかなしみではなく喜びの季節だった。『万葉集』『古今和歌集』が育んだ四季概念。武士の枯山水。江戸時代の版画に描かれた富士山、水田、桜。こうした表象を「国有化」し、軍国主義に利用した近代。そして「自然」を消費する現代へ。 「自然」という作為を人類学の視座から描く。 【目次】 序章――人類学理論における「自然」 第一章 日本人の宇宙に住まう者たち 第二章 清らかな水田――奈良時代初期における「日本の自然」の誕生 第三章 農耕民族の四季から文化的に定義された四季へ――奈良時代と平安時代 第四章 「日本の自然」としての枯山水――中世 第五章 「日本の自然」としての水田、桜、富士山――江戸時代 第六章 「日本の自然」の国有化と軍事化――近代 第七章 「日本の自然」の家畜化・商品化 第八章 消費主義の文化的基盤 終章 あとがき 図版一覧 註 索引 ーーー 四六判 ハードカバー 248ページ 送料:300円
-

世界をきちんとあじわうための本 | ホモ・サピエンスの道具研究会
¥1,870
世界ってなんだろう、どう「味わう」ことができるのだろう。例えば「呼吸を意識してみる」とかいうことが、きちんと味わうきっかけになるのでは。人類学者たちによる展示から2016年に生まれた本。 ーーー (以下、はじめにより) 世界はあたりまえのようにあって、すでに誰もがあじわっているけれど、それをきちんとあじわおうとすれば、いつもと違った「何か」が必要です。本というものは、そうしたきっかけをあたえてくれるもの。この本は、どのページを開いても、特別なものは何もなく、呼吸や靴や掃除といった、ありふれた日常の話があるだけですが、世界とはそのようなものです。 (略) この本をきっかけに、気づく、探る、指し示すの単純な流れに沿って、みなさんも、毎日の営みのうちにある、それらのあじわいに出会ってもらえればと思います。 ーーー 225mm x 165mm ソフトカバー 92ページ 送料:300円
-

ちいさな手のひら事典 秘密の教え
¥1,980
ーーー 大人気シリーズ、ちいさな手のひら事典!本作のテーマは「秘密の教え」。錬金術、手相術、オカルティズム、心霊主義などに基づく78の秘密の教えを解説します。神秘と象徴の世界を読み解くための鍵がここにあります。 ーーー A6変型 ハードカバー 176ページオールカラー 送料:300円
-

無数の言語、無数の世界 言葉に織り込まれた世界像を読み解く | ケイレブ・エヴェレット
¥3,630
ーーー 私たちは「雪」と「氷」を区別する。それはもちろん、両者が別のものだからだ――しかしもしかしたら、自分が雪と氷を区別する言語を話しているから「別のもの」に思えるのではないだろうか? 言語学者たちはこのような問いに答えるべく、世界中の言語を調べはじめた。するとさまざまな言語に、人々が住む環境の影響を受けて言葉が形作られてきた痕跡が見つかるという。 たとえば高低差2000メートルもの斜面で暮らすある人々は、「左右」にあたる言葉を持たず、ものの位置を常に「上り側」「下り側」で示す。赤道付近に暮らすある人々は、時刻を語る際に空の特定の方角を指差す。ある狩猟民族は、存在しないとされてきた「匂いの抽象語」を持っている。そして温暖な地域の一部の言語は、「雪」と「氷」を区別しない。「言語は、人間の経験の他の側面と切り離してしまっては理解できない」のだ。 かつては、あらゆる言語に共通する普遍的な特徴がいくつもあると考えられていた。しかし、西欧言語とは類縁関係にない言語のフィールド調査が進んだ結果、その仮定は覆されつつある。著者は、むしろ今問うべきは「なぜ言語はここまで多様なのか」だと語る。少数話者言語の消滅が進行する中で届けられた、言語と認知の可能性についての書。 【目次】 はじめに 第1章 未来はあなたの背後にある ――時間 第2章 西に曲がって ――空間 第3章 あなたのキョウダイは誰? ――人やモノのカテゴリー 第4章 グルー色の空 ――色と匂い 第5章 砂漠の氷 ――自然環境への適応 第6章 発話を見る ――対話と文法化 第7章 「nose」は鼻音から始まる ――音と意味のつながり 第8章 〇〇に目がない? ――文法の普遍性と相対性 終章 ーーー 四六判 ハードカバー 328ページ 送料:300円
-

数の発明 | ケイレブ・エヴェレット
¥3,740
ーーーーー “なぜ人類だけが、どこまでも数を数えられるのか。それは、ヒトが生得的に数の感覚を持っているからだ”――数は、私たちの思考に深く根付いている。だからこの説明は、一見するともっともらしい。しかし、アマゾンには数を持たない人々が暮らしている。幼少期、宣教師の父とともにこのピダハン族と暮らし、人類学者となった著者によれば、数は車輪や電球と同じ「発明品」であるという。 「数の感覚」がまったく存在しないというわけではない。ピダハン族や乳児の調査によれば、彼らは数についてごく限られた感覚を持つ。人類は長い間、この曖昧な感覚だけで生きてきたのだ。そして私たちも、幼い頃は数のない世界を見ていた。今、数がわかるのは、かつて発明された数体系を受け継いだからこそである。各地の言語には、身体やさまざまな物を足がかりに発明が起きた跡が残されている。そしてピダハン族のように、発明が起こらなかった例も存在する。 「わかったのは、ピダハンについてではなく、人類すべてに関することだ」。考古学、言語学、認知科学、生物学、神経科学に散らばる手がかりを横断し、数の発明の経緯を探り、その影響を展望する書。 ーーーーー 著者ケイレブ・エヴェレットは、アマゾン奥地に住む少数民族ピダハンの驚くべき言語と認知の世界を描いた名著『ピダハン』の著者D・L・エヴェレットの息子。幼少期に宣教師の父とともにピダハン族の村で過ごしたとのこと。現在はマイアミ大学人類学部教授。 送料:300円
-

ピダハン 「言語本能」を超える文化と世界観 | ダニエル・L・エヴェレット
¥3,740
ーーー (出版元による紹介) 著者のピダハン研究を、認知科学者S・ピンカーは「パーティーに投げ込まれた爆弾」と評した。ピダハンはアマゾンの奥地に暮らす少数民族。400人を割るという彼らの文化が、チョムスキー以来の言語学のパラダイムである「言語本能」論を揺るがす論争を巻き起こしたという。 本書はピダハンの言語とユニークな認知世界を描きだす科学ノンフィクション。それを30年がかりで調べた著者自身の奮闘ぶりも交え、ユーモアたっぷりに語られる。驚きあり笑いありで読み進むうち、私たち自身に巣食う西欧的な普遍幻想が根底から崩れはじめる。 とにかく驚きは言語だけではないのだ。ピダハンの文化には「右と左」や、数の概念、色の名前さえも存在しない。神も、創世神話もない。この文化が何百年にもわたって文明の影響に抵抗できた理由、そしてピダハンの生活と言語の特徴すべての源でもある、彼らの堅固な哲学とは……? 著者はもともと福音派の献身的な伝道師としてピダハンの村に赴いた。それがピダハンの世界観に衝撃を受け、逆に無神論へと導かれてしまう。ピダハンを知ってから言語学者としても主流のアプローチとは袂を分かち、本書でも普遍文法への批判を正面から展開している。 【目次】 目次 はじめに プロローグ 第一部 生活 第1章 ピダハンの世界を発見 第2章 アマゾン 第3章 伝道の代償 第4章 ときには間違いを犯す 第5章 物質文化と儀式の欠如 第6章 家族と集団 第7章 自然と直接体験 第8章 一〇代のトゥーカアガ──殺人と社会 第9章 自由に生きる土地 第10章 カボクロ——ブラジル、アマゾン地方の暮らしの構図 第二部 言語 第11章 ピダハン語の音 第12章 ピダハンの単語 第13章 文法はどれだけ必要か 第14章 価値と語り——言語と文化の協調 第15章 再帰(リカージョン)──言葉の入れ子人形 第16章 曲がった頭とまっすぐな頭——言語と真実を見る視点 第三部 結び 第17章 伝道師を無神論に導く エピローグ 文化と言語を気遣う理由 ーーー 四六判 ハードカバー 416ページ 送料;300円
-

ウォークス 歩くことの精神史
¥4,950
広大な人類史のあらゆるジャンルをフィールドに、〈歩くこと〉が思考と文化に深く結びつき、創造力の源泉であることを解き明かす。レベッカ・ソルニットによる名著。 ーーー (出版社による紹介) アリストテレスは歩きながら哲学し、彼の弟子たちは逍遥学派と呼ばれた。 公民権運動、LGBTの人権運動の活動家たちは街頭を行進し、不正と抑圧を告発した。 彼岸への祈りを込めて、聖地を目指した歩みが、世界各地で連綿と続く巡礼となった。 歴史上の出来事に、科学や文学などの文化に、なによりもわたしたち自身の自己認識に、 歩くことがどのように影を落しているのか、自在な語り口でソルニットは語る。 人類学、宗教、哲学、文学、芸術、政治、社会、レジャー、エコロジー、フェミニズム、アメリカ、都市へ。 歩くことがもたらしたものを語った歴史的傑作。 歩きながら『人間不平等起源論』を書いたルソー。 被害妄想になりながらも街歩きだけはやめないキェルケゴール。 病と闘う知人のためにミュンヘンからパリまで歩き通したヘルツォーク。 ロマン主義的な山歩きの始祖・ワーズワース。 釈放されるとその足でベリー摘みに向かったソロー。 インク瓶付きの杖を持っていたトマス・ホッブス。 ラッセルの部屋を動物園の虎のように歩くウィトゲンシュタイン。 刑務所のなかで空想の世界旅行をした建築家アルベルト・シュペーア。 ヒロインに決然とひとり歩きさせたジェーン・オースティン。 その小説同様に大都市ロンドン中を歩きまわったディケンズ。 故郷ベルリンを描きながらも筆はいつもパリへとさまようベンヤミン。 パリを歩くことをエロチックな体験とみなしたレチフ・ド・ラ・ブルトンヌ。 歩行を芸術にしたアーティスト、リチャード・ロング。 ......歩くことはいつだって決然とした勇気の表明であり、不安な心をなぐさめる癒しだった。 【目次】 第1部 思索の足取り The Pace of the Thoughts 第一章 岬をたどりながら 第二章 時速三マイルの精神 第三章 楽園を歩き出て――二足歩行の論者たち 第四章 恩寵への上り坂――巡礼について 第五章 迷宮とキャデラック――象徴への旅 第2部 庭園から原野へ From the Garden to the Wild 第六章 庭園を歩み出て 第七章 ウィリアム・ワーズワースの脚 第八章 普段着の一〇〇〇マイル――歩行の文学について 第九章 未踏の山とめぐりゆく峰 第十章 ウォーキング・クラブと大地をめぐる闘争 第3部 街角の人生 Lives of the Streets 第十一章 都市――孤独な散歩者たち 第十二章 パリ――舗道の植物採集家たち 第十三章 市民たちの街角――さわぎ、行進、革命 第十四章 夜歩く――女、性、公共空間 第4部 道の果てる先に Past the End of the Road 第十五章 シーシュポスの有酸素運動――精神の郊外化について 第十六章 歩行の造形 第十七章 ラスベガス――巡りあう道 訳者あとがき 注釈と出典 ーーー 四六判 ハードカバー 520ページ 送料:600円(レターパックプラス)
-

海をこえて 人の移動をめぐる物語 | 松村圭一郎
¥1,980
ーーー 人の移動を、ひとりの人生として、世界のあり方として、どう語るか? 「私にとって「移動」という問いは、学問的な探究という枠に収まるものではない。むしろ、互いの人生に巻き込み、巻き込まれた者として課された「宿題」なのだ」(本書「はじめに」より) エチオピアの村で生まれ育ち、海外へ出稼ぎに行く女性たち。長年、村に通う文化人類学者の著者は、その話に耳を傾け、歩みを追いかけてきた。彼女たちの実感やリアリティと、海をこえて移動する人びとを国家の視線でとらえる言説と……。その隔たりをどう問い直し、語るか。考えながら綴るエッセイ。 〈目次〉 はじめに 移動する人が見ているもの 第一章 国境のはざまで 第二章 フィールドで立ちすくむ ・フィールドノート1 女性たちの旅立ち 第三章 人類学は旅をする 第四章 移民が行き交う世界で ・フィールドノート2 変わる家族のかたち 第五章 移民の主体性をとらえる 第六章 移動する何者かたち ・フィールドノート3 知りえない未来を待つ 第七章 「人の移動」という問い ・フィールドノート4 揺らぐ夢の行方 第八章 移動の「夢」が動かすもの おわりに 対話をつづけるために ーーー 四六判 ソフトカバー 288ページ 送料:300円
-

驚異と怪異 想像界の生きものたち | 国立民族学博物館 監修
¥2,970
ーーー 古今東西、この世のキワにいるかもしれない不思議な生きものを一挙集成。国立民族学博物館特別展「驚異と怪異――想像界の生きものたち」公式図録。 ーーー B5変形 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

吟遊詩人の世界 | 国立民族学博物館 監修、川瀬慈 編
¥2,970
ーーー 各地を広範に移動し、詩歌の歌い語りを通して世界を異化するアジア、アフリカの吟遊詩人たちを豊富な図版とともに紹介する。国立民族学博物館特別展「吟遊詩人の世界」解説書。 ーーー B5 ソフトカバー 200ページ 送料:300円
-

世界の呪術と民間信仰 国立民族学博物館コレクション【別冊太陽】
¥2,750
ーーー ◎呪術に関わる研究の最前線がここにある! 人類にとって最も基層的な宗教現象である呪術と民間信仰。その実践的な在り方を、みんぱくが所蔵する膨大なコレクションとともに紹介。文化人類学者がめくるめく世界へと誘う。 ーーー A4変型 160ページ 送料:300円
-

熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きる | ナスターシャ・マルタン
¥2,200
この壮絶なあらすじを読んだ時点で気になって仕方ないですね。読みます。 ーーー (出版元による紹介) 熊に顔をかじられ九死に一生を得た人類学者の変容と再生の軌跡を追ったノンフィクション カムチャツカで先住民族を研究する29歳のフランスの女性人類学者が、ある日、山中で熊に襲われて大けがを負う。その日を境に西洋とシベリアの世界観、人間と獣の世界の境界が崩壊し……スパイの疑いをかけられてロシア情報機関の聴取を受け、たび重なる手術と事件のフラッシュバックに苦しみながらも、身体と心の傷を癒し、熊と出会った意味を人類学者として考えるために、再びカムチャツカの火山のふもとの森に戻ってゆく。 「熊は君を殺したかったわけじゃない。印を付けたかったんだよ。 今、君はミエトゥカ、二つの世界の間で生きる者になった」(本書より) *ミエトゥカ:エヴェンの言葉で「熊に印をつけられた者」。熊と出会って生き延びた者は、半分人間で半分熊であると考えられている。 【18か国で刊行、フランスで11万部のベストセラー!】 【ジョゼフ・ケッセル賞、フランソワ・ソメール賞、マッコルラン賞受賞!】 ーーー 四六判 ソフトカバー 208ページ 送料:300円
-

アラン島【新装版】 | ジョン・M・シング
¥3,520
SOLD OUT
劇作家である著者が1900年ごろにアイルランド西岸沖のアラン諸島に滞在した時の紀行文。厳しい自然と共にある昔ながらの暮らしが生き生きと描かれた傑作。 ーーー 「僕はアランモアにいる。暖炉にくべた泥炭の火にあたりながら、僕の部屋の階下にあるちっぽけなパブからたちのぼってくるゲール語のざわめきに、耳を澄ませているところだ」 19世紀末、文学の道を志しながらも、パリでさえない日々を送っていたJ.M.シング。友人イエィツにすすめられ、アイルランド辺境のアラン諸島に渡ったシング青年は、おじいたちから島にのこる数々の伝承を聞き、酒場や民家の炉端で島人とのつきあいを深め、またあるときは荒海に乗り出した島カヌー(カラッハ)で漕ぎ手たちと生死をともにする。 苛酷な自然の中で独自の文化を育み、たくましく生きる島人たち。その暮らしぶりを誠実に記録した紀行文学の傑作を、気鋭のアイルランド文学者によるみずみずしい新訳でお届けする。 ーーー 四六判 ハードカバー 288ページ 送料:300円
-

ロマニ・コード 謎の民族「ロマ」をめぐる冒険 | 角 悠介
¥2,200
あまりに面白い本。ロマに興味がある人、言語学に興味がある人、世界の知らない部分を知る興奮を味わいたい人に。 ロマ(ジプシー)については個人的にも以前から興味を持っていたのですが、その実情に迫るような本はあまりなく、好奇心が長年宙吊りになっていました。まさか日本人でロマの言語ロマニ語、ルーマニア語、ハンガリー語を自在に(加えてベラルーシ語やドイツ語や英語も)駆使して、各地のロマのコミュニティにどっぷり入り込んで研究しているこんな人がいたとは。そして案の定他の誰にも書けないであろう内容に興奮しっぱなしです。 著者の角悠介さんは東欧を拠点にロマの言葉ロマニ語を駆使してフィールドワークしてきた言語学者。高校卒業後ラテン語を学ぶためルーマニアに留学し、卒業後ハンガリーの大学に進学、ロマの言語ロマニ語を学び、ふたたびルーマニアに戻り、ブカレスト大学のロマニ語学科で言語学博士課程を修了したのち、ルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学で「日本文化センター」所長、文学部ロマニ語講師を務めつつ、神戸市外国語大学の客員研究員としてベラルーシのロマニ語を研究しているという、経歴だけで既に面白すぎる方。 ーーーーー ーーーーー 「分断」がすすむ今の世界で、したたかにボーダレスに生き抜く術がここにある! 私はずっと「定義された世界」を生きていた。それは一種の「仮想世界」であり、彼らが生きる「実世界」とは異なるものであった(本文より) 彼らは毎日激しく生き、死んだように眠る。死んだように眠ったら、生き返ったように目覚める。毎日が誕生日で毎日が葬式だ。だから毎日笑え、泣け、話せ、愛せ、怒れ、歌え、踊れ!(本文より) 情熱的な音楽、舞踏、魔術……神秘的なイメージで捉えられてきたロマ。若き言語学者がロマの世界に飛び込んだ! 見えないルールや境界線に息苦しさを感じている、すべての人に贈る一冊!! ーーーーー ーーーーー 【著者プロフィール】 角 悠介(すみ ゆうすけ) 1983年東京生まれ。言語学博士。 ルーマニア国立バベシュ・ボヨイ大学「日本文化センター」所長・文学部ロマニ語講師。神戸市外国語大学客員研究員。アテネ・フランセ講師(ラテン語)。全日本剣道連盟杖道六段。 2013年より「国際ロマ連盟(IRU)」の議会議員・日本代表を務め、独自の国を持たないロマ民族の最高会議「世界ロマ大会」にも参加。東欧・旧ソ連圏でロマニ語方言研究を行い、言語を通じたロマ民族への貢献により、2019年に北マケドニア共和国ロマ文化団体「ロマノ・イロ」、2022年に「欧州議会」、2023年に「国際ロマ連盟」から表彰・感謝状を授与される。 著書に『ニューエクスプレスプラス ロマ(ジプシー)語』(白水社、2021年)等がある。 ーーーーー ーーーーー 四六判 ソフトカバー 352ページ 送料:300円
-

シシになる。 遠野異界探訪記 | 富川 岳
¥2,530
ーーー [推薦]森田真生(独立研究者)&ドミニク・チェン(情報学研究者) [巻末漫画]五十嵐大介(『海獣の子供』『リトル・フォレスト』) 妖怪、山人、天狗、ザシキワラシ… この世ならざる気配に満ちた遠野には、 いまも見えないものたちの世界がある。 その扉をひらいたのが〝シシ踊り〟だった。 *** 東京の広告代理店にいた1人の若者は、 『遠野物語』を10ページで挫折しながらも 導かれるようにして遠野に移住した。 その地では、人も動物も幽霊も区別しない。 遠野に息づく文化と物語に慄く「よそ者」は、 やがてそれらに魅了され、その深みに引きずり込まれていく。 そして、100年以上前に民俗学者・柳田国男を戦慄させた 「張山しし踊り」との運命的な出会い。 牛の角、龍の鼻、鹿の目を持つ霊獣シシ。 その装束をかぶって舞うシシ踊り。 それは苦難の歴史を抱える地で華ひらいた「鎮魂のための芸能」であった。 シシの担い手となって踊る日々が、 解き明かしていく『遠野物語』に秘められた謎。 いつしか周囲に生まれる、奇跡のような出会いと物語—— 民俗学をベースとした様々な創作活動や文化振興を行い、 いま各界から注目を集める若きプロデューサーが 10年にわたるリサーチと実践、 そして研究者との協業をもとに熱量を込めて書き下ろした、 渾身のデビュー作。 この本を読まずして遠野は語れない。 民俗学の聖地に新時代をもたらす物語がいま始まる! [解題&用語解説:桜井祐(九州産業大学准教授)] [造本設計:吉岡秀典(セプテンバーカウボーイ) ********** 【目次】 はじめに 『遠野物語』の謎を解く 第一章 『遠野物語』の先へ 第二章 シシ踊り 第三章 コロナとお盆 第四章 内なる野生 第五章 魂と共に生きる あとがき 五十嵐大介「ダガイコ ダンヅゴ」 付録 遠野の芸能とシシ踊り 解題 桜井祐「シシとは何か、人はなぜシシになるのか」 ********** 著者紹介 富川岳(Tomikawa Gaku) 1987年、新潟県長岡市生まれ。岩手県遠野市在住。シシ/作家。都内の広告会社にプロデューサーとして勤務した後、2016年に岩手県遠野市へ移住。『遠野物語』に戦慄して以来、民俗学をベースとした様々な創作活動や文化振興を行う。2018年から張山しし踊り(遠野郷早池峰しし踊り張山保存会)に所属。郷土芸能「シシ踊り」に傾倒する日々を送る。著書に『本当にはじめての遠野物語』(遠野出版)、『異界と共に生きる』(生活綴方出版部)。株式会社富川屋代表、遠野市観光協会理事。 ーーー 四六判 ソフトカバー 348ページ 送料:300円
-

ヴァイキング解剖図鑑
¥1,870
研究により、単に乱暴な海賊というイメージではないヴァイキングの姿が明らかになってきているのだそうです。気になる一冊。 ーーー (出版社による紹介) 中世ヨーロッパを席巻し、「ヴァイキング時代」と呼ばれる一時代を築いた「海の覇者」の全貌に迫る! ・コロンブスより早く北米大陸に到達、アイスランドやグリーンランドに入植 ・イングランド王国を支配下に収める ・現在のウクライナやロシアなどの源流となる国家の建設に寄与 略奪に明け暮れる「海賊」という一面だけでは見えてこないヴァイキングの全体像をイラストともにわかりやすく解説。最大の強みであった高度な造船・航海技術や伝説的なヴァイキングの指導者なども紹介、創作者の資料にも役立つ一冊。 ーーー A5 ソフトカバー 140ページ 送料:300円
-

チョンキンマンションのボスは知っている | 小川 さやか
¥2,200
香港の重慶大厦(チョンキンマンション)を拠点とするタンザニア人ビジネスマンの周囲には、独自の互助組合、信用システム、SNSによるシェア経済など、既存の制度に期待しない人々による、合理的で可能性に満ちた生き方があった。当店でもロングセラーとなっている人類学の名作です。 四六判 ハードカバー 276ページ 送料:300円
-

世界の発酵食をフィールドワークする | 横山智 編著
¥2,090
高野秀行さんが『酒を主食とする人々』で取材したエチオピアの飲酒民族デラシャについて、第一人者である新潟大学・砂野唯さんの研究成果がコンパクトにまとまっています。 ーーー (出版社による紹介) 世界各地で、農畜水産物を長期に保存したり、うま味を醸し出す発酵食を調味料として利用したり、栄養豊かな発酵食を主食としたりする人間の営みにフォーカスを当て、地域の食文化における発酵食の位置づけ、発酵食と社会との関係を明らかにする。取り上げる地域は、日本、モンゴル、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマー、ネパール、エチオピア、そしてアフロ・ユーラシアの乳加工品をつくる地域とし、インジェラ、エンセーテ、納豆、ナレズシ、塩辛、魚醤、後発酵茶、馬乳酒、チーズ、バター、醸造酒、餅麹などの発酵食を論じる。 【目次】 序章 人類と発酵食 第1部 主食としての発酵食 1章 酸っぱさに憑かれた人びと――エチオピアのパン類をめぐって 2章 酒を食事とする暮らし――ネパールとエチオピアの人びと コラム1 酵母:人類のために進化し続けてきた微生物 第2部 副食としての発酵食 3章 牧畜民の発酵乳加工とその利用 4章 魚の発酵食をめぐる民族の接触と受容――カンボジア周縁地域を事例に コラム2 生業と「農村食」:発展途上国における農村生活と食の変化 第3部 調味料としての発酵食 5章 近代化・グローバル化による食と味の変容――タイの調味料文化 6章 ラオスの味,パデークの科学 7章 納豆はおかずか調味料か?――日本と東南アジアの納豆の地域間比較 コラム3 納豆菌:その細菌分類学上の位置づけ 第4部 嗜好品としての発酵食 8章 茶を漬けて食べる――北部タイの「噛み茶」文化とその変容 9章 モンゴル国の馬乳酒「アイラグ」 10章 東南アジアの餅麹になぜ新大陸起源の唐辛子が用いられるのか コラム4 乳酸菌:食を支える微生物 終章 フィールド発酵食品学の創出に向けて ーーー 四六判 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

贈与論 | マルセル・モース
¥1,430
「贈与と交換こそが根源的人類社会を創出した」。人類学、宗教学、経済学ほか諸学に多大の影響を与えた不朽の名著、待望の新訳決定版。 ーーー ポトラッチやクラなど伝統社会にみられる慣習、また古代ローマ、古代ヒンドゥー、ゲルマンの法や宗教にかつて存在した慣行を精緻に考察し、贈与が単なる経済原則を超えた別種の原理を内在させていることを示した、贈与交換の先駆的研究。贈与交換のシステムが、法、道徳、宗教、経済、身体的・生理学的現象、象徴表現の諸領域に還元不可能な「全体的社会的事象」であるという画期的な概念は、レヴィ=ストロース、バタイユ等のちの多くの思想家に計り知れない影響とインスピレーションを与えた。 文庫版 320ページ 送料:300円
-

津軽のイタコ | 笹森建英
¥3,080
ーーー (出版社による紹介) 津軽のイタコの習俗・口寄せ・口説き・死後の世界・地獄観・音楽など、彼女たちの巫業や現状とは一体どういうものなのか?長きに亘りイタコに関する研究を行ってきた著者が、調査体験に基づき実態を明らかにする。 【目次】 序 第一章 口寄せ 第二章 名称 第三章 歴史 第四章 巫業 第五章 イタコの生活史 第六章 加持祈祷 第七章 祝福・祈祷祓いの経文 第八章 祭文 第九章 音・音楽 第十章 宗教・信仰 結語 補遺―口寄せの経文―(笠井キヨによる) 引用・参考文献(五十音順) あとがき ーーー A5判 ハードカバー 208ページ 送料:300円
-

世界ぐるぐる怪異紀行
¥1,562
9名の文化人類学者が世界各国地域の調査地で見聞きした怪異を紹介。各国の人の怪異への接し方や、その背景にある意味とは。異文化への知的好奇心をくすぐり、自分の世界「だと思っていたもの」に変化が起きるような1冊。「14歳の世渡り術シリーズ」新刊。 ーーー (出版社による紹介文) 「わからない」ものはどうしてこわいのか。文化人類学者たちが世界各国の怪異をどのように受け取り、紐解くのか。自分の常識がみるみるうちに変化していく、恐ろしくも楽しい世界へご案内。 【目次】 はじめに 1 村津蘭「ベナンの妖術師」…ベナン 2 古川不可知「ヒマラヤの雪男イエティ」…ネパール(クンブ地方) 3 藤原潤子「どうして「呪われた」と思ってしまうの?──現代ロシアの呪術信仰」…ロシア 4 近藤宏「かもしれない、かもしれない……」…パナマ東部(中南米) 5 福井栄二郎「ヴァヌアツで魔女に取り憑かれる」…ヴァヌアツ(アネイチュム島) 6 平野智佳子「中央オーストラリアの人喰いマムー」…オーストラリア(中央部) 7 奥野克巳「幼児の死、呪詛と猫殺しと夢見」…ボルネオ島(東南アジア島しょ部) 8 川口幸大「鬼のいる世界」…中国(広東省) 9 イリナ・グリゴレ「映像によって怪異な他者と世界を共有する方法──ジャン・ルーシュの民族誌映画が啓く新しい道」…日本 ーーー 四六判 ソフトカバー 192ページ 送料:1562円
-

ツンドラの記憶 エスキモーに伝わる古事 | 八木 清
¥2,420
写真良し、ブックデザイン良し。極北の先住民を撮り続けてきた写真家が、彼らの伝承を選び和訳し、写真とともにまとめた一冊。 ーーー (出版社による紹介文) 世界の始まり。生き物たちの奇談。聖霊や魂にまつわる面妖な物語。人間と動物に区別がなく、同じ言葉を話していた時代の記憶。時にユーモラスで、時に難解な「魔法の言葉」を、極北の狩猟民は世代を超えて語り継いできた。探検家ラスムッセンが未開の極地で採録した彼らの伝承を中心に、長年エスキモー文化圏の人々や自然を撮影してきた写真家が選び、和訳したアンソロジー。 ーーー A5変型判 ハードカバー 128ページ 送料:300円
-
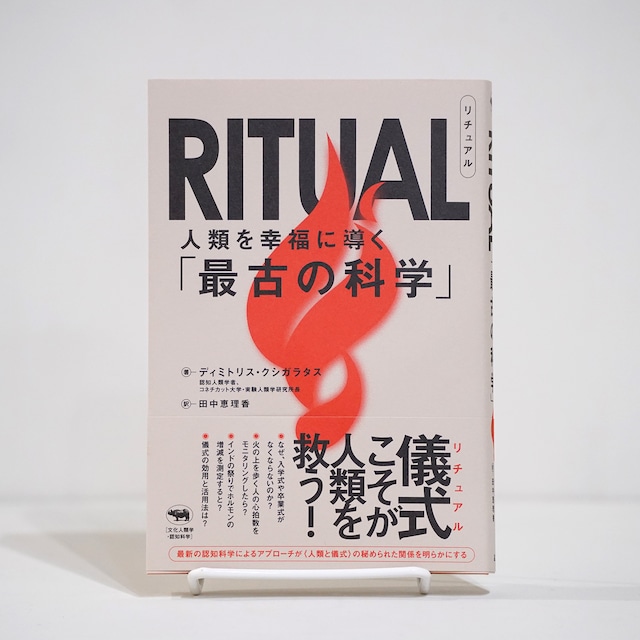
RITUAL――人類を幸福に導く「最古の科学」 | ディミトリス・クシガラタス
¥2,420
ーーー (出版社による紹介文) 世界を変えるための「最古の科学」が「儀式」だった!火渡りの祭礼から卒業式まで、儀式の秘密と活用のヒントを探究する空前の書 生活や価値観が猛スピードで変化する現代。昔からある「儀式」は単調で、退屈で、無意味にみえる。でも、ほんとうに? 認知人類学者の著者は熱した炭の上を歩く人々の心拍数を測り、インドの祭りでホルモンの増減を測定。フィールドに実験室を持ち込んで、これまで検証されてこなかった謎めいた儀式の深層を、認知科学の手法で徹底的に調査する。ハレとケの場、両方にあふれる「儀式」の秘密と活用のヒントを探究する空前の書。 ーーー 四六判 ソフトカバー 368ページ 送料:300円
-

『YOKOKU Field Notes #01 台湾:編みなおされるルーツ』
¥1,320
コクヨ株式会社のリサーチ&デザインラボ「ヨコク研究所」が刊行する『『YOKOKU Field Notes』の第1号が入荷。台湾で様々な活動を営む人々を取材したとても興味深い一冊。コラムも充実。台湾に興味がある方は必読かと思います。写真もデザインもグッドです。 ーーーーー 日本・鹿児島でのフィールドリサーチに端を発しその流れを継ぐ〈YOKOKU Field Notes〉第1号となる本書では、外来文化に翻弄されてきた複雑な歴史を背負う台湾をフィールドに、人々が共に生きるための拠り所となる「ルーツ」を問いの切り口として、5つの事例を巡ります。 ・老朽化した台北の巨大団地街一体に根付き、受け継がれる福祉活動の現場〈南機場〉 ・花蓮の東海岸を舞台に、”魚育”から台湾の海洋食・漁業に光を当てる〈洄遊吧(FISH BAR)〉 ・教師, 親, 生徒という立場が流動する、原住民語のみの実験学校〈Tamorak 阿美語共學園〉 ・アミ族の規範と青年同士の協働のあわいで催される音楽フェスティバル〈阿米斯音樂節〉 ・バンド活動の傍ら農家として地元・旗山のバナナ産業に根ざす〈台青蕉樂團(Youth Banana)〉 これら台湾各地に点在する新たな営みの断片を捉え、変えられない本質としてのルーツに対峙し、自らの存在の意味と居場所を編み直そうとする人々の活動を手がかりに、ルーツの構築可能性について考えます。 ーーーーー ■ 目次 ◎ リサーチの概要 ◎ コラム :台北、市井の生活者より──台湾社会にふれる7つの主題 ◎ 本編 :編みなおされるルーツ 事例1:南機場地区・忠勤里 都市の人生を養い継ぐ 事例2:洄遊吧(FISH BAR) 渦巻く海への感懐 事例3:Tamorak 阿美語共學園 言葉の焚き火を囲んで 事例4:阿米斯音樂節 境界を揺らす “民族” の複音 事例5:台青蕉樂團(Youth Banana) 故郷の根茎が紡ぐ詩 ◎ 編集後話 ーーー B5判 厚さ約8mm 120頁 送料:300円