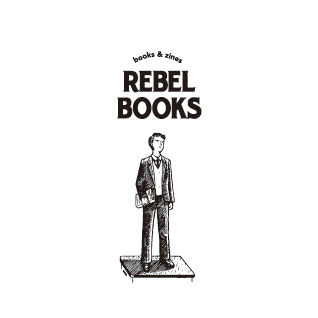-

アニータの夫 | 坂本泰紀
¥1,870
タイトルもカバーもすごくいいですね。あのアニータ事件のノンフィクション。私も買って読もうと思います。 ーーー 「誠意を持って真実をお話しします」。新聞社に勤める記者のもとに、一通の手紙が届く。差出人は、青森県住宅供給公社から14億5000万円を横領し、そのうち少なくとも8億円を妻アニータに送金した千田郁司(ちだ・ゆうじ)だった。 なぜ、千田は公金を自在に動かすことができたのか。 なぜ、その金は海を越え、チリへ送られたのか。 朝日新聞連載時から大きな反響を呼んだ「事件のその後」がついに書籍化。青森からサンティアゴへ、地球の表と裏を往還しながら、記者はふたりの数奇な人生を追う。 犯罪史に残る巨額横領事件の渦中にいた「夫婦」の深淵に迫る、圧巻のノンフィクション。 ーーー 四六判 ソフトカバー 270ページ 送料:300円
-
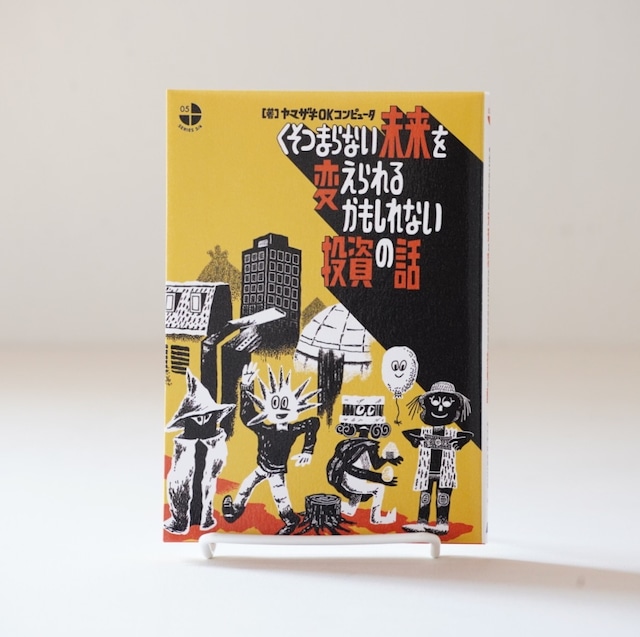
くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 | ヤマザキOKコンピュータ
¥1,540
バンドマン/パンクスである著者が書くのは「くそつまらない未来を変えるには、少しずつでも好きな企業の株を買って保有したら?」という話。幸せってなんだ?お金ってなんだ?未来をどうしたいんだ?ということを根本的に考えて、資本主義のシステムの中でより効果的に戦うためにどうするか。単に金を稼ぐことが目的ではない投資の姿が見えてきます。これほんとすばらしいのでみなさん読んでほしいです。 タバブックスの「シリーズ3/4」は分量的にも読みやすいので誰でもとっつきやすく、おすすめ。 B6版変型(173mm×123mm)・ソフトカバー・148ページ 【送料300円】 『お金信仰さようなら』と『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』セット https://rebelbooks.theshop.jp/items/135117696
-

マージナル・フーディー・ツアー|サラーム海上
¥2,420
行かなければ出会えないまだ知らないうまいものを、世界各地を飛び回って食べまくっているサラームさんのこの新刊は、食べることで世界を味わう喜びに満ちている。写真たっぷりオールカラー。さあ、紙上食紀行に出かけよう! ーーー (出版社による紹介文)ワールドミュージック評論家にして、世界各国を旅して美味しい料理を探し続けるサラーム海上氏による、イスタンブルのミシュラン星付き店、フィンランドのトナカイ料理、オスロの新北欧料理、コートジボワールのフェス飯、ポルトガルの海鮮雑炊、バリ島のバビ・グリンなど、日本ではまだまだ知られていない料理が満載のオールカラー352ページ食紀行! ーーー 四六判 ソフトカバー 352ページ 送料:300円
-

日本で一番美しい県は岩手県である | 三浦英之
¥1,980
ーーー 岩手在住・開高健賞受賞のルポライターが、独自の文化や信仰、暮らしといった「普段着の岩手」を切り取る日本再発見ルポエッセイ。 ーーー 【目次】 はじめに 第一章 神が棲む山々 お化け屋敷 ◉渓谷の歌姫鬼死骸村 ◉不条理の牙 ◉鬼が舞う ◉ナマハゲ ◉断崖絶壁の寺 ◉ネコ神様 ◉震災とオシラサマ ◉消えゆく蚕文化 ◉ほか 第二章 雪国の暮らし 樹齢900年の姥杉日高火防祭 ◉SL銀河 ◉飛龍山の湯 ◉金色堂900年 ◉倉沢人形歌舞伎 ◉鹿踊部の危機 ◉大谷グローブ ◉平笠裸参り ◉最後の蘇民祭 ◉ほか 第三章 クルミの味 わらび餅の春 ◉クルミの味 ◉味噌玉 ◉さくら色のいなりずし ◉10段巻きのソフトクリーム ◉種市のウニ ◉幻の羊羹 ◉亀の子煎餅 ◉寄せ豆腐 ◉甲子柿 ◉ほか 第四章 盛岡の城下町 湧き水の街 ◉ホームスパン ◉チャグチャグ馬コの夏 ◉さんさ踊り ◉闘牛 ◉宮古うみねこ丸 ◉浄法寺の漆 ◉海の中の県境 ◉遠野物語の子孫 ◉ゆっくり苫屋 ◉ほか 第五章 宮沢賢治の子どもたち バラ名人 ◉農民管弦楽団 ◉タクシー運転手 ◉モンゴル人の羊飼い ◉憧れの日本 ◉片腕の記憶 ◉102歳の歌人 ◉ピエロ校長 ◉「あの日」と同じではない ◉ほか おわりに ーー 【本書の特長】 ・稀代のルポライターを魅了した北方文化や風物を、岩手在住者ならではの視点で深堀り。 ・カラー写真(前半)&見開き完結のショートエピソードで、サクサク読めます! ・装丁は岩手県・盛岡市出身の名久井直子さん。美しい装丁・造本にも注目してください。 ーー 著者プロフィール: 三浦英之(みうら・ひでゆき) 1974年、神奈川県生まれ。朝日新聞記者、ルポライター。2021年4月に岩手県一関支局、2022年4月から盛岡総局に勤務。『五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦後』で第13回開高健ノンフィクション賞、『日報隠蔽 南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(布施祐仁氏との共著)で第18回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、『牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って』で第25回小学館ノンフィクション大賞、『南三陸日記』で第25回平和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞、『帰れない村 福島県浪江町「DASH村」の10年』で2021 LINEジャーナリズム賞、『太陽の子 日本がアフリカに置き去りにした秘密』で第22回新潮ドキュメント賞と第10回山本美香記念国際ジャーナリスト賞、『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』で第13回日隅一雄・情報流通促進賞特別賞を受賞。近著に『1945年 最後の秘密』。 ーーー 四六判 ソフトカバー 208ページ 送料:300円
-

大谷のバットはいくら? スポーツを支える道具とひとびとの物語 | 熊崎敬
¥1,760
ーーー 大谷翔平のバット、羽生結弦の靴、北口榛花のやり――知られざるスポーツ道具の「値段」と「秘密」を解剖する36のストーリー。 ーーー 四六判 ソフトカバー 288ページ 送料:300円
-

クィアのカナダ旅行記 | 水上文
¥1,760
ーーー 日本の同性カップルが「難民認定」されたカナダで手にしたたくさんの問い、そして言葉。 日本と違って20年前から同性婚ができて、「LGBTQ先進国」と言われるカナダ。先住民や有色人種への差別が残り、パレスチナ解放をめぐって揺れ動いてもいるカナダ。二度の滞在をもとに、そしてバックラッシュが強まる日本の政治的状況を踏まえながら、その今を記録した著者初のエッセイ集。 ー 【目次】 プロローグ 第1部 トロント・プライド 1 正義を今、求めてる――2023年のトランス・マーチ 2 自分の権利のためにマーチする必要があるか?――2023年のダイク・マーチ 第2部 カナダ再訪 1 再びカナダについて 2 トロント・スケッチ 3 ウィニペグ旅行⑴――赤いドレスとブリュワリー 4 ウィニペグ旅行⑵――人権ミュージアム 5 クィアのカップルセラピー 6 クィアのホームパーティー 7 クィアと空間の政治⑴――パレスチナ連帯キャンプ 8 クィアと空間の政治⑵――「ラファに手を出すな」集会 9 ここにも、そこにも、どこにでも エピローグ ー 【著者略歴】 水上文〈みずかみ・あや〉 1992年生まれ、文筆家。主な関心の対象は近現代文学とクィア・フェミニズム批評。企画・編著に『われらはすでに共にある――反トランス差別ブックレット』(現代書館)。 ーーー 四六判 ソフトカバー 216ページ 送料:300円
-

小さな店をつくりたい 好きな仕事で生きる道 | 井川直子
¥1,760
食に関するノンフィクションの名著をたくさん書かれている井川直子さんの最新刊。「小さな店」とは生き方であり、表明である。小さな店を営む店主の物語。試し読みを読んで今回も名著を確信。 こちらで試し読みができます https://www.naokoikawa.com/posts/58173171 ーーー 今の時代になぜ、「小さな店」だったのか。 彼らはなにも、新しい感覚の店をつくりたかったわけじゃない。 「自分にとって大切なこと」を自身に問いかけた結果である。 ―まえがきより抜粋― 店づくりに関わる取材に長く携わり、独自の視点で、「食」にまつわるノンフィクションを書き続けてきた著者が、10坪あまりの小さな飲食店を営む8人(組)を取材。「この店主にぜひ話を聞きたい」という熱い思いで、独立10年以内の8店を厳選しました。店を始めるまでの経緯や、店にかける思い、店づくりや経営の工夫などを掘り下げ、書き下ろした充実の内容。それは、いずれ独立して店を始めたい人だけでなく、仕事や生き方に悩む人、物づくり興味がある人にも響く内容です。 【目次】 1 カレーを作りたくないって日は一日もない:ダバ☆クニタチ 2 一等地の二等地:赤い部屋 3 生き残る道:デリカ 4 再開発とコの字酒場:ブンカ堂 5 飲食店は、素敵だな:nashwa ナシュワ 6 東京ってなんだろう?:サプライ 7 まずは自分が健全であること:中華可菜飯店 8 つないでいく、という役割:みよし屋 ーーー 四六判 ソフトカバー 192ページ 送料:300円
-

動物たちのインターネット 生きものたちの知られざる知性と驚異のネットワーク
¥2,420
ーーー ネズミは地震の数日前に逃げ、渡り鳥は夜空で会話し、アシカの子どもは人間と動物の関係性を3年越しに記憶していた──。 本書は、最先端の動物追跡技術「ICARUS(宇宙を利用した動物研究のための国際協力)」プロジェクトを通じて明らかになった、動物たちの驚くべき知性と相互作用、そして人間との関係を描いたサイエンス・ノンフィクションだ。 著者のマックス・プランク研究所の生態学者マーティン・ヴィケルスキは、この研究のパイオニアであり、世界各地の研究仲間とともに20年もの人生をこのプロジェクトに費やしてきた。野生動物に超小型の無線タグを装着し、国際宇宙ステーションからその動きを追跡することで、鳥、アザラシ、キツネ、サメ、ゾウ、トンボに至るさまざまな生きものたちの生態をリアルタイムで「可視化」する壮大な構想として実現した。 そのビジョンが形になるまでの、現場で経験した笑いと涙のエピソードの数々。その結果導き出された深い洞察。自然災害の予測、感染症の拡大、気候変動への適応など、私たち人類の未来にかかわるテーマが語られている。 自然を愛する人、科学に心を躍らせる人、そして地球という奇跡の星に思いを馳せるすべての読者に。 【動物たちの目を通して見えてくる新しい世界】へようこそ。 ■内容 キース・ギャディスによる序文 序章:アシカのベビー・カルーソ 第1章 大草原から宇宙へ、そしてまた大草原へ 第2章 鳥の情報ハイウェイ 第3章 小さなカマドムシクイから教わったこと 第4章 初期の追跡調査 第5章 カウボーイのような歩き方になったわけ 第6章 私たちのスプートニク的瞬間 第7章 知っているようで知らないネズミたち 第8章 イカロスへ続く長い道のり 第9章 ヨーロッパへ戻って 第10章 誰が主体か? 第11章 ICARUSの設計が始まる 第12章 野外で動物にタグを付ける 第13章 打ち上げに近づく 第14章 待ちに待った打ち上げ 第15章 タグ開発の険しい道のり 第16章 システムの明暗 第17章 遊ぶ動物たち 第18章 プーチンのウクライナ侵攻 第19章 アリストテレスからフンボルトにいたる宇宙の概念 第20章 地震予知をするウシ、ベルタ 第21章 動物たちのインターネット 終章:さらに速く、さらに遠くまで飛ぶICARUS あとがき:明るい未来への展望 解説 佐藤克文 ーーー 四六判 ソフトカバー 320ページ 送料:300円
-

IN/SECTS Vol.18 特集「THE・不登校」
¥2,420
さまざまな角度から「不登校」について考えた特集。 【内容】 ◯ 誰も通わなくなった学校 山本みなみ ◯ 子を認めることの大切さを改めて思う 近藤雄生 ◯ 子どもたちの〝からだのボイコット〟沢木ラクダ ◯ 子どもの成長を見守れる場所を探す 松村貴樹 ◯ 娘はいま、なにを考えているんだろう? 島田潤一郎 ◯「あきちの学校」で起きたこと 矢萩多聞 ◯ 屋久島の子どもたちの不登校事情 国本真治 ◯ 小・中学生が使うTeen Slang ◯ 歌人・上坂あゆ美インタビュー ◯ 不登校から広がる短歌の世界 ◯ 不登校生動画甲子園ってなんだ! ◯ 僕・私の大切なものスナップ ◯ 緊急誌上調査! 学校てなんなんやろう?アンケート ◯ 聞いてみよう! 不登校の家庭事情 ◯ キムチ部・太田尚樹さんの「おもろい」が肯定のまなざしになる ◯ 廃校になった母校を撮りに行ったら、不登校児童のための教育センター になっていた ◯ 居場所をつくる! 間論の活動 from 福山 ◯ 不登校まったり日記 ◯ 漫画 「山に行ってみたけどダメだった」 ◯ 学校を考えるための映画100選 ◯「教員として思うこと」今野ぽた ◯ 編集部・福永の私のパートナーの明るい不登校 ◯ Neshina room ◯ コラム 星野郁馬/瀬尾まいこ/三田三郎 ◯ 山下睦乃の한국에서의 어느날~a day in Korea 登校編~ ◯ Cover Interview Rosie Ball ◯ 岩井秀人 THE・不登校スペシャルインタビュー ーーー A5 ソフトカバー 132ページ 送料:300円
-

痛いところから見えるもの | 頭木弘樹
¥1,870
ーーー 潰瘍性大腸炎から腸閉塞まで――壊れたからこそ見えるものがある。 絶望的な痛みと共に生きてきた著者がゆく〝文学の言葉〟という地平 ・水を飲んでも詰まる〝出せない〟腸閉塞のつらさ ・痛みでお粥さえ口に〝入れられない〟せつなさ ・オノマトペ、比喩……痛みを「身体で語る」すすめ ・女性の痛みが社会的に「軽視」されてきた理由 ・カントの勘違い、ニーチェの〝苦痛の効用〟…etc. なぜ痛みは人に伝わりづらいのだろう? 「痛い人」と「痛い人のそばにいる人」をつなぐ、かつてなかった本 ーーー 四六判 ソフトカバー 320ページ 送料:300円
-

ソーシャルメディア・プリズム SNSはなぜヒトを過激にするのか?
¥3,740
ーーー 計算社会科学Computational Social Scienceの最先端を走る研究者が、政治的分極化への処方箋を提示する。 「われわれのチームは、何千何万というソーシャルメディア・ユーザーの複数年にわたる行動を記述した億単位のデータポイントを収集してきた。自動化されたアカウントを使って新実験を行ったり、外国による誤情報キャンペーンが与える影響について先駆けとなる調査を実施したりしてきた」 「その真実とは、ソーシャルメディアにおける政治的部族主義の根本原因が私たち自身の心の奥底にあることだ。社会的孤立が進む時代において、ソーシャルメディアは私たちが自身を——そして互いを——理解するために使う最重要ツールのひとつになってきた。私たちがソーシャルメディアにやみつきなのは、人間に生得的な行動、すなわち、さまざまなバージョンの自己を呈示しては、他人がどう思うかをうかがい、それに応じてアイデンティティーを手直しするという行動を手助けしてくれるからである。ソーシャルメディアは、各自のアイデンティティーを屈折させるプリズムなのだ——それによって私たちは、互いについて、そして自分についての理解をゆがめられてしまう」(本文より) ーーー 「本書は、データに基づく解決策が私たちを崖っぷちから救い出してくれるという希望を与えてくれる」 J・ゴルベック(『サイエンス』誌) 「エコーチェンバーが作用しているという仮説に、スマートかつ魅力的に挑戦している」 F・ブルニ(『ニューヨーク・タイムズ』紙) 「ベイルによる発見は、社会の成り立ちについての興味深い結論を教えてくれる」 N・ヘラー(『ニューヨーカー』誌) ーーー 四六判 ハードカバー 240ページ 送料:300円
-

牛疫 兵器化され、根絶されたウイルス | アマンダ・ケイ・マクヴェティ
¥4,400
ーーー 出版社による紹介文 ーーー そのウイルスを制御する力を得たとき、ある人々は根絶を夢想し連帯を訴え、ある人々はそれを兵器に変えた。紆余曲折の歴史をたどる。 牛疫は、数週間で牛の群れを壊滅させる疫病である。徹底的な検疫と殺処分しか防ぐ手段がなく、その出現以来、この疫病は人々に恐れられてきた。 ところが20世紀初め、牛疫ウイルスをワクチンにできるとわかると、牛疫と人々の関係が変わり始める。恐るべきウイルスは、制御可能な力に変わったのだ。 宿主にワクチンで免疫を与えれば、地域からウイルスを排除できる。ある国での成功が他の国でのキャンペーンを誘発し、その先に地球上からの根絶という夢が生まれた。しかしその道のりは、各国の利害にたびたび翻弄されることになった。 その一方で、ワクチンの誕生は、自国の牛を守りながらウイルスで別の地域の食糧生産を攻撃できることを想像させた。一部の国々は第二次世界大戦中に生物兵器研究を開始する。研究は、大規模な根絶キャンペーンの陰で、時にはキャンペーンを主導する国によって、戦後も続けられた。 牛疫は、人類が根絶に成功した2種のウイルスの内の一つである。牛疫は、根絶に至る最後の150年間に、国際的な連帯の意義を示し、そして科学技術があらゆる目的で利用されうることを示した。疫病との戦いを記録し、科学研究のあり方を問う、必読の書。 ーーーーー 出版社詳細ページはこちら https://www.msz.co.jp/book/detail/08887/ ーーーーー 送料:300円
-

【本とコーヒー豆】『センス・オブ・ワンダー』と『読書ブレンド』
¥3,080
『センス・オブ・ワンダー』 当店の選書のカギになっている本であり、当店が最も売りたい本のひとつでもあります。森の小さな草花、夜を照らす満月の光、打ち寄せる波の音。美しいもの、未知なもの、神秘的なものに目を見はる感性「センス・オブ・ワンダー」を育むことの尊さを伝える名著。子どもと一緒に自然を探検し、発見の喜びに胸をときめかせる、そういう大人が必要です。短い文章に美しいカラー写真が添えられた60ページほどの本ですが、人が自然とどう接するべきかを詩情豊かに教えてくれます。ぜひ手元に置いて何度も読み返してください。 ーーーーー 『読書ブレンド』 群馬のスペシャルティコーヒーの草分け、高崎の名店、トンビコーヒーさんに作ってもらった当店のオリジナルブレンドです。粉でなく豆です、150gです。 華やかな香り、チョコレートのような滑らかなコク、やさしい甘みが特徴。酸味や苦みが突出することなく、飲み疲れない、飲み飽きないマイルド感。読書のおともにもぴったりです。 ※酸味が強すぎるのも、苦くて濃いコーヒーも苦手という方におすすめです。その中間の中深煎り、バランスの良い美味しさです。 ーーーーーーーーーー 『センス・オブ・ワンダー』1650円 『読書ブレンド』1430円 送料:300円
-

北欧ではたらく 移住して見つけた私だけの生き方 | 萩原健太郎
¥2,420
好きなことを追い求める。居心地よく働く。日本から北欧へ移住した、14人のリアルストーリー ーーー デンマークの建築家、ノルウェーのデザイナー、スウェーデンの児童文学翻訳家、パティシエ、フィンランドの雑貨店店主、和食店オーナー、etc. 20年にわたり北欧各国を取材してきた著者が出会った、かの地で自分らしい働き方、生き方を見つけた人たち。移住した彼らへのインタビューから、憧れに留まらず、日本と大きく異なる国だからこその生き方を描く。 北欧との出会いや、キャリアを築くまでの奮闘、家族との関係——。自らの意思で、あるいは導かれるように、北欧で働き、生活する彼らの言葉を読んでいくうち、ブームではなく、“スタイル”として北欧を身近に感じられるはず。 ーーー 四六判 ソフトカバー 264ページ 送料:300円
-

高野秀行さんZINE2冊セット
¥2,300
高野秀行さんのZINE2冊のセットです ・チャットGPT対高野秀行 キプロス墓参り篇 ーーー これが高野秀行のリアルな旅! 高野作品の舞台裏が覗けるかのような 〈バックステージ〉ZINE シリーズ第1弾が爆誕! 前代未聞のサブティカル休暇を取得した高野秀行は、春先に亡くなった父親のお墓参りを兼ねてなぜか八王子の菩提寺ではなく、キプロスに向かった。旅の相棒はチャッピーと名付けたChatGPT。 「南(キプロス共和国)から入国した方がいい」「シャトルバスでニコシアの中心部まで行けます」世界の辺境を旅して40年の高野と時代の最先端をいくAI が繰り広げる珍道中。果たして高野秀行に真の休暇はやってくるのか!? ーーー B6判並製 136ページ 1300円(税込) ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーー ・寛永御前試合 ーーー プロレス黄金時代を飾ったプロレスラーたちが、もし江戸の剣豪として暮らしていたら……。 「思いついて3日で書き上げた」という、高野秀行未発表の小説。 高野秀行辺境チャンネルオリジナルのZINEとして登場。 【あらすじ】 古びた瓦版に眠る〝日流〞剣術の秘史。若き天才剣士・三沢虎雄は祝言を前に、師・馬場と宿敵・猪木の果たし合いをめぐる陰謀に巻き込まれる。 必殺・延髄切りと無敵の脳天唐竹割り。 おぞましい〝談合〞の影。勝敗の彼方にある師の覚悟とは何か? 虎雄の恋の行方は? 消された歴史の間から伝説の剣士たちが今ここに甦る!! ーーー B6判並製 72ページ 1000円(税込) ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーー 送料:300円
-

チャットGPT対高野秀行 キプロス墓参り篇| 高野秀行
¥1,300
ーーー これが高野秀行のリアルな旅! 高野作品の舞台裏が覗けるかのような 〈バックステージ〉ZINE シリーズ第1弾が爆誕! 前代未聞のサブティカル休暇を取得した高野秀行は、春先に亡くなった父親のお墓参りを兼ねてなぜか八王子の菩提寺ではなく、キプロスに向かった。旅の相棒はチャッピーと名付けたChatGPT。 「南(キプロス共和国)から入国した方がいい」「シャトルバスでニコシアの中心部まで行けます」世界の辺境を旅して40年の高野と時代の最先端をいくAI が繰り広げる珍道中。果たして高野秀行に真の休暇はやってくるのか!? ーーー B6判並製 136ページ 送料:300円
-

【サイン本】酒を主食とする人々 エチオピアの科学的秘境を旅する | 高野秀行
¥1,980
問答無用の面白さです。 ★サイン本です ★特典ペーパーも付きます ・高野秀行自著解説 ・高野秀行が2024年に読んで面白かった本 ・担当編集杉江さんによる刊行記念コラム ーーー (出版社による紹介) 世界の辺境を旅する高野秀行も驚く " 朝昼晩、毎日、一生、大人も子供も胎児も酒を飲んで暮らす" 仰天ワールド! 話題騒然の「クレイジージャーニー」の全貌が明らかに! 幻の酒飲み民族は実在した! すごい。すごすぎる......。 改めて私の中の常識がひっくり返ってしまった。 デラシャ人は科学の常識を遥かに超えたところに生きている── 朝から晩まで酒しか飲んでいないのに体調はすこぶるいい! 出国不能、救急搬送、ヤラセ、子供が酒を飲む... まさか「クレイジージャーニー」の裏側で、 こんな"クレイジー"なことが起こっていたとは!? 目撃者たった一人のUMA状態の酒飲み民族を捜しに、 裸の王様に引率された史上最もマヌケなロケ隊が、 アフリカ大地溝帯へ向かう! ーーー 四六判 ソフトカバー 280ページ 送料:300円
-

ロッコク・キッチン(書籍版) | 川内有緒
¥2,090
福島・浜通りを貫く国道6号線(通称ロッコク)沿いに住む人々の「みんな、なに食べて、どう生きてるんだろ?」を聞きに行くプロジェクト。問いが普遍的だからそれぞれの物語がこんなに生き生きと、やさしく書かれているのだと思います。鍋パーティーに呼ばれて友達の友達の話を聞いているような感覚で、出てくるどの人の話ももっと聞きたいと思います。とてもよいです。 ノンフィクション作家・川内有緒さんによる、2025年度Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞作。 四六判 ソフトカバー 304ページ 送料:300円 ・冊子版「ロッコク・キッチン」はこちら https://rebelbooks.theshop.jp/items/126577618 ・冊子版「ロッコク・キッチン」とのセットもあります https://rebelbooks.theshop.jp/items/126577537
-

ロッコク・キッチン(冊子版) | 川内有緒 ロッコク・キッチン・プロジェクト
¥1,430
SOLD OUT
福島・浜通りで暮らすみなさんの「食」にまつわるエッセイ12篇と川内有緒さんのエッセイを収録した冊子版ロッコク・キッチンです。とてもよいです。『ロッコク・キッチン』書籍版と合わせてぜひ。 B6 縦(12.8cm×18.2cm) ソフトカバー 96ページ 送料:300円 ・書籍版「ロッコク・キッチン」はこちら https://rebelbooks.theshop.jp/items/126577746 ・冊子版「ロッコク・キッチン」とのセットもあります https://rebelbooks.theshop.jp/items/126577537
-

『ロッコク・キッチン』書籍版と冊子版のセット
¥3,520
SOLD OUT
【書籍版】ノンフィクション作家・川内有緒さんによる、福島・浜通りを貫く国道6号線(通称ロッコク)沿いに住む人々の「みんな、なに食べて、どう生きてるんだろ?」を聞きに行くエッセイ。問いが普遍的だからそれぞれの物語がこんなに生き生きと、やさしく書かれているのだと思います。鍋パーティーに呼ばれて友達の友達の話を聞いているような感覚で、出てくるどの人の話ももっと聞きたいと思います。とてもよいです。 [2090円] 【冊子版】福島・浜通りで暮らすみなさんの「食」にまつわるエッセイ12篇と川内有緒さんのエッセイを収録した冊子版ものです。 [1430円] 送料:300円
-

エッシャー完全解読 なぜ不可能が可能に見えるのか | 近藤滋
¥2,970
ーーー (出版社による紹介) エッシャーの代表作である《物見の塔》《滝》《上昇と下降》などのだまし絵。これらの作品は、一見しただけではそこに錯視図形があるとわからないほど自然に見える。しかし、少しの間をおいて「これはありえない立体だ」と気付いた瞬間、鑑賞者に大きな驚きをもたらす。 この劇的な鑑賞体験はどのようにして作られたのか。エッシャーはまず、絵のあちこちに鑑賞者を誘導するトリックを仕掛け、さらにそれらを手品師さながらに覆い隠していった。そしてトリックの存在を生涯隠し通し、決して語らなかったのだ。 本書は100点を超える図版でだまし絵の制作過程を分解し、エッシャーがかつて5つの作品に仕掛けた視覚のトリックを明らかにしている。エッシャーが制作中に何に悩み、何を大切にしていたかにまで踏み込んでいく。謎解きの楽しさに満ちた1冊。 ー 著者からの7つのヒント 《物見の塔》 なぜ、1階に囚人がいるのか? 《物見の塔》 なぜ、一部の屋根だけが高いのか? 《描く手》 中央の斜めの影は何のためにある? 《上昇と下降》 階段の周りの屋根や塔の役割は何か? 《画廊》 中央の空白は何を隠している? 《滝》 滝壺の位置に何の意味があるのか? 作中の人物のほとんどが、だまし絵のトリックに加担している ーーー 四六判変型 ハードカバー 208ページ 送料:300円
-

オマルの日記 ガザの戦火の下で | オマル・ハマド
¥1,980
ーーー 兄が、眠る前に訊いてきた。 「俺たち、生き残れるかな?」 僕はしばらく黙ってから答えた。 「無理だろうね」 ガザに住み、文学と詩を愛するパレスチナ人青年が 毎日Xに投稿しつづけた、ありのままのガザ。 そこに綴られていたのは… ー 「名もなき人々」のひとり、オマル・ハマド氏による 悲痛な、しかし時に詩のように繊細で美しい文章は、 世界の多くの人の心を動かしています。 (編訳者のことばから) ーーー 著者プロフィール:オマル・ハマド 1996年、パレスチナ・ガザ地区ベイトハヌーン生まれ。大学では薬学を修め、薬剤師の資格を取得。本を愛し、映画を愛し、美しきものを愛し、作家になる夢を温めている。代々縫製業を営む家に育ったことから、ミシンの扱いもプロ級。2019年に大学を卒業後は、薬局や医薬品会社で働いたが、4万5000米ドルを投じて念願のコスメショップを開店。しかし、この店は占領軍によって跡形もなく破壊された。 ーーー 四六判 ソフトカバー 208ページ 送料:300円
-

無数の言語、無数の世界 言葉に織り込まれた世界像を読み解く | ケイレブ・エヴェレット
¥3,630
ーーー 私たちは「雪」と「氷」を区別する。それはもちろん、両者が別のものだからだ――しかしもしかしたら、自分が雪と氷を区別する言語を話しているから「別のもの」に思えるのではないだろうか? 言語学者たちはこのような問いに答えるべく、世界中の言語を調べはじめた。するとさまざまな言語に、人々が住む環境の影響を受けて言葉が形作られてきた痕跡が見つかるという。 たとえば高低差2000メートルもの斜面で暮らすある人々は、「左右」にあたる言葉を持たず、ものの位置を常に「上り側」「下り側」で示す。赤道付近に暮らすある人々は、時刻を語る際に空の特定の方角を指差す。ある狩猟民族は、存在しないとされてきた「匂いの抽象語」を持っている。そして温暖な地域の一部の言語は、「雪」と「氷」を区別しない。「言語は、人間の経験の他の側面と切り離してしまっては理解できない」のだ。 かつては、あらゆる言語に共通する普遍的な特徴がいくつもあると考えられていた。しかし、西欧言語とは類縁関係にない言語のフィールド調査が進んだ結果、その仮定は覆されつつある。著者は、むしろ今問うべきは「なぜ言語はここまで多様なのか」だと語る。少数話者言語の消滅が進行する中で届けられた、言語と認知の可能性についての書。 【目次】 はじめに 第1章 未来はあなたの背後にある ――時間 第2章 西に曲がって ――空間 第3章 あなたのキョウダイは誰? ――人やモノのカテゴリー 第4章 グルー色の空 ――色と匂い 第5章 砂漠の氷 ――自然環境への適応 第6章 発話を見る ――対話と文法化 第7章 「nose」は鼻音から始まる ――音と意味のつながり 第8章 〇〇に目がない? ――文法の普遍性と相対性 終章 ーーー 四六判 ハードカバー 328ページ 送料:300円
-

ピダハン 「言語本能」を超える文化と世界観 | ダニエル・L・エヴェレット
¥3,740
ーーー (出版元による紹介) 著者のピダハン研究を、認知科学者S・ピンカーは「パーティーに投げ込まれた爆弾」と評した。ピダハンはアマゾンの奥地に暮らす少数民族。400人を割るという彼らの文化が、チョムスキー以来の言語学のパラダイムである「言語本能」論を揺るがす論争を巻き起こしたという。 本書はピダハンの言語とユニークな認知世界を描きだす科学ノンフィクション。それを30年がかりで調べた著者自身の奮闘ぶりも交え、ユーモアたっぷりに語られる。驚きあり笑いありで読み進むうち、私たち自身に巣食う西欧的な普遍幻想が根底から崩れはじめる。 とにかく驚きは言語だけではないのだ。ピダハンの文化には「右と左」や、数の概念、色の名前さえも存在しない。神も、創世神話もない。この文化が何百年にもわたって文明の影響に抵抗できた理由、そしてピダハンの生活と言語の特徴すべての源でもある、彼らの堅固な哲学とは……? 著者はもともと福音派の献身的な伝道師としてピダハンの村に赴いた。それがピダハンの世界観に衝撃を受け、逆に無神論へと導かれてしまう。ピダハンを知ってから言語学者としても主流のアプローチとは袂を分かち、本書でも普遍文法への批判を正面から展開している。 【目次】 目次 はじめに プロローグ 第一部 生活 第1章 ピダハンの世界を発見 第2章 アマゾン 第3章 伝道の代償 第4章 ときには間違いを犯す 第5章 物質文化と儀式の欠如 第6章 家族と集団 第7章 自然と直接体験 第8章 一〇代のトゥーカアガ──殺人と社会 第9章 自由に生きる土地 第10章 カボクロ——ブラジル、アマゾン地方の暮らしの構図 第二部 言語 第11章 ピダハン語の音 第12章 ピダハンの単語 第13章 文法はどれだけ必要か 第14章 価値と語り——言語と文化の協調 第15章 再帰(リカージョン)──言葉の入れ子人形 第16章 曲がった頭とまっすぐな頭——言語と真実を見る視点 第三部 結び 第17章 伝道師を無神論に導く エピローグ 文化と言語を気遣う理由 ーーー 四六判 ハードカバー 416ページ 送料;300円