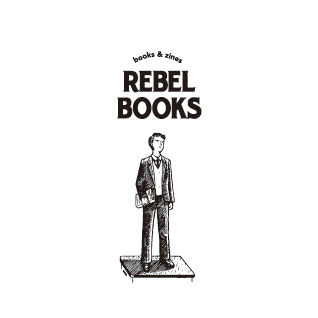-

オマルの日記 ガザの戦火の下で | オマル・ハマド
¥1,980
ーーー 兄が、眠る前に訊いてきた。 「俺たち、生き残れるかな?」 僕はしばらく黙ってから答えた。 「無理だろうね」 ガザに住み、文学と詩を愛するパレスチナ人青年が 毎日Xに投稿しつづけた、ありのままのガザ。 そこに綴られていたのは… ー 「名もなき人々」のひとり、オマル・ハマド氏による 悲痛な、しかし時に詩のように繊細で美しい文章は、 世界の多くの人の心を動かしています。 (編訳者のことばから) ーーー 著者プロフィール:オマル・ハマド 1996年、パレスチナ・ガザ地区ベイトハヌーン生まれ。大学では薬学を修め、薬剤師の資格を取得。本を愛し、映画を愛し、美しきものを愛し、作家になる夢を温めている。代々縫製業を営む家に育ったことから、ミシンの扱いもプロ級。2019年に大学を卒業後は、薬局や医薬品会社で働いたが、4万5000米ドルを投じて念願のコスメショップを開店。しかし、この店は占領軍によって跡形もなく破壊された。 ーーー 四六判 ソフトカバー 208ページ 送料:300円
-

見知らぬ人を認識する パレスチナと語りについて | イザベラ・ハンマード、訳:岡真理
¥2,970
ーーー 「その場にいない私たち、遠くからただ見守るしかない私たちは、これに耐えようと自分の感情を切り離すとき、どのように自分自身を深く損なっているのだろうか」 ジェノサイドが行われているガザ。そこには、人間を人間として見ないという認識の暴力が並走している。そうした認識が変わらないかぎり、暴力は続いていく。 小説は、私たちの認識が変わる瞬間を描いてきた。他者の光とともに、見えなかった現実が姿を現す。パレスチナ系英国人の作家が、サイードを手がかりに、現在進行中の暴力を支える認識の転換の瞬間をうながす。他者を非人間化することで自分が人間であるとする植民地的認識が崩れることで、ともに抵抗し、ともに支えあうための行動を起こす道が開かれる。 岡真理による解説「ホロサイドに抗して」を付す。 ーーー 四六判 ハードカバー 152ページ 送料:300円
-

彼女の最初のパレスチナ人 | サイード・ティービー
¥2,860
パレスチナ移民たちの心情を描く傑作短篇集 ーーー 母国について教えた恋人が救済活動に目覚めていく姿に戸惑う医師 かつて暮らした国への小さな投稿によって追い詰められていく数学者 ルームメイトたちに溶け込むために架空の恋人をでっちあげる大学生 正規採用と引き換えに違法なミッションを引き受けてしまう司法修習生 妻と娘のために禁断の取引に手を伸ばしてしまうプログラマー…… 安住の地となるはずの国で心揺らぐパレスチナ移民たちの日々が、珠玉の9篇に。瀬戸際に追い詰められながら自らのアイデンティティを探る姿を多彩な筆致で綴る、カナダ発傑作短篇集。 ー 〈 編集者からのおすすめ情報 〉 2023年秋以降ガザ地区の惨状が世界中に発信されていますが、パレスチナの人々の苦難は1948年の「ナクバ」(イスラエル建国に際して70万人以上のパレスチナ人が難民化)に端を発しています。本作に登場するのも、祖父母や父母、あるいは本人が故郷を失いやむにやまれずカナダに移り住んできたという人たちです。しかし安住の地を得たと思いきや、ふとした局面で差別や偏見、居づらさを感じ、身を小さくする思いで暮らす人々。そんな移民たちの九つの物語です。パレスチナの苦難の歴史とともに、海外からの移住者が増えている今の日本で、彼らの心の内にも思いを馳せるきっかけとなれば幸いです。 ーーー 四六判 ソフトカバー 272ページ 送料:300円
-

ガザに地下鉄が走る日
¥3,520
アラブ文学を専門とする著者による、パレスチナ問題に関するエッセイ集。40年にわたって何度も現地(周辺国含む)に足を運んだからこそ書ける現地の状況とその変化。パレスチナの現状を伝える情報は日本にはまだまだ少ない中で、近年の情勢も含めて書かれたこの本は、多くの人に読んでもらいたい一冊です。2018年刊行。 ーーーーーーーーーー 出版社による紹介文 ーーーーーーーーーー イスラエル建国とパレスチナ人の難民化から70年。高い分離壁に囲まれたパレスチナ・ガザ地区は「現代の強制収容所」と言われる。そこで生きるとは、いかなることだろうか。 ガザが完全封鎖されてから10年以上が経つ。移動の自由はなく、物資は制限され、ミサイルが日常的に撃ち込まれ、数年おきに大規模な破壊と集団殺戮が繰り返される。そこで行なわれていることは、難民から、人間性をも剥奪しようとする暴力だ。 占領と戦うとは、この人間性の破壊、生きながらの死と戦うことだ。人間らしく生きる可能性をことごとく圧殺する暴力のなかで人間らしく生きること、それがパレスチナ人の根源的な抵抗となる。 それを教えてくれたのが、パレスチナの人びとだった。著者がパレスチナと関わりつづけて40年、絶望的な状況でなお人間的に生きる人びととの出会いを伝える。ガザに地下鉄が走る日まで、その日が少しでも早く訪れるように、私たちがすることは何だろうかと。 出版社の詳細紹介ページはこちら https://www.msz.co.jp/book/detail/08747.html 【送料300円】
-

『アラブ、祈りとしての文学【新装版】』岡真理
¥3,300
ーーー (出版社による紹介文)もしもパレスチナの難民キャンプで傷付いた子どもの傍らにいたなら、私たちはその手をとるだろう。ベツレヘムの街で自爆に赴く青年が目の前にいたら、彼の行く手を遮るだろう。だが私たちはそこにいない。 小説を書き、読むという営みは理不尽な現実を直接変えることはない。小説は無能なのか。悲惨な世界を前に文学は何ができるのか。古くて新しい問いが浮上する。 ガザ、ハイファ、ベイルート、コンスタンティーヌ、フェズ……、様々な土地の苛烈な生を私たちに伝える現代のアラブ文学は多様な貌をもつ。しかし各作品に通奏低音のように響く、ひとつの祈念がある。 「「かつて、そこで」起きた、もはやとりかえしのつかない、痛みに満ちた出来事の記憶。もう帰ってはこない人々。[…]作家は、頭蓋骨に穿たれた二つの眼窩に湛えられた深い闇からこの世界を幻視し、彼岸と此岸のあわいで、起こらなかったけれども、もしかしたら起こりえたかもしれない未来を夢見続ける死者たちの息づかいに耳を澄ます。」 小説を読むことは、他者の生を自らの経験として生きることだ。見知らぬ土地、会ったこともない人々が、いつしか親しい存在へと変わる。小説を読むことで世界と私の関係性が変わるのだ。それは、世界のありようを変えるささやかな、しかし大切な一歩となる。世界に記憶されることのない小さき人々の尊厳を想い、文学は祈りになる。 ーーー 四六判 ハードカバー 320ページ 送料:300円
-

「イスラエル人」の世界観 | 大治朋子
¥1,980
エルサレム特派員として現地で6年半暮らした新聞記者が、イスラエル人の世界観、思考を明らかにする。 ーーー (出版元による紹介) なぜ、世界中から非難されても彼らは攻撃・報復を止めないのか。建国以来、周辺地域との戦闘を繰り返してきた国家の論理がわかれば、イスラエル・パレスチナ紛争の本質も見えてくる。 筆者は2013年3月、エルサレム特派員としてイスラエル、パレスチナ地域に赴任し、2019年9月までの6年半にわたり現地で暮らした。そのころから、筆者の心にはある疑問が深く根を張りはじめていた。2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスがイスラエルを急襲し、イスラエルによるガザへの報復攻撃が長期化するにつれ、その疑問はかつてないほど存在感を増した。 「イスラエルのユダヤ人は、隣人であるパレスチナ市民が苦境にあえいでいるというのに、なぜあれほど無頓着でいられるのか」 「彼らはいったい、どのような世界観の中に生きているのか」 強い疑問が筆者に芽生えたのは、2014年夏の取材がきっかけだった。約50日間にわたり続いたイスラエルとハマスの戦闘。そのうちの25日間、筆者はガザ側から惨状を伝えた。イスラエル軍による無数の1トン爆弾の投下、崩れ落ちた建物の隙間に取り残されるガザ市民と子供たち。目の前に広がる光景は、まさに地獄絵図であった。2009年にアフガニスタンで、米軍と現地の支配勢力タリバンの戦闘を取材した経験のある筆者にとっても、これほど過酷な惨状を目にしたことはなかった。 「イスラエルのユダヤ人は所詮、そういう人たちだから」。そんな風に切り捨てる声も耳にした。だが、事態はそれほど単純ではないと感じた。人間も社会も多面体であり、「闇」だけでなく「光」も存在する。完全な善もなければ、絶対の悪もない。そう信じる筆者は、イスラエル人の内面世界――その〈世界観の森〉に分け入ってみたいとの衝動に突き動かされ、この本を書くに至った。 本書は、紛争や政治心理学の専門家らへの取材、現地の人々との対話を通じて、紛争地に暮らす人々に共通する認識や世界観、そしてイスラエルのユダヤ人に特徴的と思われる思考を明らかにしようとする試みである。戦後80年を迎えた日本にとっても、他者の世界観に触れることは、自らの思考と社会のありようを見つめ直す契機となるはずだ。日々のニュースだけでは見えてこないイスラエル・パレスチナ紛争の本質に踏み込み、私たち一人ひとりがどう関わるべきかを問いかける一冊。 ーーー 四六判 ソフトカバー 320ページ 送料:300円
-

イスラエル vs. ユダヤ人【増補新版〈ガザ以後〉】 | シルヴァン・シペル
¥2,970
二〇二三年年末以降のハマスとの衝突・ガザにおける暴虐について加筆した増補新版。戦闘が周辺諸国へ広がり、世界各地で外国人排斥が熾烈化する中、ユダヤ人ジャーナリストである著者が、イスラエル社会の日常から法制度までを横断し、今後の国際関係を見通す。 【目次】 増補新版への序文――ダヒヤ・ドクトリン:「われわれの世代の運命」 本書を読み解くための基礎知識 前編(高橋和夫) イントロダクション――埋めることのできない溝 最後まで考えを変えなかった父 袋小路に陥った国 武力で解決できなければ、さらに武力を行使する イスラエルに魅了された自民族中心主義者たち 第1章 恐怖を植えつける――軍事支配 世界で最も品行方正なイスラエル軍という嘘 倫理観の喪失 台頭するユダヤ版「クー・クラックス・クラン」 テロとの戦いを指導するイスラエル 第2章 プールの飛び込み台から小便する――イスラエルの変貌 事実を否定するのをやめる アザリア事件が意味すること 無処罰によって粗暴となるイスラエル社会 ファシズムの香り 第3章 血筋がものを言う――ユダヤ人国民国家 「それはイスラエルとユダヤ人にとって悪法だ」 自民族中心主義の勝利 ユダヤ人にとっての「生存圏」 第4章 白人の国――純血主義の台頭 黒人「潜入者」に降りかかる災い 白人至上主義者とのつながり 「ユダヤ人遺伝子」を求めて 第5章 イスラエルの新たな武器――サイバー・セキュリティ 武器輸出という伝統 最先端のサイバー監視技術 制約なく活動する イスラエルとカショギ殺害事件 パレスチナ人の次は、イスラエルの反体制派 第6章 公安国家――権威主義的な民主主義 パレスチナ人だけでなく反体制派ユダヤ人も対象 国内の敵「ベツェレム」 「ボイコット、投資撤収、制裁(BDS)運動」という「張りぼて」 公安機能の滑稽なまでの強化 第7章 絶滅危惧種――イスラエル法制度の危機 最高裁判所は「最後の砦」でなくなったのか 反体制派の当惑 第8章 ヒトラーはユダヤ人を根絶したかったのではない――ネタニヤフの歴史捏造、反ユダヤ主義者たちとの親交 ホロコーストを扇動したのは、エルサレムのイスラム法官なのか イスラム嫌悪という絆 アメリカの福音派とユダヤ人 東ヨーロッパに古くから存在する反ユダヤ主義者との絆 ソロスに対する非難:トランプは反ユダヤ主義者か 第9章 黙ってはいられない――反旗を翻すアメリカのユダヤ人 イスラエルに背を向けたアメリカのユダヤ人たち なぜ今、この変化が生じたのか 民主党の危機 イスラエルを非難するアメリカ人たち 第10章 今のはオフレコだよ――臆病なフランスのユダヤ人 フランス革命から極右のシオニズムへ CRIF(フランス・ユダヤ人団体代表評議会)の正体 臆病なフランスのユダヤ系知識人 第11章 イスラエルにはもううんざり――ユダヤ教は分裂するのか あなたの将来のイスラエル像は? 虚構の上に成り立つ牙城 アメリカにおけるディアスポラの再生 ユダヤ教は分裂するのか 第12章 鍵を握るアメリカの外交政策――トランプ後の中東情勢 トランプの置き土産 バイデンの挑戦:アパルトヘイト国家への対応 イランとの核合意に賭ける 結論 イスラエルvs.ユダヤ人 トニー・ジャットを悼んで 謝辞 本書を読み解くための基礎知識 後編(高橋和夫) 訳者あとがき 原注 ーーー 四六判 400ページ 送料:300円
-

ガザの光 炎の中から届く声
¥2,970
燃やされているのは学校や病院だけではない。人々が、物語が、記憶そのものが焼かれているのだ。侵攻目前に書かれた記録から、私たちは何を聴き取るべきなのか。ガザ地区内外のパレスチナ人作家たちによる様々なエッセイや詩を収録。二〇二二年に原書刊行。 読者のみなさん、この本を読み進めるあなたは、その行動によって人の命を救い、歴史を変える可能性を持っている。あなたには何ができますか? 何をしますか? この本に意味を持たせてくれますか? ――リフアト・アルアライール「ガザは問う」より 四六判 ハードカバー 384ページ 送料:300円
-

パレスチナ/イスラエルの〈いま〉を知るための24章
¥2,200
2023年10月7日以降に編まれた本で、現在の状況を理解するためには中長期的な視座からの検討が不可欠とのことから、比較的最近現地へ長期調査または留学で滞在した研究者、NGOをはじめとする実務家が執筆している。 ーーーーー (出版社による紹介文) 昨今混迷化するパレスチナ情勢を受け、パレスチナに暮らしている人々や故郷を追われた人々の現状、イスラエル国内の世論等、一元的な対立構造ではない多様な視点からパレスチナ問題がわかる別冊エリア・スタディーズが誕生。どのようにガザを支援しているのか、パレスチナ国内のカルチャーや商業活動等、現地の日常も活写したパレスチナ理解の決定版。 ーーーーー 【目次】 パレスチナ/イスラエル全景 パレスチナ難民の移動と現在の居住地 Ⅰ ガザ情勢から見るパレスチナ/イスラエル 第1章 ガザの風景――潮風が香る街道の町[鈴木啓之] 第2章 「封鎖」以前のガザ――うち続く反開発と人びとのスムード[藤屋リカ] 第3章 封鎖下の生活――若者の志を打ち砕く現実[手島正之] 第4章 国際社会とガザ――ガザの人びとと国際人道支援[吉田美紀] 第5章 ハマースとガザ――抵抗と統治のはざま〈山本健介] 第6章 イスラームと政治――その規範的観点と歴史的文脈[ハディ・ハーニ] 第7章 パレスチナと国際人道法――継続する占領と集団罰[島本奈央] 第8章 イスラエルと虐殺の記憶――過剰防衛の歴史社会的背景[鶴見太郎] コラム1 レバノンの政治運動とパレスチナ[早川英明] コラム2 イスラエル南部のキブツ[宇田川彩] コラム3 イスラエル軍の徴兵制[澤口右樹] Ⅱ 日常のパレスチナ/イスラエル 第9章 東エルサレムと人びとの日常――支配の侵食に抗うこと[南部真喜子] 第10章 西エルサレムの人びとと生活――弦の橋が映し出す街の姿[屋山久美子] 第11章 イスラエル国籍のパレスチナ人――「1948年のアラブ人」の日常[雨雲] 第12章 ヨルダン川西岸での人びとの生活――入植地、分離壁、検問所の存在とその影響、生活する人たちの思い[福神遥] 第13章 テルアビブ――世俗的首都の「多様性」[宇田川彩] 第14章 終わりのみえない難民生活――レバノン在住のパレスチナ人[児玉恵美] 第15章 日常の中のナクバ/ナクバの中の日常――歴史の抹消にあらがう人びとの暮らし[金城美幸] 第16章 パレスチナをめぐるもうひとつの争点――LGBTQの権利について[保井啓志] 第17章 入植者植民地主義とパレスチナの解放――地中海からヨルダン川まで[今野泰三] コラム4 教育と日常[飛田麻也香] コラム5 「非日常」の抵抗――パレスチナと演劇[渡辺真帆] コラム6 日常という抵抗、文学という抵抗[佐藤まな] Ⅲ 日本や世界との関わり 第18章 UNRWAの活動と日本――70年続いてきた支援[清田明宏・角幸康] 第19章 国際NGOとパレスチナ社会――人びとの暮らしに寄り添って[大澤みずほ] 第20章 ガザの商品を扱う――フェアトレードの試み[山田しらべ] 第21章 パレスチナ・ガザ地区での医療援助――国境なき医師団の活動を通して見た紛争地医療の課題[白根麻衣子] 第22章 国際協力NGOとアドボカシー活動――日本外交への提言[並木麻衣] 第23章 パレスチナ勤務の経験から――緊急人道支援から大規模産業復興プロジェクトまで[大久保武] 第24章 帝国主義とパレスチナ・ディアスポラ――大英帝国からアメリカ帝国へ[イヤース・サリーム] コラム7 14歳のパレスチナ難民が日本に伝えたこと[新田朝子・石黒朝香] コラム8 転換期にあるBDS運動 ICJ暫定措置命令と対イスラエル武器禁輸[役重善洋] コラム9 『ガザ素顔の日常』上映と映画の力[関根健次] パレスチナ/イスラエルを知るための参考資料 ーーーーー 四六判 ソフトカバー 324頁 送料:300円
-

『三つの願い パレスチナとイスラエルの子どもたち』デボラ・エリス
¥1,540
カナダ人ジャーナリストが2002年に現地に滞在し、パレスチナ・イスラエル両方の子どもたちにインタビューしてまとめた本。インタビューの合間にパレスチナ・イスラエルの歴史や現状も語られています。ふりがなもあり、10才ごろから読めそうですし、パレスチナ問題入門書として大人にもおすすめです。子どもの語ることは素直で、当地の現実がリアルに伝わるように思います。日本語版2006年刊行。 四六判 ハードカバー 192ページ 送料:300円
-

パレスチナを知るための60章
¥2,200
1948年のイスラエル建国以降、中東の火種となってきたパレスチナ。70年近くに及ぶ難民キャンプの暮らし、あるいは「分離壁」に代表されるイスラエルの抑圧的な政策の下にあって、なおアイデンティティを求め続けるパレスチナの人々を描く。 ーーー Ⅰ パレスチナ イメージと実像 第1章 パレスチナとはどこか――アイデンティティの拠り所を考える 第2章 世界に離散するパレスチナ人――繰り返される移動 第3章 パレスチナ人はどんなところに住んでいるのか――難民キャンプから「持ち家」へ 第4章 パレスチナ人は何を食べているのか――オスマン時代から続く伝統的食文化 【コラム1】パレスチナの家庭料理――ひと手間が引き出すおいしさと家庭の誇り 第5章 パレスチナのイエと社会――パレスチナ人のアイデンティティ/39 【コラム2】結婚式 第6章 キリスト教徒として生きる人々――多様な宗教文化 第7章 ドゥルーズ派の人々――イスラエルとアラブのはざまで 【コラム3】「3652年間この地に生きる」サマリア人 第8章 失われた多様性――つくられた「マイノリティ問題」 第9章 ハリウッド映画のパレスチナ人像――捏造される「悪いアラブ」 【コラム4】映画『ミュンヘン』――9・11後のアメリカ社会とパレスチナ問題 第10章 日本人キリスト教徒のパレスチナ・イメージ――パレスチナへの無関心は何によるのか 第11章 『オリエンタリズム』の衝撃――日本でのエドワード・サイード受容 Ⅱ 歴史 第12章 オスマン帝国時代のパレスチナ――蒔かれた紛争の種 第13章 イギリスによる支配――パレスチナ委任統治期 【コラム5】ド・ブンセン委員会――イギリス中東分割政策の青写真 第14章 パレスチナ難民はなぜ生まれたか――忘却されるナクバ 第15章 イスラエルに残ったパレスチナ人――差別・分断と新たな機運 第16章 アラブ・ナショナリズムとパレスチナ・ナショナリズム――シュカイリー初代PLO議長 第17章 パレスチナ解放運動の昂揚――ヤーセル・アラファートとパレスチナ解放機構(PLO) 第18章 アラブ諸国との軋轢――黒い9月とレバノン内戦 第19章 石の蜂起――幻の独立宣言から孤立へ 【コラム6】アメリカン・コロニーの変遷 第20章 オスロ和平プロセス――誕生・展開・挫折 第21章 なぜパレスチナ人はハマースを支持するのか――暫定自治政府の限界 【コラム7】アフマド・ヤースィーン――創設者が描いたハマースの原点と広がり Ⅲ 生活と文化 第22章 ヘブロンの都市生活――イスラーム的伝統の復興 第23章 オリーブと生きる――土地とのつながり、人々の暮らしの象徴 【コラム8】パレスチナのビール・ワイン 第24章 パレスチナの刺繍――モチーフが映し出すパレスチナ 【コラム9】パレスチナの衣装 第25章 難民女性ガーダ――占領と強権の圧力に抗する 第26章 「同胞の“痛み”を我が“痛み”として生きる」――人権活動家ラジ・スラーニとその活動 第27章 タブーに挑む――パレスチナ人ジャーナリストの挑戦 【コラム10】パレスチナ映画――パレスチナ人の実存の視覚的オルタナティブ 第28章 パレスチナ演劇――「失われた」言葉を取り戻す 【コラム11】パレスチナの踊り「ダブケ」 第29章 パレスチナ文学――ナクバから生まれた言葉の力 【コラム12】言葉の「ナクバ」――ヘブライ語で書くパレスチナ人作家 第30章 ウード弾きたちの挑戦――伝統音楽から新しい地平へ 第31章 ポピュラー音楽――革命歌からラップまで 【コラム13】パレスチナ系アメリカ人のコメディアン Ⅳ 世界の中のパレスチナ 第32章 国連の難民救済事業――UNRWAの活動 【コラム14】第一次中東戦争に参加した北アフリカ義勇兵 第33章 アメリカのパレスチナ関与――歴代大統領はパレスチナをどう見てきたか 第34章 ソ連・ロシアの対パレスチナ政策――放置されるロシアの飛び地 第35章 パレスチナ国家の承認――紛争解決の模索 第36章 大国エジプトの変節――宗教、帝国主義、民族主義、そして新しい時代へ 【コラム15】ガザ難民――二人の女子学生と出会って 第37章 隣国ヨルダンの歩み――紛争の展開と国家像の模索 第38章 シリア・レバノンのパレスチナ人――安全と未来を求めて 【コラム16】「イスラーム国」とパレスチナ 第39章 大義を掲げる湾岸諸国――アラブの同胞か、他人事か 第40章 聖都エルサレム――占領下の生活空間 第41章 イスラエルとパレスチナの非対称性――国家主体と非国家主体 【コラム17】パレスチナを旅行する Ⅴ 経済と社会 第42章 パトロン・クライアント関係――近代パレスチナ社会の支配層 第43章 水と土地――権利あるいは空間をめぐる問題 第44章 ヨルダン川西岸の産業――実地調査から見える現状と課題 【コラム18】パレスチナの伝統工芸品 第45章 パレスチナの農業――資源と市場への限られたアクセス 第46章 農村の生活――パレスチナの文化を育む農村の暮らし 第47章 通貨と金融――オスロ合意は何をもたらしたか 第48章 公共部門と公共サービス――あまりに不安定な現実 【コラム19】アンマーンの交通事情と難民 第49章 ワクフ――翻弄されたイスラーム的信託制度 第50章 難民の初等・中等教育――UNRWAの教育と育つ人材 第51章 占領下で学ぶ――大学設立にかけた願いと挑戦 【コラム20】記録し、発信する――パレスチナ研究機構の挑戦 第52章 変遷する障害者福祉――誰も置き去りにしない社会に向けて 【コラム21】分離壁 Ⅵ パレスチナと日本 第53章 対パレスチナ外交――人的交流から資金援助まで 【コラム22】アラファートの日本訪問とIPTIL 第54章 日本に来たパレスチナ人――パレスチナ駐日代表アブドゥルハミードと日本 【コラム23】PLO東京事務所と日本 【コラム24】李香蘭とパレスチナ 【コラム25】「天よ、我に仕事を与えよ」――自己否定と弱者の政治=軍事再考 第55章 日本の経済支援――国際協調と地域安定への試み 第56章 日本の医療支援――パレスチナに根づいた支援 第57章 市民社会による支援――1万キロを越えての連帯とその課題 第58章 イスラエル・ボイコット運動――パレスチナにおける「アパルトヘイト」廃絶への挑戦 第59章 フェアトレード――生活の糧としての伝統工芸 第60章 日本のジャーナリズムとパレスチナ――エルサレム特派員が見たオスロ合意 【コラム26】戦前・戦中の日本とパレスチナ パレスチナを知るための文献・情報ガイド ーーー 四六判 412ページ 送料:300円
-

イスラエルを知るための62章【第2版】
¥2,200
ユダヤ民族主義運動から生まれたイデオロギー国家イスラエルの、その激動の歴史、多様な社会、そして人々の暮らしの素顔を紹介。関係各国の政治的思惑が交差する国際政治のなかで、中東に位置する、この国の現実と未来を見通すための最適の一冊。 ーーー Ⅰ イスラエルという国 第1章 一瞬も退屈のない国――波乱と緊張と多様性の中で 第2章 自然と気候――「肥沃なる三日月地帯」の南端 【コラム1】世界のユダヤ人とイスラエル Ⅱ 歴史 第3章 シオニズム――ユダヤ人ナショナリズムの三つの流れ 【コラム2】「近代シオニズムの父」ヘルツル 第4章 宗教共同体から民族共同体へ――ヨーロッパ近代がもたらした新たな潮流 第5章 パレスチナへの移民の波――ユダヤ人社会の誕生とアラブ系住民との軋轢 第6章 ホロコーストとシオニズム――悲劇をどう解釈するか 【コラム3】アイヒマン裁判――陳腐ではなかった悪 第7章 イスラエル独立と第一次中東戦争――民族の悲願達成、戦いの歴史の始まり 【コラム4】ダヴィッド・ベングリオン――イスラエル建国を実現 第8章 第三次中東戦争と「領土と平和の交換」原則――いまだ達せられない和平の枠組み 第9章 第四次中東戦争から現代まで――45年の変化は大きかったが Ⅲ イスラエル歳時記 第10章 夏に迎える新年――ユダヤの歴史に基づく年中行事 第11章 誕生から死まで――世俗的イスラエル人と通過儀礼 【コラム5】メア・シャリーム 第12章 聖と俗の緊張関係――ユダヤ教とイスラエル社会 【コラム6】労働禁止の安息日「シャバット」 第13章 産めよ育てよ――イスラエルの出産・子育て事情 第14章 教育重視社会――18歳で大きな転機 第15章 体外受精も保険でカバー――柔軟な医療・社会福祉制度 第16章 イスラエルのユダヤ料理――ユダヤ教の戒律と多様性 Ⅳ 多様な言語と社会 第17章 日常語になった現代ヘブライ語――手に入れた自分たちの言語 【コラム7】イディッシュ語やラディノ語の「復活」 第18章 アシュケナジームとスファラディーム――移民とイスラエル社会 第19章 世界中のユダヤ人を受け入れるイスラエル――5人に1人が国外出身 第20章 いろいろ話せて当たり前――多言語社会イスラエル 第21章 活発なメディアとSNS――アプリ開発をリードする高い利用率 第22章 ホロコースト生存者――高齢化と拡大する格差の陰で 第23章 時代とともに変化し続けるキブツ――自然と社会環境の豊かな世界 Ⅴ 政治と安全保障 第24章 多党化と不安定な政権――百家争鳴の政党政治 第25章 右傾化するイスラエル――背景に人口構成の変化 【コラム8】イツハク・ラビン――イスラエル建国からの“象徴” 第26章 「憲法」のない国――将来の憲法を構成する「基本法」を整備 第27章 政治と軍事――安全保障政策は誰が決定しているのか 第28章 国防軍(IDF)とイスラエル社会――政軍関係と聖俗関係との狭間で 第29章 イスラエルの核戦略――曖昧政策と一方的抑止 第30章 兵器産業と武器輸出――最先端システムを支える柱 第31章 変化するイスラエルの脅威概念――新たな類型の出現と対抗戦略 【コラム9】世界有数のサイバーセキュリティ先進国 第32章 情報機関――国家安全保障の根幹 第33章 モサド――失敗の系譜 第34章 軍事作戦と国際法――自衛権の行使か、過剰な軍事力の行使か Ⅵ 経済発展の光と影 第35章 イスラエル経済の変遷――特異な発展モデル 第36章 二つの基幹産業――発展する農業と岐路に立つダイヤモンド 【コラム10】イスラエル産ワイン――ストレートで味わい深く 第37章 イノベーション大国――ハイテク国家の旺盛な起業精神 第38章 日本・イスラエル“ビジネス新時代”――進展する経済関係 第39章 共存の夢は遠く――進むパレスチナとの経済分離 第40章 経済を取り巻く課題――国際協調と社会的不平等の是正 Ⅶ 文化・芸術・若者 第41章 イスラエル文学――ヘブライ語の再生・建国とともに 【コラム11】村上春樹とエルサレム賞――「壁と卵」 第42章 クラシック音楽界――芸術音楽の限界と可能性 第43章 オリエント音楽からジャズまで――移民社会ゆえの多様な音階とリズム 【コラム12】今あつい「ムズィカ・ミズラヒート」 第44章 元気なイスラエル映画――「芸術的なディベート文化」の結晶 第45章 ポスト・シオニズム論争――「新しい歴史家」が提起したもの 第46章 盛んなスポーツ――そこにも政治の影が 【コラム13】二都物語――エルサレムとテルアビブ 第47章 若者文化――サブカルチャーとバックパッカー Ⅷ 外交 第48章 曲折の対外関係――最近は孤立傾向 第49章 米国のユダヤ人――政治的影響力の背景にも変化の兆し 第50章 米国との「特別な関係」――活発に議論されてきた特別さ 第51章 米国政府の対イスラエル援助――大きな規模を維持 第52章 白人福音派とイスラエル――米中東外交を左右するキリスト教シオニスト 第53章 微妙なドイツとの関係――「殺人者の国」からパートナーへ 第54章 日本とイスラエル――高い関心、でも「遠い国」 Ⅸ 中東和平問題とイスラエル 第55章 オスロ和平プロセスとその破綻――行き詰まった和平プロセス 第56章 パレスチナ問題とイスラエル世論――2000年を境に大きく変化 第57章 宗教と政治の複雑な絡みあい――エルサレム問題とイスラエル 第58章 増え続ける入植者人口――パレスチナ人の反対をよそに 第59章 「世界最大の刑務所」ガザ――長期化するハマスの実効支配と封鎖 第60章 アラブ系国民――2割を占めるマイノリティ 第61章 占領上の要衝ゴラン高原――シリアとの最前線 第62章 〈終章〉イスラエルはどこに向かうのか――輝かしい成長と根源的ジレンマ イスラエルを知るための文献・情報ガイド ーーー 四六判 388ページ 送料:300円