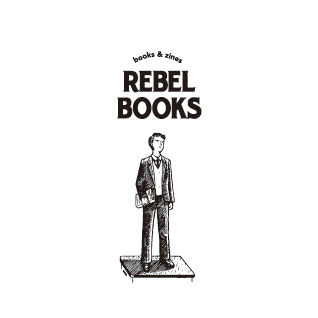-

まちに生きるローカル商店 14事例にみる生き残りかた | URローカル商店研究会(編著)
¥2,530
各地の特色あるローカル商店の事例集です、ご近所の寝具店・金澤屋さんも紹介されています。明確なコンセプトを打ち出してリニューアルし、この時代にもしっかり生き残っている本当にすごいお店です。他のお店の事例も気になります。学びたいですね。 ーーー 銭湯、駄菓子屋、豆腐屋、文具店…。まちに暮らす人々とともに生きながら、その“まち”らしい風景を生み出す“ローカル商店”は、まちの魅力をかたちづくるもの。本書では経営危機を乗り越えた14軒のローカル店の復活ストーリーと生き残りの工夫をまとめた。各店の生き残り術を抽出したポイント、年表やデータも掲載。まちづくり・事業承継に興味のある人に向けた、魅力的で持続可能なまちの実現を目指すための一冊。 ーーー 【目次】 CASE STUDIES まちに生きるローカル商店 CASE 1 銭湯の文化を日本に残し続けたい「サウナの梅湯」(京都府京都市) CASE 2 毎日食べてもらえる日常の豆腐をつくりたい 「安達屋」(東京都世田谷区) CASE 3 まちにある居場所の一つでありたい 「スナック水中」(東京都国立市) CASE 4 創業の地でひとりひとりの眠りを支えたい「金澤屋商店」(群馬県高崎市) CASE 5 子どもたちが集まり憩う風景を残し続けたい「ぐりーんハウス」(東京都町田市) CASE 6 人々の記憶に残る“写真館”という場を残したい「亀甲館写真」(神奈川県逗子市) CASE 7 震災から再生し商店街とともに歩んでいきたい「文化堂」(福島県福島市) CASE 8 歴史ある酒蔵の名と建築を残したい「瀬戸酒造店」(神奈川県足柄上郡) CASE 9 長年愛された“思い出の味”を守りたい 「まぼろし商店/烏森百薬」(東京都港区)/「キッチンビーバー」(東京都千代田区) CASE 10 無添加かまぼこの製造技術を承継したい「吉開のかまぼこ」(福岡県みやま市) CASE 11 新潟銘菓「ゆか里」を残し続けたい「明治屋ゆか里店」(新潟県新潟市) CASE 12 喫茶店という“居場所”を神田のまちに残したい「神田珈琲園」(東京都千代田区) CASE13 旧友との約束“安くてうまい食事の提供”を守りたい善通寺「構内食堂」(香川県善通寺市) CASE 14 木造建築のまちなみと名物パン屋を守りたい「ハト屋パン店」(東京都墨田区) ANALYSIS EDITION ローカル商店が生き残るということ ーーー 四六判変型 ソフトカバー 228ページ 送料:300円
-

社会主義都市ニューヨークの誕生 | 矢作弘
¥2,420
SOLD OUT
2025年のニューヨーク市長選で民主社会主義者でムスリムのゾーラン・マムダニが当選。その背景を解き明かす本。私も今読んでますが非常に面白い。格差の拡大で本当に困った市民たちの切実な声と、その声に耳を傾けるマムダニ。世界のどの都市にも当てはまる市民生活と政治の普遍的な課題と取り組みが見えてくる。これからのニューヨークがどうなるかも興味深いですが、この本を読んでおくとかなり解像度が上がるはず。 ーーー グローバル資本主義の首都ニューヨークの市長に、急進左派の!?民主社会主義者、ゾーラン・マムダニ氏が就任へ!生活苦の労働者・若者の支持を集める背景や氏の人物像、家賃凍結/公共バスや子供保育の無償化/市所有スーパーマーケットの展開/富裕層・大企業増税等の政策を解剖し、他都市やワシントン政治への影響を展望。 ーーー 四六判 ソフトカバー 188ページ 送料:300円
-

〈わたし〉からはじめる地方論――縮小しても豊かな「自律対話型社会」へ向けて | 工藤尚悟
¥2,200
ーーー (出版元による紹介) 人口、産業、文化……縮小するなかで地域は何を持続していくのか?都市と地方の二項対立から脱し、地域が自らの「言葉」で豊かさを語り直したとき、本当の意味での「地方創生」につながる──。 秋田県五城目町で研究する「地域✕サステイナビリティ」の論客、20年の集大成。 ー 【目次】 はじめに 縮小するなかで「地域が続く」とはどういうことか? 第1章 地域の縮小に向き合う〈わたし〉はどこにいるのか ――「地域活性化」という言葉で見えなくなるもの 第2章 人口減少社会の現在地を探る ――縮小する社会をどうデザインするか 第3章 「地域が続いていく」とはどういうことなのか ――流れのなかの〈あいだ〉として地域を見る 第4章 五城目町は、なぜ〈わたし〉を取り戻せたのか ――つながりと企てが頻発するまちづくりのための5つの仕組み 第5章 自律対話型社会にむかって ――地域ごとの豊かさをつくりだす「風土のサステイナビリティ」 おわりに 〈わたし〉を起点に、対話をはじめよう ーーー 四六判 ソフトカバー 280ページ 送料:300円
-

都市と路上の再編集 – LIVE NOW DEVELOPMENT –
¥2,200
まずタイトルが素晴らしいですよね。 「トップダウンで都市開発をする人々と、ボトムアップでまちづくりに参加するプレーヤーが手を取り合うには、どうすればいいのか?」という問いに基づき、「大企業や自治体とも手を取り合って、まちづくりに関わっているプレーヤーたちの話」を集めた本。 早速読み始めてますがとてもいいです、各事例深く掘り下げていて刺激満載。 たくさん発注し、先行入荷してます、みなさんぜひお読みください! ーーー 【目次】 ◆LIVE NOW DEVELOPMENTとは p4 はじめに──まちづくりの思考、手法、関係性を“再編集”する p10 HOME / WORK VILLAGE 小野裕之/まちづくりはビジネス or カルチャーじゃない ◆今、くらしに求められていること p24 建築家 山本理顕/変えるべきは「働く」と「住む」の分断 p36 解剖学者 養老孟司/脳化された現代にこそ「田舎」が必要 ◆今、再編集への期待が高まるもの p50 グランドレベル 田中元子/論理性に偏った社会に、非論理性の文鎮を乗せたい p62 Dprtment 佐々木大地/ストリートの心×パブリックの視点 p70 SHONAI 山中大介/“個”の自由な往来が、地方都市をおもしろくする p78 西村組 西村周治/ロマンとそろばんの両輪を駆動するために p86 真鶴出版 川口瞬/心を入れて、残したい風景を言語化する p94 加和太建設 河田亮一/まちづくりが「映画制作」にまで発展 ◆手を取り合って生まれている新たな動き p106 さとゆめ 嶋田俊平/「ふるさと」と「情緒」の関係性を言語化し、実装する p116 創造舎 山梨洋靖/まちづくりは究極、人づくり p126 いまでや 小島雄一郎/自宅の1階に、好きな店を誘致できた理由p136 アメリカヤ 千葉健司/横のつながりを最大化し、目的地になる町にリノベーション ◆おわりに 互いに必要とする間(あいだ)の存在 p148 n’estate 櫻井公平 × ジモコロ 徳谷柿次郎/今、求められる「価値観の反復横跳び」 ーーー 価格:本体2,200円(税込) 仕様:A5 変型/160 ページ 発行:風旅出版(株式会社Huuuu) ーーー 送料:300円
-

A GUIDE to KUROISO
¥3,000
栃木県黒磯のガイドブック。『ジモコロ』や長野県の移住サイト『SuuHaa』を手がける編集の会社Huuuuが丹念に取材して制作。驚くほど良いお店が多数掲載されていて読んでるだけで刺激を受けるし、若い人が引っ越してきて仕事が生まれていて、その循環すごいなと感じます。黒磯に行ってみたくなること間違いなし。「街のあり方」と「街の見せ方」を考える人の、大いに参考になるであろう一冊でもあると思います。 送料:300円
-

まちは言葉でできている | 西本千尋
¥1,980
ーーー 都市計画の中で妊婦や子どもや障害者や女性や高齢者の存在が想定されていないこと、安全で快適な空間のためにホームレスの人々が排除されてきたこと、「公園まちづくり制度」の名の下に緑豊かな公園がなぜか消えていくこと、歴史ある町並みや昔ながらの銭湯を残すのがこんなにも難しいこと、「創造的復興」が被災者の生活再建に結びつかないこと―― 目の前にあるまちは、どのようにして今あるかたちになったのか。誰がそれに同意したのか。住民にまちを変えていく力はあるのか。「みんなのため」に進められる再開発の矛盾に目を凝らし、その暴力性に抗っていくために、専門家や行政の言葉ではなく、生活にねざした言葉でまちを語り直したい。 “すベて景色の前には「言葉」がある。わたしたちは「言葉」でまちをつくってきた。ある日突然、そこにブルドーザーが現れるのではない。必ず、その前に「言葉」がある。だからその「言葉」が変われば、ブルドーザーの現れ方も、立ち入り方も、去り方も変わり、まちのかたちも変わる。”(本文より) 「まちづくり」に関わるようになって約20年、現場で味わった絶望と反省を、各地で受け取った希望を、忘れないために記録する。ごくふつうの生活者たちに捧げる抵抗の随筆集。 ーー 【目次】 はじめに 第1部 再開発の言葉 第1回 モア4番街のオープンカフェ 第2回 神宮外苑の再開発 第3回 生きられる町並み 第4回 誕生を祝うまち 第5回 「東京大改造」は持続可能な開発か? 第2部 足もとの言葉 第6回 自分の家のように感じる(でも家ではない) 第7回 頼りなく外へ出る 第8回 百年の森林(もり)を生きる 第9回 「取るに足りなさ」との闘い 第10回 コモンズを破壊しない建築は可能か? 第11回 「創造的復興」――能登から問い直す 第12回 普通に一緒にいる――外国ルーツの人々 第13回 足裏の記憶――『大邱の敵産家屋』と森崎和江 第14回 覚えていたい――認知症と高齢者 おわりに ーー 著者プロフィール: 西本千尋〈にしもと・ちひろ〉 1983年埼玉県川越市生まれ。NPO法人KOMPOSITION(居住支援法人)理事/JAM主宰。2003年から商店街、景観、観光、歴史的建築物、町並み保存、エリアマネジメント、居住支援等、各種まちづくりに携わる。跡見学園女子大学兼任講師。 ーーー 四六判 ソフトカバー 216ページ 送料:300円
-

オン・ザ・ロード2 スーパーウェルビーイング | 指出一正
¥2,530
ーーー 日本関係人口協会刊行書籍 第一弾! 刊行後忽ち3刷を重ね、韓国版も刊行された大好評の前作 『オン・ザ・ロード 二拠点思考』待望の続編! まちや社会がウェルビーイングであるためにはどうしたらいいのか。 地方創生、関係人口、二地域居住など、地域の課題を解決するヒントを詰め込んだ1冊! SNSでも使える!編集長秘伝の『指出流 伝わる文章の書き方11箇条』を収録。 今、読むべき!心が温かくなる親子の関係『僕のスーパーウェルビーイング日記』完全収録。 【目次】 序章:「オン・ザ・ロード」がつなぐ人と場所 大切なことはみんな「移動」が教えてくれた 1章:関係人口の未来をつくる7つのキーワード 「スーパーウェルビーイング」の時代 2章:人を幸せにするまちの共通点 「関係案内所」のこれからを考える 3章:思索の足どり2025 スーパーウェルビーイングは日常のなかにある 4章:ローカル観をアップデートする3つの視点 東京というローカル、環世界、ヴァナキュラー 5章:指出流!スーパー読書術・文章術 まちづくりにも人生にも活かせる考え方 僕のスーパーウェルビーイング日記 おとうとまことの釣り物語 ーーー 四六判 ソフトカバー 368ページ 送料:300円
-

新版 日本のまちで屋台が踊る
¥2,530
何もなかった道や広場に屋台が現れると、人が集まる「場」に変わる。プライベートとパブリックの境界を溶かしてしまう屋台の現代的意義を探る一冊。初版が完売した人気書籍に新規コンテンツを追加して「新版」として発売。 ーーー それぞれの屋台にはドラマがある!なぜ屋台に行き着き、どう屋台をまちで動かすか。飲食や健康相談など屋台実践者たちへのインタビューと、文化人類学、社会学、哲学、都市史、政治学など分野を超えた専門家のレクチャーを通して、現代の「屋台」から暮らし方、働き方、社会への関わり方を考える。屋台はまちへとび出し、踊る。 中村睦美・今村謙人・又吉重太 編/今村謙人・モリテツヤ・鈴木有美・神条昭太郎・孫大輔・小川さやか・南後由和・鞍田崇・石榑督和・栗原康・阿部航太・笹尾和宏 著 ーーー 四六判 ソフトカバー 284ページ 送料:300円
-

アメリカで復活する 中心市街地・商店街 コミュニティが育むスモールビジネス | 矢木達也
¥2,750
タイトルから心を掴む一冊。米国の人口5000〜5万程度の小さな街で、人が集まる「コミュニティとしてのメインストリート」が復活する事例が増えているのだそうです。学びたいですよね。 ーーー かつてモータリゼーションによって衰退したアメリカのメインストリート(商店街)やダウンタウン(中心市街地)が、2010年以降、各地で活気を取り戻し始めている。 新築ではなく歴史ある建物の再生によって経済が循環し、地域がよみがえった例も少なくない。 本書では、どのようにしてこの「復活」が実現したのか、その背景と成功の鍵を豊富な事例とともに解き明かす。 ーーー B5/並製/208頁/オールカラー 送料:300円
-

公共デザイン学入門講義 コミュニティセンスを生む演出術 | 権安理
¥2,200
ーーー まちを歩く。人と語る。場をつくる。――そんな日常の風景や人とのつながり、身近なモノの工夫のなかに〈公共〉はひそんでいます。 『公共デザイン学入門講義』は、公共を「むずかしい議論」ではなく、生活のシーンから考え直す図版を多用した入門書です。 キーワードは〈コミュニティセンス〉。公共を「生きられるシーン」としてとらえ直します。 登場するのは、コミュニティフリッジ、路上スナック、廃校活用、渋谷のJINNAN MARKETといった現代のまちづくり・地域活性化の事例。豊富な写真や図、イラストとともに、公共空間や地域デザインがどのように開かれ、人々がどう関わり合うのかを描き出します。 難解になりがちな哲学や社会論も、やわらかい文体と生活に根ざした題材で解説。社会人・実践家から学生まで、幅広い層に開かれた新しい公共入門。高校の「公共」科目や探究学習にも役立つ一冊です。 ーーー ●あなたのセンスが、〈まち〉を変える。 ●これからは、公共をつくる感覚=コミュニティセンスの時代! * 【目次】 はじめに 序章 「コミュニティセンスとデザイン」をエピソードから考える 第1部 公共デザインのWhatとHowを知る 第1章 公共デザインを哲学的に考える――コンビニから始めよう 第2章 「デザインの本質=演出」を事例から考える――カフェとポスターから始めよう 第2部 公共デザインの事例と法則を知る 第3章 事例を知るⅠ――セット(道具・配置)の演出 第4章 法則を知るⅠ――反転の法則 第5章 事例を知るⅡ――シーン(場面)とステージ(舞台)の演出 第6章 法則を知るⅡ――ドラマの法則 第3部 公共デザインを復習する 終章 センスのフィロソフィー(哲学) 文献/ホームページ、インスタグラム、note など/付記/あとがき ーーー 四六判 ソフトカバー 192ページ 送料:300円
-

サードプレイス コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」 | レイ・オルデンバーグ
¥4,620
今や広く知られるになったサードプレイスという概念を提唱した場づくりにおける重要書。スターバックスはサードプレイスを戦略上の重要概念としてきたことが知られていますが、著者オルデンバーグは後に「スターバックスは自分の定義するサードプレイスではない」と答えていたりもします。サードプレイスとは何なのか、あなたにとって「とびきり居心地よい場所」とはどこなのか。あらためて考えるきっかけとしたい一冊。 ーーー 居酒屋、カフェ、本屋、図書館…情報・意見交換の場、地域活動の拠点として機能する〈サードプレイス〉の概念を社会学の知見から多角的に論じた書、待望の邦訳。 第一の家、第二の職場とともに、個人の生活を支える場所として都市社会学が着目する〈サードプレイス〉。そこでは人は家庭や職場での役割から解放され、一個人としてくつろげる。 著者オルデンバーグが、産業化‐効率化‐合理化を進めてきたアメリカ社会と、そのもとに展開されてきた都市計画が生んだ人々の孤独の問題を批判しつつ、地域社会を再び活気づけるための〈サードプレイス〉として注目するのが、地域に根ざし、長く人々に愛されつづけている地元の飲食店だ。「見知らぬ者どうしの気楽で面白い混交」を創り出し、情報交換・意見交換の場所、地域の活動拠点としても機能する、地元の飲食店や個人商店ならではの特質が社会学の知見をもとに照らし出される。 第I部では、〈サードプレイス〉の機能、特徴、物理的な条件が詳細に解説され、第II部では、イギリスのパブやフランスのカフェなどの具体例から、文化や国民性が生み出す〈サードプレイス〉のヴァリエーションが紹介される。さらに第III部では、社会・政治面での〈サードプレイス〉の課題とその解決策が論じられる。 全編を通じ、オルデンバーグが〈サードプレイス〉に向ける期待は揺るぎない。そこには長年「とびきり居心地よい場所」に親しみ観察してきた者の実感と、「コミュニティの問題は住民の力で解決できる」という市民魂がみなぎっている。 店舗設計、都市計画、マーケティング、地域社会づくりの分野に刺激を与えつづけてきた書の待望の邦訳。 ーーー 四六判 ハードカバー 528ページ 送料:600円(レターパックプラス)
-

涌出 wakiizu 001
¥1,760
長野県の地域探訪誌、その創刊号。各地域で起きていることをまとめた気になる記事がたっぷりと。写真とデザインがとても良いです。制作・発行は長野県在住のメンバーで構成する編集デザインチームであり出版レーベル「涌出 WAKIIZU」。 ーーー 【目次】 特集1_ 木曽谷 / なぜ今、次々と狼煙があがるのか。木曽に吹く“風”をたどる 旅へ。/ 9 特集2_ 小布施 / 地元の先輩と、若き移住者が一緒にまちをつくる。人が人を呼ぶ町、小布施の現在地。 / 25 特集3_ 上田 / 映画館は公共空間であり、記憶を留める装置でもある。100年 分の記憶をつむぐ「上田映劇」/ 41 連載_ 僕と長野 / 皆川明 / 52 特集4_ 伊那 / 森は理想を語ることすら難しく、答えはないに等しい。それで も森に伴走し、課題を解きほぐし、伝える「やまとわ」 / 55 連載_ 手仕事の信州 / 滝澤充恵 / 66 連載_ 本のなかの山 / 石垣順子、小野村美郷 / 68 連載_ 信州の発酵 / Son of Smith Hard Cider /59醸 / 70 ーーー A5変型 ソフトカバー 80ページ 送料:300円
-

世界に学ぶ自転車都市のつくりかた | 宮田浩介 編著
¥2,640
環境にも良く、健康にも良く、街の小さなお店にも寄りやすい。実は未来の乗り物は既にあった、それは自転車。水素自動車でも空飛ぶ車でもなく。 世界の自転車先進都市の事例、滋賀県の事例、これからの日本の自転車空間への提言、自転車空間設計のノウハウ図解まで、写真や図もたくさん使いながら解説。すばらしい本です。 地方の人は「車がないと生きていけない」という固定観念にとらわれていますが、高崎・前橋をはじめとした群馬県平野部は地形的にアップダウンも少なく、積雪も少なく、自転車向きの土地です(唯一強風があるのですがまあなんとかなります)。日常の足は自転車があれば事足りるという地域も少なくありません。事実私はそのように生活しています。これからの街のあり方を考えるうえで自転車は必須の視点だと思います。 ーーー (出版社による紹介文)子どもも大人も使える便利でエコで健康的な移動手段、自転車。その利用を伸ばす環境整備が、車より人が中心の交通への回帰のため、持続可能な社会のために、世界で進められている。各地の「おのずと自転車が選ばれる」まちづくりを、ニーズ、デザイン、都市戦略から解説し、自転車×まちの未来を展望。設計カタログも収録。 ーーー 四六判 ソフトカバー 256ページ(カラー64ページ) 送料300円
-

15分都市の実践 世界に学ぶ地球規模の課題解決
¥2,970
私は日ごろ自宅と仕事場含めほとんど自転車15分圏内で過ごしていて、とても快適です。都市をこの観点から分析・考察することは大いに価値があるはず。非常に気になる一冊。 ーーー (出版元による紹介) 徒歩・自転車・公共交通により15分でアクセスできる範囲に生活機能を集める「15分都市」構想。孤立から気候変動まで地球規模の課題に挑むアイデアを先駆けて実践する、パリ、ミラノ、ポートランド、メルボルン、釜山などの都市政策について、提唱者自らが解説した『The 15-Minute City』待望の邦訳。 ーーー A5 ソフトカバー 264ページ 送料:300円
-

アクティブシティ戦略 暮らしているだけで健康になるまちづくり
¥2,640
ーーー (出版元による紹介) “健康で幸福に暮らせるまち”はどうつくれるか? 生活・運動習慣をめぐる最新のエビデンスから健康観を捉え直し、15分都市やウォーカブルシティ、プレイスメイキングなど国内外の先進都市による施策例を紹介しながら、現代人を健康行動に誘うまちづくりのポイントについて解説。「健康人口」が増えるまちの条件がわかる1冊 ーーー 四六判 ソフトカバー 248ページ 送料:300円
-

ネイバーフッド都市シアトル リベラルな市民と資本が変えた街 | 内田奈芳美
¥2,750
ーーー ジェントリフィケーションの功罪と向き合う リベラルでアクティブな市民やオルタナティブなスモールビジネスが育む多様なネイバーフッドに、アマゾン、スターバックス、マイクロソフトら世界的企業が進出し、西海岸の地方都市を米国有数のスーパースター都市に変貌させた。ジェントリフィケーションがもたらす功罪、それに人々がどう向き合ったか、躍動感あふれる軌跡。 ーーー 四六判 ソフトカバー 240ページ(カラー16ページ) 送料:300円
-

経営戦略としての都市再生 チームによるエリアマネジメントの実践と手法 | 後藤太一+リージョンワークス
¥2,970
ーーー 30年の実践から導く戦略・組織・事業づくり まちづくりの成果が見えない。経営という視点がなく、各取り組みの成果がまち全体に波及しないからだ。福岡、神山、渋谷、福井で都市の経営を30年実践してきた実務のプロが、戦略・組織・事業づくりを体系化。まちづくりを構造改革し、職能をアップデートする希望と武器を獲得できる待望の書。馬場正尊氏、藻谷浩介氏推薦。 ーーー A5変型 ソフトカバー 272ページ(カラー16ページ) 送料:300円
-

アムステルダム ボトムアップの実験都市 | 根津幸子
¥2,970
アムステルダムに見られるサーキュラーエコノミーや都市再生の先進プロジェクトには、市民のアイデアから生まれたものが多いのだとか。アムステルダムという都市の素顔と市民の躍動感を伝える一冊。 ーーー 個人のアイデアで街を変えるプロジェクト集 低湿地に暮らすオランダ人は環境意識が高く、フレキシブルな思考力とスピーディな実行力に長けている。2000年代以降、建築家やクリエイター、市民らが始めたサーキュラー・エコノミー、リジェネラティブ・デザインの先進地では、個人のアイデアがどのように人を動かし街を変えているのか。現地建築家が紹介するプロジェクト集。 ーーー 四六判 ソフトカバー 272頁(カラー128頁) 送料:300円
-

公務員のためのマーケティング講座 成果を最大化する政策・施策・事業づくり
¥2,640
ーーー (出版元による紹介) 厳しい財政状況や人手不足の中、限られた経営資源をもとに、実施する事業の成果を高め、多様化した住民ニーズや災害に迅速かつ柔軟に対応していくための有効な手段が「マーケティング」だ。マーケティング戦略の5つの実践ステップと、マーケティングの実効性を高めるためのコーディネーションを実例とともに学ぶ入門書。 ーーー A5 ソフトカバー 200ページ 送料:300円
-

A GUIDE TO SHINANO-MACHI 長野県信濃町のガイドブック
¥3,300
SOLD OUT
長野県信濃町に暮らす人々の価値観を徹底取材したガイドブック。人口7500人。山に囲まれ、野尻湖を擁し、夏は避暑地、冬は雪。「なぜこの町に人が惹かれるのか」「移住者たちはどんな暮らしをしているのか」に迫り、“旅のガイド”でありつつ“人生のガイド”の要素も色濃いです。 信濃町に縁がある人はもちろん、全国の「山あいのちいさな町」に暮らす人の「生きるヒント」「移住のヒント」「まちの情報を発信するヒント」になり得る本だと思います。局地的だからこそ逆に汎用的に自分ごととして読めるかも。 写真がとても良いです。まずは写真だけぱらぱらと見ていくだけで土地の良さがスーッと腑に落ちるような気がしてきます。撮影は隣町・飯山市のおじいちゃんおばあちゃんたちの写真集『鶴と亀』でも知られる小林直博さん。 編集はローカルの編集を得意とする株式会社Huuuu。編集長は自らも信濃町への移住者である徳谷柿次郎さん。発行は信濃町役場。 【内容】 <インタビュー> ・自然と信濃町 / アファンの森財団 大澤渉さん ・ミヒャエル・エンデと信濃町 / クルミドコーヒー 影山知明さん ・サウナと信濃町 / LAMP 野田クラクションべべーさん ・うどんと信濃町 / 温石 須藤剛さん ・クラフトマンと信濃町 / OND WORK SHOP 木村真也さん&サユリ美容室 木村早悠里さん ・コーヒーと信濃町 / 珈琲占野 占野大地さん ・パンと信濃町 / EN BAKERY 39! 谷口美樹さん ・伝統野菜と信濃町 / 農家 関塚賢一郎さん、信濃町役場 川口彰さん <そのほか> ・珈琲占野ご夫婦の移住こぼれ話対談 ・一級建築士 野々山修一の町と関わる建築談義 ・夫の都合で信濃町に連れてこられた妻対談 ・信濃町に帰ってきた母と娘の国際村対談 ・徳谷柿次郎と新卒ふろめぐみが語る”集落”の価値観対談
-

プロジェクト図解 地域の場を設計して、運営する 設計事務所15の実践
¥3,300
自らの拠点を外にも開いている設計者たちの事例15個を、写真、図面、初期投資額、月々の支出と収入まで(!)書いた、貴重な情報満載の一冊。 ーーー 場に投資し自ら価値をつくりだす設計運営術 建築・ランドスケープを仕事にしながら飲食・宿泊施設、銭湯等を運営する設計者たちの15拠点を図解。図面や写真から読み解く、複合用途の計画やまちへ開く居心地の設計手法。収支表・運営関与度グラフで分析する、経営管理や組織運営と持続性。ネットワーク図で可視化する、生活圏での活動と地域内外に拡張する協働体制。 ーーー A5判 192ページ オールカラー 送料:300円
-

ポートランド 世界で一番住みたい街をつくる
¥2,200
レベルブックス店主も2013年に訪問し、5日間徒歩と自転車で回って大のお気に入りになったオレゴン州ポートランド。食も自然もカルチャーもエキサイティングなこの街が、なぜ多くの人を惹きつけるのか?ポートランド市開発局勤務(執筆当時)の日本人著者が書いた本。ポートランドについてはいくつも本が書かれていますが、魅力的な街である理由について知りたいならこの本が最もおすすめです。自分が住む/関わる街に応用するためのヒントにもなるでしょう。当店で開店以来コンスタントに売れ続けているロングセラーです。 ーーーーーーーーーー 出版社による紹介文 ーーーーーーーーーー この10年全米で一番住みたい都市に選ばれ続け、毎週数百人が移住してくるポートランド。コンパクトな街、サステイナブルな交通、クリエイティブな経済開発、人々が街に関わるしくみなど、才能が集まり賢く成長する街のつくり方を、市開発局に勤務する著者が解説。アクティビストたちのメイキング・オブ・ポートランド。 出版社による詳細な紹介ページはこちら http://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761526238/ 【送料300円】
-

歩いて読みとく地域経済 地域の営みから考えるまち歩き入門 | 山納洋
¥2,200
歩いてまちのどこを見るか、見つけた要素をどう読み解くか。地域経済の視点で各地を読み解いた実例。歩くことはすべてにおいて重要だと最近特に思います。 ーーー 歩きながら考える「わたしたちの経済圏」 農山漁村や港、町工場、百貨店や商店街、観光地に埋立地…普段のまちを地域経済の視点で歩くと、その成り立ちをめぐる人々の営みのドラマが見えてくる。企業活動のスケール化で風景が画一化するなか、地域内の経済循環を生み出すコモンズの可能性にも注目。まち歩きの達人が贈る、「わたしたちの経済圏」を考えるためのヒント。 ーーー A5判 ソフトカバー 188ページ 送料:300円
-

数字とファクトから読み解く 地方移住プロモーション | 伊藤将人
¥2,640
33のトピックで移住の最新事情を、ファクトに基づいて解説する本。「フェアで持続可能な移住促進」というテーマが良いですね。章タイトルを見ても「移住ランキングと適度な距離感で付き合う」とか「過度な自治体間競争から脱却しよう」とか共感できる言葉が並んでいます。 ーーー 競争や流行にとらわれず、まちに本当に必要な“移住者”と出会うためには何が重要だろうか?本書では「フェアで持続可能な移住促進」という視点を軸に据え、移住をめぐる研究結果や統計調査など様々なファクトを豊富に紹介。33のトピックに分け、行政・事業者・地域が直面する課題や葛藤を乗り越えるアイディアを提示する ーーー 四六判 ソフトカバー 240ページ 送料:300円