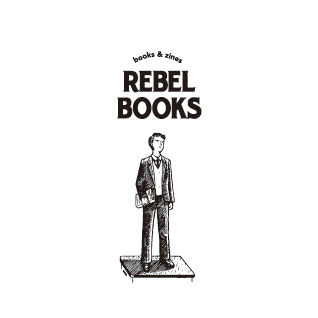-

お金信仰さようなら | ヤマザキOKコンピュータ
¥1,980
「投資」というものの本質に迫り、それまで投資に興味がなかった(僕みたいな)人が目からウロコを落としまくった(投資を始めた人も多くいた)本『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』のヤマザキOKコンピュータさんによる待望の新刊がいよいよ刊行です。 ーーー 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 成長と労働ばかりが求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? 売れないものには価値がないのか? 経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 投資家やバンドマンとして、金融界のみならず国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培ってきた独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 ヤマザキOKコンピュータの最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。 ー ◆目次 この本を書くにあたって 第1章 自分の〈いま〉に名前を付ける お金を信仰する時代/退屈で残酷な、グローバル資本主義社会/お金の大小しか見ない、一次元的な世界観/①市場信仰/②貨幣信仰/お金ではなく、お金信仰に別れを告げる 第2章 未来に不要なものは置いていく 新しい時代の歩き方/ハードコアパンクバンドが示してくれたアンサー/お金持ちになったら幸せになる?/国が豊かになったら貧困問題は解決する?/〈見えざる手〉は人々の理想を実現できる?/私たちの暮らしは本当に豊かになっている?/お金がここまで強く信仰される理由 第3章 新しい価値観に名前を付ける 新たな世代の、新たな価値観/アメリカのFIREムーブメント/中国の寝そべり主義者宣言/パラレルワールドをいまからやる/欧州パンクの共同体における知性あふれる価値観の共有/昔の商店街に見る、活気主義の世界/自分が本当に価値を感じるもの/接続性=人や社会とのつながり×文脈としてのつながり/①社会的接続価値/②文脈的接続価値/お金信仰は終わらせる力、接続性はつなぐ力/お金信仰に別れを告げるときが来た さいごに 私が出した、ひとつの答え ーーー 四六判 ソフトカバー(ビニールカバー) 224ページ 送料:300円 === くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 https://rebelbooks.theshop.jp/items/32944059
-
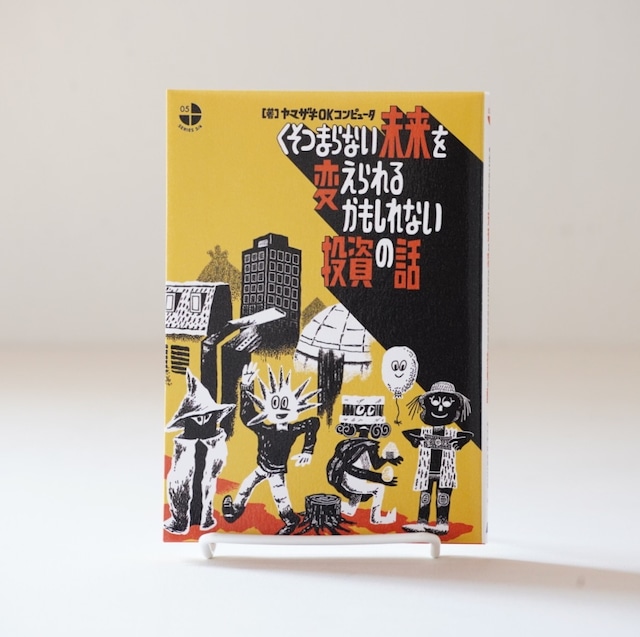
くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 | ヤマザキOKコンピュータ
¥1,540
バンドマン/パンクスである著者が書くのは「くそつまらない未来を変えるには、少しずつでも好きな企業の株を買って保有したら?」という話。幸せってなんだ?お金ってなんだ?未来をどうしたいんだ?ということを根本的に考えて、資本主義のシステムの中でより効果的に戦うためにどうするか。単に金を稼ぐことが目的ではない投資の姿が見えてきます。これほんとすばらしいのでみなさん読んでほしいです。 タバブックスの「シリーズ3/4」は分量的にも読みやすいので誰でもとっつきやすく、おすすめ。 B6版変型(173mm×123mm)・ソフトカバー・148ページ 【送料300円】
-

社会主義都市ニューヨークの誕生 | 矢作弘
¥2,420
2025年のニューヨーク市長選で民主社会主義者でムスリムのゾーラン・マムダニが当選。その背景を解き明かす本。私も今読んでますが非常に面白い。格差の拡大で本当に困った市民たちの切実な声と、その声に耳を傾けるマムダニ。世界のどの都市にも当てはまる市民生活と政治の普遍的な課題と取り組みが見えてくる。これからのニューヨークがどうなるかも興味深いですが、この本を読んでおくとかなり解像度が上がるはず。 ーーー グローバル資本主義の首都ニューヨークの市長に、急進左派の!?民主社会主義者、ゾーラン・マムダニ氏が就任へ!生活苦の労働者・若者の支持を集める背景や氏の人物像、家賃凍結/公共バスや子供保育の無償化/市所有スーパーマーケットの展開/富裕層・大企業増税等の政策を解剖し、他都市やワシントン政治への影響を展望。 ーーー 四六判 ソフトカバー 188ページ 送料:300円
-

ニッポンの移民——増え続ける外国人とどう向き合うか | 是川夕
¥1,012
ーーー 移民で日本はどう変わるのか? 増え続ける外国人に対し不安の声は多い。この国の未来を冷静に議論するために、第一人者がデータに基づいた基礎知識を伝授する。 ー 少子高齢化による労働力不足や、流動的な世界情勢を受け、 近年日本に多くの外国人がやってくるようになった。2070年には、人口の約10%に達するとも言われる。それに対し、 治安や社会保障に関する不安の声は多く、 排外主義も台頭している。 移民は日本にとって救世主なのかリスクなのか? 日本は欧米のように分断されるのか? 移民なしではこの国はもたないのか? 第一人者が、エビデンスを基に、 移民政策の歴史と未来について考察。移民をめぐる議論に一石を投じる。 ーーー 新書 256ページ 送料:300円
-

Community Based Economy Journal 002 - 美しい経済の風景をめぐる旅の記録 -
¥2,970
Community Based Economy Journal 002 - 美しい経済の風景をめぐる旅の記録 - 「美しい経済の風景をめぐる旅の記録」をテーマに、過去に学び、現在に出会い、未来に遺すために世界をめぐるビジネスドキュメンタリー誌の第2号。 ーーー 美しい経済の風景は、「土」の中から生えてくる。 「土」の質感を手がかりに、各地各様の経済の風景をたのしんでみてください。 ー [目次] # 1 美しい経済の風景の、つくり方を訪ねる 寺田本家/寺田 優/ CHIBA 7 Kontrapunkt / Philip Linnemann / COPENHAGEN 23 老松/太田 達/ KYOTO 39 うむさんラボ/比屋根 隆/ OKINAWA 54 The Centre for GOOD Travel / Eliza Raymond、Julia Albrecht / LOWER HUTT 69 Urban Farm Oasis / Novella Carpenter、Kate Hobbs / BERKELEY 84 やまとわ/奥田 悠史/ NAGANO 99 ひより保育園・そらのまちほいくえん/古川 理沙/ KAGOSHIMA 114 # 2 美しい経済の風景の、感じ方と出会う 山極 壽一/総合地球環境学研究所 所長/ KYOTO 130 鞍田 崇/明治大学理工学部 准教授/ TOKYO 145 紫牟田 伸子/編集家/ KAMAKURA 160 中川 周士/中川木工芸 三代目/ SHIGA 175 # 3 美しい経済の風景の、つくり手と歩く シェアビレッジ「森山ビレッジ」/丑田 俊輔/ AKITA 191 関美工堂「Human HUB Tenneiji Soko」/関 昌邦/ AIZUWAKAMATSU 206 紫野和久傳「和久傳ノ森」/桑村 綾/ KYOTO 221 ーーー A5変型 ソフトカバー 240ページ 送料:300円 ★第1号はこちら https://rebelbooks.theshop.jp/items/88959429
-

Community Based Economy Journal 001 - 美しい経済の風景をめぐる旅の記録 -
¥2,200
SOLD OUT
「美しい経済の風景をめぐる旅の記録」をテーマに、過去に学び、現在に出会い、未来に遺すために世界をめぐるビジネスドキュメンタリー誌の創刊号。 ーーー (発行元によるステートメント) 本誌は、“Community”と“美しい”という二つの感覚を糸口に、グローバルに展開する企業からローカルに根ざす商いまで、規模や拠点を問わず、私たちが美しいと感じる経済の営みを訪ね、対話し、その背後にある人々の哲学や態度、創意工夫や仕組みを各地のCommunity Based Companiesが取材・執筆したものです。 ビジネスが内包している「文化が経済を育て、経済が文化を育む」という側面にスポットを当て、親密さや美意識といった数値に置き換えにくい価値を大切にできるビジネスの可能性の発見を可視化し、希望の持てる経済活動の選択肢が世の中に増えることを願い、創刊しました。 ーーー 【目次】 #1 美しい経済の風景の、つくり方を訪ねる ワコール「京の温所」/ 楠木 章弘 / KYOTO 8 散歩社「BONUS TRACK」/ 内沼 晋太郎、小野 裕之 / TOKYO 20 シーベジタブル /友廣 裕一、蜂谷 潤/ TOKYO 33 リズム学園「はやきたこども園」/ 井内 聖 / HOKKAIDO 45 The Cheese Board Collective / Steve Manning、津曲 陽子 / BERKELEY 55 産直市場グリーンファーム / 小林 啓治/ NAGANO 65 Larry vs Harry / Hans Bullitt Fogh / COPENHAGEN 75 obama village / 有村 健弘、有村 康弘 / KAGOSHIMA 87 Think the Earth / 上田 壮一 / TOKYO 94 香老舗 松栄堂 / 畑 正高 / KYOTO 106 #2 美しい経済の風景の、感じ方と出会う 堂目 卓生 / 大阪大学大学院経済学研究科教授 / OSAKA 120 小野寺 愛 / そっか 共同代表 / ZUSHI 131 Anker Bak / 家具デザイナー / COPENHAGEN 140 藤田 一照 / 曹洞宗僧侶 / HAYAMA 150 #3 美しい経済の風景の、つくり手と歩く ◯と編集社「トビチ商店街」/ 赤羽 孝太 / NAGANO 172 リバーバンク「GOOD NEIGHBORS JAMBOREE」/ 坂口 修一郎 / KAGOSHIMA 161 パースペクティブ「工藝の森」/ 高室 幸子、堤 卓也 / KYOTO 180 ーーー A5変型 ソフトカバー 192ページ 送料:300円
-

ラーゴムが描く社会 スウェーデンの「ちょうどよい」国づくり | 鈴木賢志
¥2,420
ーーー (出版社による紹介) 自分も他者も尊重しつつ、何ごとにつけ「ほどほど」をよしとする哲学の奥深さ。幸福度ランキング上位国に学ぶ国家像 ー スウェーデンには、人々に愛されてきた「ラーゴム」という考え方がある。自分を大切にしつつ、周りのことも考えて多くを求めすぎない、「ちょうどよい状態」を美徳とする一種の行動規範で、この国の人々のライフスタイルの基本となっている。この「ラーゴム」の精神が、個人だけでなく、スウェーデンという国の政治や経済、社会システムにも力強く息づいているのではないか——そう考え、本書を著すことにした。 スウェーデンは国際的に見ても非常にユニークな国である。「高福祉高負担」という観点からはアメリカの対極に位置するが、経済的な豊かさではアメリカを上回っており、ご存じのように国民の「幸福度」は非常に高い。 日本を含む多くの社会では、「高福祉高負担は勤労意欲を阻害し、働くだけ損だと考えて怠ける人が増える」という通念が根強い。しかしそうした通念をひっくりかえすようなことがこの国では日々起きている。その謎を解くカギが「ラーゴム」にあると断言したい。 本書では、現在のスウェーデンを形づくっている社会システムや政治・経済・ビジネスの仕組み、先進的な環境政策などを「ラーゴム」の視点から読み解くことで、この国を総体的に理解することを目指した。スウェーデンや北欧に関心のある人が、各専門領域に踏み込む前に、まずはこの国の全体像をつかむためのテキストとしても活用できるものになっている。 いま世界的に、社会の中に分断や対立をあえてつくり出し、それを煽ることで支持を拡げるという手法がアメリカを中心に蔓延している。スウェーデンが歩み続ける「ラーゴム」の道は、その有力なアンチテーゼとなるはずだ。むろん、そこには悩みも揺らぎもあるわけだが、それも含めて、日本社会の今後のあり方を考えるヒントともなるだろう。 ーーー 四六判 ソフトカバー 224ページ 送料:300円
-

チョンキンマンションのボスは知っている | 小川 さやか
¥2,200
香港の重慶大厦(チョンキンマンション)を拠点とするタンザニア人ビジネスマンの周囲には、独自の互助組合、信用システム、SNSによるシェア経済など、既存の制度に期待しない人々による、合理的で可能性に満ちた生き方があった。当店でもロングセラーとなっている人類学の名作です。 四六判 ハードカバー 276ページ 送料:300円
-

平等についての小さな歴史 | トマ・ピケティ
¥2,750
トマ・ピケティが各1000ページに及ぶ三冊の主著を自ら要約した親切な一冊。 ーーー (出版社による紹介) 3000ページの達成を250ページに凝縮。 「格差に対処する野心的な計画を提示している。…政治の未来についての議論の出発点だ」 マイケル・J・サンデル(ハーバード大学教授|『実力も運のうち』) 「ピケティにとって、歴史の弧は長く、しかも平等に向かっている。…平等を成し遂げるには、つねに無数の制度を[再]創造しなくてはならない。本書はそれを助けるためにやってきた」 エステル・デュフロ(2019年ノーベル経済学賞受賞者) 「不平等から平等へと焦点を移したピケティが示唆しているのは、必要なのは鋭い批判だけではなく、回復のための治療法だということだ」 ジェニファー・サライ(『ニューヨーク・タイムズ』) ー 公正な未来のために、経済学からの小さな贈り物。 「〈あなたの著書はとても興味深いです。でも、その研究について友人や家族と共有できるように、もう少し短くまとめて書いてもらえるとありがたいですが、どうでしょう?〉 このささやかな本はある意味、読者の皆さんにお会いするたびに決まって言われたそんな要望に応えたものだ。私はこの20年間に不平等の歴史について3冊の著作を世に出したが、いずれもおよそ1000ページにも及ぶものになった。『格差と再分配』『21世紀の資本』『資本とイデオロギー』の3冊だ。…こうして積み重ねられた膨大な量の考証を前にすれば、どんなに好奇心旺盛な人でも意気消沈してしまうことだろう。そこで私はこれまでの研究を要約することにした。本書はその成果である。 しかし本書は、こうした研究から得られる主な教訓を総論的に紹介しているだけではない。…自分の数々の研究を通して深めた確信に基づいて平等の歴史についての新たな展望を示している」 (謝辞より) ーーー 四六判 ハードカバー 264ページ 送料:300円
-

WORLD WITHOUT WORK AI時代の新「大きな政府」論 | ダニエル・サスキンド
¥4,620
ーーー (出版社による紹介) 「本書は、現代における最大の経済的試練の一つをテーマとしている。迫り来る驚くべき技術革新によって、働いて稼ぎを得るということを全員が全員行なえるわけではない世界が来たら、その先はどうするのか。…この先に待ち構える根幹的な難問、それは分配の問題だ。技術進歩は人類全体をかつてないほどにゆたかにしているかもしれないが、富を分配する従来の方法――労働に対して賃金を払う――が過去のような効果を示さなくなるのだとすれば、そのゆたかさをどうやって分かち合っていけばいいのだろう」 「技術進歩は僕たちを、人間がする仕事が足りない世界へと連れていく。僕たちの祖先を悩ませていた経済問題は消滅し、かわりに3つの新たな問題と入れ替わっていく。1つめは不平等の問題。2つめは政治的支配力の問題。そして3つめは人生の意味の問題だ。…21世紀の僕たちは、新しい時代を築いていかなければならない。安定をもたらす基盤として、もはや有償の仕事には頼らない時代だ」(本書より) イギリスの新進気鋭の経済学者が、21世紀の〈所得分配国家〉〈資本分配国家〉〈労働者支援国家〉を描き出す。 ーーー 四六判 ハードカバー 400ページ 送料:300円
-

人を動かすルールをつくる 行動法学の冒険 | ベンヤミン・ファン・ロイ アダム・ファイン
¥3,960
ーーー (出版社による紹介) 「行動科学が法律を理解する際になくてはならないことを気づかせてくれる、見事な書だ」 ロバート・チャルディーニ(アリゾナ州立大学名誉教授|『影響力の武器』) 「才気あふれ、根源的で、しかも書きぶりは美しく、人の心をつかんで離さないこの本は、ずっと前から必要だった運動のきっかけになるだろう…現状のシステムはあまりに不公正だ。本書はシステムをもっと公正にする明確な道筋を示している」 ローレンス・レッシグ(ハーヴァード大学ロースクール教授|『CODE』) 死刑の効果から、税務コンプライアンスまでを科学する。 「なぜ法律は、人間の行動を改善できないのだろうか。… 紙のうえの法律がどのように行動を形作るのか理解するためには、視点を変えなければならない。…細かいルールをいちいち目で確認するのではなく、人々がルールにどのような反応を示すかという点に注目しなければならない。そうすると、まったく異なるコードが見えてくる。それは行動のメカニズムに関するコード、すなわち行動コードだ。… 私たちの法律を改善して効率を高めるためには、この行動コードを理解しなければならない。ここでは社会科学が大いに役立つ。この分野での数十年にわたる研究の結果、法的ルールに対する人間の反応を形作る行動メカニズムが、いまでは明らかになった。目に見えない行動コードも、科学のおかげで見えるようになった。… 人間の行動を理解してこそ、法律は機能を十分に発揮して私たちの安全が守られるのだ」(本文) 従来の法学を超えた視点から、新たな規範と道徳の可能性を示した、行動法学へのいざない。 ーーー 四六判 ハードカバー 352ページ 送料:300円
-

カーボンZERO 気候変動経営 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング
¥3,080
ーーー (出版社による紹介) 2015 年のパリ協定採択以降、気候変動をめぐる潮流が世界で加速しています。 気候変動というアジェンダは、今後の企業経営にとって極めて重要な意味をもつようになっています。 一歩梶取りを誤れば、事業の競争力が削がれ、企業の存続が危ぶまれるリスクとなっているのです。 一方で、適切に自社を適合させることができれば、企業価値の向上と持続可能性の実現に寄与する機会にもなり得ます。 気候変動にかかる情報は日々あらわれていますが、企業経営の目線から気候変動問題を論じている書籍は未だあまり見られません。 科学的根拠にもとづき人類社会に警鐘を鳴らすものや、将来について技術的な観点を中心に論じるものがほとんどです。 本書の執筆に関わった私たちは、特に日本企業および産業が、気候変動をめぐる社会の動向を読み違え、対応を誤ることにより、国際的な競争力を阻害される事態を危惧しています。 本書は、経営層を中心に企業で働くビジネスパーソンが、自身の文脈に照らして気候変動問題を捉え、自社において取るべき対策を検討する契機となることを狙いとしています。 ー 【目次】 第1章 気候変動をめぐる国際潮流 第2章 気候変動と金融機関・投資家 第3章 気候変動と経済安全保障 第4章 気候変動経営 第5章 気候変動対応の事業変革 第6章 TCFDシナリオ分析 第7章 脱炭素技術をサプライチェーンに取り入れる 第8章 気候変動とサーキュラーエコノミー 第9章 気候変動と行動科学 第10章 日本を救う「50年経営」 第11章 未来を共創する 2021年刊行 ーーー A5判 ソフトカバー 288ページ 送料:300円
-

ジャーニーシフト デジタル社会を生き抜く前提条件 | 藤井保文
¥2,420
ーーー (出版社による紹介) 「ジャーニーシフト」とは、顧客提供価値が時代によって変質したことを示した言葉です。一文で示すと以下のようになります。 顧客提供価値は、「モノや情報の提供」「瞬間的な道具としての価値」から、ありたい成功状態を実現させ、行動を可能にさせる「行動支援」に変わっている。 これは言い換えると、「ユーザにとって何かしらの行動やアクションを可能にしていなければ、企業として何の価値もない時代」になってきているということでもあります。自分の中でどれだけ受け止め、理解したり解釈したりしても、世の中に対して発信や貢献をし、社会やコミュニティーに干渉しないと、意味がない時代になってきているのです。 本書は、世界の潮流から新たな変化を読み解く本です。社会のビフォアアフターを書いたこれまでのシリーズに対し、提供価値のビフォアアフターを書いたものがこの『ジャーニーシフト デジタル社会を生き抜く前提条件』です。 DXやOMOから、SDGsやパーパス、Web3やメタバースなど、次々と現れるバズワードは、1つの大きな潮流【提供価値の行動支援化】を示しており、その中には2つの特性【利便性の進化・意味性の進化】があります。本書を通してこれらを整理し理解することが、変化の速い時代の道しるべになるのではないか、と考えています。読んでくださった方の仕事や生き方において、さまざまなバズワードに埋もれて身動きが取れなくならないよう思考しアクションしていくための、コンパスや道具になることを願っています。 ー 中国の「社会実験」からインドネシアの「世渡り上手」へ。「UX」をめぐる藤井さんの旅は、デジタル/新自由主義世界に「社会」を取り戻すためのジャーニーなのだと思う。 ―若林恵氏(黒鳥社 コンテンツディレクター) ー <目次> はじめに 体験中心の時代、生き抜くための視点を 第1章 新興国からデジタルの未来を学ぶ時代 第2章 新たな社会リーダーシップとジョイントビジョン 第3章 Web3がもたらす意味性の進化 第4章 行動支援の時代:行動実現してくれないものに、もはや価値はない 第5章 ジャーニーシフトに必要な視点と思考法 巻末特別対談 深津貴之氏との対談 「画像生成AIから見る、意味生成の在り方、企業の戦い方」 2022年12月刊行 ーーー A5 ソフトカバー 200ページ 送料:300円
-

第七の男 | ジョン・バージャー(著)ジャン・モア(写真)
¥3,080
小説家、批評家、ジャーナリスト、詩人として活躍したジョン・バージャーが、欧州の移民の実情を描き出し、新自由主義的資本主義の問題点に迫る。素晴らしい写真と編集の妙で、良質なドキュメンタリー映画の味わいもある一冊。原著刊行は1975年ながら、英国では2010年に新版が刊行され、今なお読み継がれているという名著。REBELな本です。 A5変型判 ソフトカバー 256ページ 送料:300円
-

コモンの「自治」論 | 編/斎藤幸平・松本卓也
¥1,870
『人新世の「資本論」』の斎藤幸平さんをはじめ注目の書き手が集結した本で、興味深いトピックばかり。個人的には人類学者松村圭一郎さんが書く「第2章:資本主義で「自治」は可能か?──店がともに生きる拠点になる」が非常に気になります。 ーーー 【『人新世の「資本論」』、次なる実践へ! 斎藤幸平、渾身のプロジェクト】 戦争、インフレ、気候変動。資本主義がもたらした環境危機や経済格差で「人新世」の複合危機が始まった。国々も人々も、生存をかけて過剰に競争をし、そのせいでさらに分断が拡がっている。崖っぷちの資本主義と民主主義。この危機を乗り越えるには、破壊された「コモン」(共有財・公共財)を再生し、その管理に市民が参画していくなかで、「自治」の力を育てていくしかない。 『人新世の「資本論」』の斎藤幸平をはじめ、時代を背負う気鋭の論客や実務家が集結。危機のさなかに、未来を拓く実践の書。 【目次】 ●はじめに:今、なぜ〈コモン〉の「自治」なのか? 斎藤幸平 第1章:大学における「自治」の危機 白井 聡 第2章:資本主義で「自治」は可能か? ──店がともに生きる拠点になる 松村圭一郎 第3章:〈コモン〉と〈ケア〉のミュニシパリズムへ 岸本聡子 第4章:武器としての市民科学を 木村あや 第5章:精神医療とその周辺から「自治」を考える 松本卓也 第6章:食と農から始まる「自治」 ──権藤成卿自治論の批判の先に 藤原辰史 第7章:「自治」の力を耕す、〈コモン〉の現場 斎藤幸平 ●おわりに:どろくさく、面倒で、ややこしい「自治」のために 松本卓也 ーーー 四六判 ソフトカバー 288ページ 送料:300円