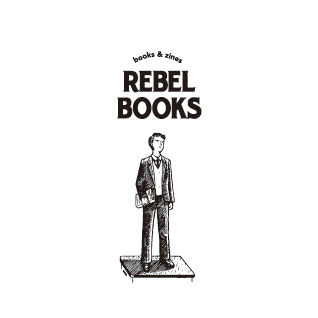-

薔薇の名前[完全版]上下セット | ウンベルト・エーコ著、河島英昭/河島思朗 訳
¥6,820
中世イタリアの修道院で起きた連続殺人事件。事件の秘密は知の宝庫ともいうべき迷宮の図書館にあるらしい。記号論学者エーコがその博学で肉づけした長編歴史ミステリ。全世界で異例の大ベストセラーとなった名作。その「完全版」。 初版刊行以来、エーコ自身が加えてきた数々の訂正、削除等をすべて反映したものになっており、上巻巻頭には、そうした修正について、2012年版に作者自身が寄せた付記も収めた。 下巻の巻末には、エーコ自身による覚書(本編刊行後 1983年に発表されたもの)、執筆のために書き溜めたメモや、登場人物や建造物のデッサン等も併録した。 全体を通して、故河島英昭氏に代わって(覚書については英昭氏の準備訳稿が存在した)、河島思朗氏が訳文全体を見直し(特にラテン語関連は精査)、作者による訂正、 削除についても細部にわたって確認した。 上巻:3300円 下巻:3520円 送料:600円(レターパックプラス)
-

奇奇怪怪 | TaiTan,玉置周啓
¥2,750
唯一無二のポッドキャスト番組書籍化第二弾!小口に塗りが施された造本から既に楽しいです。音声と書籍、合わせてぜひ。 ーーーーー ラッパーのTaiTan(Dos Monos)、音楽家の玉置周啓(MONO NO AWARE / MIZ)の二人が、映画・音楽・小説・漫画などのコンテンツから、生活の中で遭遇する違和感とワンダーの裏に潜む経済の謎まで縦横無尽に語り尽くす、Spotify Podcastチャートで最高順位第1位を記録した、超人気ポッドキャスト番組『奇奇怪怪』。 2022年にポッドキャスト番組としては異例の500ページ越え・本文三段組み・函入りという造本で書籍化され大反響を呼び(国書刊行会より刊行)、版元史上最高予約数(当時)を記録。同年秋にはアニメ化やTBSラジオでレギュラー番組『脳盗』が開始されるなど、領域を超えて広がりを見せる同番組が満を持して刊行する書籍版第二弾! 第一弾の百科事典的装いから漫画雑誌的オブジェクトへと変貌を遂げ、書き下ろし序文、語り下ろし跋文、そして巻末解説にギャグ漫画家・藤岡拓太郎氏の短編漫画を併録! 文化と経済の森羅万象を「強引に面白がる」ための言葉と思考の実弾が詰まった異形の対話篇。 ーーーーー B5 392ページ 送料:300円
-

占星術の文化誌 | 鏡リュウジ
¥3,080
ーーー 占星術に対して客観的な立場を保ちつつ、占星術が文学・美術・音楽など文化にどのような影響を与えてきたのかを書いた本。「占星術を知らないとシェイクスピアもルネサンス絵画もわからない」という言葉、本書を読むと納得します(読みました)。 予備知識なく「占星術ってどういうものなんだろう?」という疑問を持つ人におすすめ。 ーーー 四六判 ハードカバー 334ページ 送料:300円
-

世界のほうがおもしろすぎた――ゴースト・イン・ザ・ブックス | 松岡正剛
¥2,090
2024年に逝去された編集者にして博覧強記の読書家・松岡正剛さんの、ロングインタビューによる自伝です。 ーーー (出版元による紹介) 「ぼくが目指したことは、すべて編集です」 異能の編集工学者が謎に包まれたその生涯と秘策を一気に語り明かす。 ロングインタビューによる、最初で最後の「自伝」。 「若者の教祖」「知の巨人」「博覧強記」――。 あらゆるレッテルを嫌い、「生涯一編集者」であることに徹した松岡正剛。その歩みは理科少年の時代[ころ]に抱いた自己同一性への疑問に始まっていた。十数時間におよぶ、生前最後にして初の自伝インタビューを完全再録。また付録として、未発表稿及び年譜を掲載。 ーーー 四六判 ソフトカバー 404ページ 送料:300円
-

政治的に無価値なキミたちへ | 大田比路
¥1,650
政治のことがわからない人でもこれを読むうちに政治的論点を持ち、自らの政治的立場を把握できるようになるという本。早稲田大学の政治入門講義を書籍化したもの。 序盤で問いに答えていくと自分が「リベラル」「リバタリアニズム」「共同体主義」「保守主義」のどれに近いのかがわかる。 個別の論点で言うと例えば話題の東大授業料値上げ、「まあお金はかかるし昔とは違うしな」と思った方もいるかもしれない。この本では教育の項で「国公立大学の初年度納付額」や「教育予算額の対GDP比率」のデータを用い、日本が先進国の中でも最悪の部類に入る「教育弱小国」であることを示す。 すべての項目で具体的なデータ(のグラフ)を用いて解説しておりよく理解できる。 政治は生活と直結し、自分の人生に直接的な影響を及ぼす。 次の選挙までにたくさんの人に読んでほしい一冊。 おすすめです。 四六判 ソフトカバー 320ページ 送料:300円
-

群れから逸れて生きるための自学自習法 | 向坂くじら 柳原浩紀
¥1,980
ーーー (出版社による紹介) 注目の詩人と教育者による、アウトサイダーのための勉強論 「勉強するのに仲間はいらない。むしろ、ひとりでいるために勉強が必要なのだ」。群れず、つるまず、あなた自身でいるための学び方とは。その試みは、他者を理解し、世界をゆがみなく捉える第一歩となる。一斉授業に困難を抱える中高生から、学び直しを求める大人まで。 【目次】 はじめに なぜ勉強の方法を知る必要があるのか? 【理論編】 01 学ぶとは何か?──目的と手段、そして対話 02 読む──すべての勉強はここからはじまる 03 理解する──少しはみ出すくらいがいい 04 覚える──ぶらぶら散歩するのがいい 05 言語化する──つまり、軽々と間違えること 06 考える──制約と跳躍 【実践編】 07 英語 ◇コラム 勉強する理由は「楽しいから」か? 08 数学 ◇コラム テストとは何か? なぜ試験勉強は勉強ではないのか? 09 国語 ◇コラム 勉強仲間は必要か? 10 社会 ◇コラム くじけるとは何か? 正しいくじけ方について 11 理科 ◇コラム なぜ学習法が大切なのか? 努力に逃げないことを頑張る おわりに 参考文献/教材リスト ーーー 四六判 ソフトカバー 192ページ 送料:300円
-

はじまりのデザイン学 | 中村将大
¥2,750
帯にあるキャッチコピー「リベラルアーツとしてのデザイン入門」がいいですね。リベラルアーツカレッジを出て、デザインの専門学校に行って、本屋をやっている身として言うと、本質的な意味でのデザインの勉強はあらゆることに役立ちます。また、あらゆる種類のデザインを行う上でデザインとは何かという本質的な問いに対して何らかの答えを持っていないと良いデザインはできないと思います。あと単純に興味深く面白いです、デザインを学ぶこと。 ーーー (出版社による紹介) 今いろいろなかたちをしている「デザイン」のそもそも、皆さんはご存知でしょうか? 本書はデザインをリベラルアーツ(さまざまな視点をもつための基礎教養)として学んでゆく内容です。細分化した各分野へつながる助走として、デザインに関心のあるすべての人に読んでほしい一冊です。各論に通底する普遍的なデザインの基礎を共有し、自信をもって自身の専門性を極めていけるように。まだ未分化のデザイン。その正体を咀嚼していきましょう。 本書は4つの部をまたぐ全15講のかたちで構成されています。 第1部 デザインのそもそも|デザインを定義する 「デザインって、そもそもなんだろう?」 デザインという行為について、身近な話からはじめ、そこから事例を参照しつつ、ひとまずの「デザインの定義」を試みます。 第2部 デザインのしつらえ|情報の構造 デザインと情報は不可分です。ここでは視覚情報とわたしたちの関係を考察しながら、これがどのような構造で成り立っているかについて紹介してゆきます。キーワードはヴィジュアルコミュニケーション、メディア、情報設計、タイポグラフィ、そしてグリッドシステムです。 第3部 デザインのこれまで|歴史と価値形成 デザインの良し悪しとは、いったいなんでしょう。わたしたちが漠然と共有しているデザインの価値は、長い時間のなか形成された結果です。ここでは歴史背景を紐解き、視点を大小しながら、いま「あたりまえ」にあるデザイン、その理由について考えてゆきます。 第4部 デザインのいとなみ|ワークプロセスと実践 これらをふまえて、デザインの実践を想定しながら、デザインワークの過程や段階、マインドセットを紹介してゆきます。アイデアやリサーチ、プロトタイピングとの向き合い方のヒントも示します。 ーーー A5判 ソフトカバー 240ページ 送料 300円
-

贈与論 | マルセル・モース
¥1,430
「贈与と交換こそが根源的人類社会を創出した」。人類学、宗教学、経済学ほか諸学に多大の影響を与えた不朽の名著、待望の新訳決定版。 ーーー ポトラッチやクラなど伝統社会にみられる慣習、また古代ローマ、古代ヒンドゥー、ゲルマンの法や宗教にかつて存在した慣行を精緻に考察し、贈与が単なる経済原則を超えた別種の原理を内在させていることを示した、贈与交換の先駆的研究。贈与交換のシステムが、法、道徳、宗教、経済、身体的・生理学的現象、象徴表現の諸領域に還元不可能な「全体的社会的事象」であるという画期的な概念は、レヴィ=ストロース、バタイユ等のちの多くの思想家に計り知れない影響とインスピレーションを与えた。 文庫版 320ページ 送料:300円
-

信じない人のための〈宗教〉講義 | 中村圭志
¥3,520
信じない人こそ宗教を学ぶべきだと思ってます。 ーーー (出版社による紹介文) 〈宗教〉なんて過去の遺物? あやしいもの? 怖いもの? そんなあなたのために、ざっくばらんな世界〈宗教〉ツアーをご用意しました。ご安心ください。何か特定の〈宗教〉へお誘いするようなことはありません。私もまたいわゆる〈無宗教〉の一人ですから。 「〈宗教〉という言葉はやや漠然とした言葉です。この茫漠と広がる意味領域を大雑把にひっくるめて述べるとすると、〈宗教〉とはなんらかの制度として存在している、とでも言っておくしかなさそうです。そうした制度の別の側面は、人びとの意識のなかに現れるさまざまな世界イメージです。 人びとは日々の暮らしのなかで世界イメージを自己のものとする努力を行なっています。この努力の世界に読者をいざなおうというのが本書の目的です」(はじめに) 宗教家や宗教学者にはちょっと書けない、この脱〈信仰〉型の宗教案内で、私たち自身の偏見や怖れをも、このさい解きほぐしてみましょう。 ーーー 四六判 ハードカバー 256ページ 送料:300円
-

自閉症が文化をつくる | 竹中均
¥2,530
ーーー 伊藤若冲やアルチンボルド、アンディ・ウォーホルやエリック・サティ、ルイス・キャロルやコナン・ドイルらが生み出した文化には、時と場所を越えて不思議な共通点がある。ぴったりとはまらない人々がつくる、ぴったりとはまる文化とはどのようなものか。文化史の地層から「自閉文化」の鉱脈を掘り起こし、リアリズムと合理性に依存する「健常」で「定型」な近代を問い直す。 ー 【目次】 はじめに 第1部 自閉症がつくる文化 第1章 若冲からチューリングへ 第2章 常数としてのマニエリスムと自閉症 第3章 自閉症とは何か 第4章 「自閉文化」の特徴 第2部 世界はそもそもパズルである 第5章 迷宮と蒐集──ルドルフ二世とアルチンボルド 第6章 「不思議の国」は「驚異の部屋」──ルイス・キャロルとアリス 第7章 名探偵・妖精・心霊──コナン・ドイルとホームズ 第8章 点と線──エリック・サティの奇想の音楽 第9章 缶詰が並んでいる──アンディ・ウォーホルの凍りついた宇宙 第10章 パズルと対位法──グレン・グールドの録音スタジオ 第11章 マシンと夢──村上春樹のジグソー・パズル 第12章 コンビニ空間──村田沙耶香と「世界の部品」 第13章 「おひとりさま」の可能性──上野千鶴子の「離脱の戦略」 第14章 ゲームと機械──榎宮祐のライトノベル異世界 第3部 ずれた世界でよりよく生きる 第15章 『アリス』のパラドクス──自己言及を字義通り生きる 第16章 笑いのワンダーランド──二つの世界 第17章 自閉症から認知症へ──プロセスと崩れ おわりに ーーー 四六判 ソフトカバー 270ページ 送料:300円
-

『恋愛の授業』丘沢 静也
¥2,200
ーーー 「恋愛作法の達人になるのは、ふふ、無理だろうけど、「恋する私」や「失恋した私」をながめる眼鏡くらいは、手に入るかも」(「シラバス(2019前期)」より) 「恋愛学」と学生の間で呼ばれた都立大学の人気授業を書籍化! 恋愛に正解はない――だからそれは自分や他人について考える絶好の機会になる。 オペラ、文学、哲学、映画、ドラマなど多彩な素材から繰り出される問いの数々と、出席者の等身大の声でつくりあげられた異色にして極上の授業の報告。 金曜4限の「ドイツ語圏ドイツ文化論」、学生たちがつけたまたの名を「恋愛学」。2010年頃に始まったこの授業は、「彼(彼女)にも受講してほしい」と口コミで広がり、ついには参加者200名超にも及ぶ人気講義になりました。 《カルメン》や《ドン・ジョヴァンニ》などのオペラ、太宰治の恋文、ヴィトゲンシュタインの哲学、『存在の耐えられない軽さ』にドラマ『あまちゃん』まで、多彩な素材をもとに恋愛について考えます。 授業を彩るもうひとつの重要な要素が授業のリアクションペーパー、通称「紙メール」。「草食化」、「恋愛離れ」というレッテルを貼られがちな20代の等身大の声を導きの糸に、授業は縦横無尽に展開していきます。 恋は、がんばったからといって上手くいくものではありません。相手の気持ちはもちろん、自分の気持ちもコントロールできない。「私は、私という家の主人ですらない」(フロイト)のが人間です。コントロールできない局面でどうふるまうか――。恋愛に正解はありません。だからこそ恋について考えることは、「私」やコミュニケーションについて考えを深める、またとない機会でもあります。 「パルラ・バッソ(低い声で語れ)」、「捨恋」、「オイラー図」、「136問題(「伝えたいことが10あったとする。文字情報で伝わるのは1。声の調子や表情や身ぶりなどで伝わるのは3。残りの6は伝わらない」)」……ユニークで一度聞いたら忘れられない合言葉の数々。思わず自分の恋も語りだしたくなる? 感情揺さぶる〈実況中継〉講義。 ーーー 四六判 ソフトカバー 328ページ 送料:300円
-

旋回する人類学 | 松村圭一郎
¥1,650
ーーー 文化人類学ってどんな学問? 黎明期の先駆者たちから、ラトゥール、インゴルド、グレーバーまで。繰り返されてきたパラダイム・シフト(=転回)と研究者たちの「格闘」の跡をたどり、現在地を探る。 6つのテーマ(人間の差異、他者理解、経済行動、秩序、自然と宗教、病と医療)を取り上げ、ぐるぐるめぐり歩きながら考える、文化人類学の新しい入門書。 【「はじめに」より】 「文化人類学ってどんな学問ですか?」そう聞かれると、いつも言葉に詰まる。「昔は未開社会といわれた民族を研究していたんですが、いまは病院とか、企業とか、軍隊とか、現代的な場所も対象になっています」。そんな言い方をして顔色をうかがう。納得いかない様子なら、「ただフィールドワークという現場に深く入り込んで調査する手法は一貫しています」などと言葉をたす。 うまくストレートに説明できないのは、文化人類学が何度も大きなパラダイム・シフト(=転回)を経験してきたからだ。研究対象が変わるだけでなく、学問の前提となる理論的枠組みがたびたび入れ替わってきた。その変化は、かならずしも連続的な「発展」ではない。むしろ「断絶」や「亀裂」でもあった。そこには、人類学者たちが先人の築いた基盤やその時代の支配的概念を批判的に乗り越えようと格闘してきた足跡が刻まれている。 (中略) 私たちはいったいどんな世界をつくりだそうとし、現実にどう世界を変えてきてしまったのか。それは、人類学という一学問に限らず、いまの時代を生きるすべての人にとって切実な問いである。人類学の一筋縄ではいかない旋回の軌跡をたどりなおす過程は、その問いへの向き合い方がいくつもありうることを確認していく作業でもある。 ーーー 【目次】 1章 人間の差異との格闘 1 「差異」を問う 2 構造のとらえ方 3 未開と近代 2章 他者理解はいかに可能か 1 他者理解の方法 2 揺らぐフィールドワーク 3 存在論へ 3章 人間の本性とは? 1 社会から個人へ 2 形式主義と実体主義 3 近代への問い 4章 秩序のつくり方 1 法と政治の起源 2 国家と政治 3 国家なき社会 5章 自然と神々の力 1 宗教とアニミズム 2 神の概念 3 自然と人間 6章 病むこと、癒やすこと 1 災いの原因 2 医療人類学の地平 3 ケアの視点 7章 現在地を見定める 1 二分法を問い直す 2 変革と実践の学問へ ーーー 四六判 ソフトカバー 256ページ 送料:300円
-

犬に話しかけてはいけない 内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌
¥2,640
ーーー 内陸アラスカではかつて「犬に話しかけてはいけない」という禁忌があった――。 本書は、マルチスピーシーズ民族誌と環境人文学の視点から、フィールドワークを通してアラスカ先住民の人々と「自然環境」との関わりを描く。内陸アラスカ先住民の人々は、動植物や精霊、土地との関係性のなかで息をひそめながら暮らしてきた。「人間」が問い直されている今、彼らの「交感しすぎない」という知恵から「自然との共生」を再考する。 ーーー 四六判 ソフトカバー 240ページ 送料:300円 「はじめに」をnoteで試し読みできます https://note.com/keioup/n/nbc6f7dfd6307?magazine_key=ma630bcfda397
-

「専門家」とは誰か | 村上陽一郎 編/著
¥1,980
わたしたちは何を信じればいいのか?不信をぬぐい、対立を越えて――激しく揺れ動く社会で求められる知のありかたに9つの観点から迫っていく 危機が訪れればたちまち、さまざまな「専門家」が現れ、種々の「専門知」が入り乱れる。多くの人たちは翻弄され右往左往させられることが世の常となっている。それは新型コロナウイルス禍でいっそう明らかとなった。これまでも起きてきた、これからも起きるだろう。わたしたちは誰を信じればいいのか?何を指針とすればいいのか?科学、テクノロジー、歴史、メディア……多彩な分野から執筆陣を招き、専門知のあり方を問いなおす論考集。求められる知の実体を探り、どのように社会に生かすことができるかを考える。 【目次より】 ◆専門家とは何か――村上陽一郎 ◆隣の領域に口出しするということ: 専門家のためのリベラルアーツ――藤垣裕子 ◆科学と「専門家」をめぐる諸概念の歴史――隠岐さや香 ◆「ネガティブ・リテラシー」の時代へ――佐藤卓己 ◆ジャーナリストと専門家は協働できるか――瀬川至朗 ◆リスク時代における行政と専門家: 英国BSE問題から――神里達博 ◆女子教育と男子教育からみる「教養」と「専門」――佐伯順子 ◆社会と科学をつなぐ新しい「専門家」――小林傳司 ◆運動としての専門知: 対話型専門知と2061年の子どもたちのために――鈴木哲也 ーーー 四六判 ソフトカバー 264ページ 送料:300円
-

聖書を読むたのしみ(ICU選書)
¥1,760
西洋文化の根底には聖書があるが、多くの日本人は聖書についての知識をあまり持ち合わせていない。それに、聖書は魅力豊かな書物でもある。ICU(国際基督教大学)において生涯学習の聴講生向けに行われた、同名の連続講義をもとにした本。1999年刊行なので店主がICU在学中に刊行されたことになりますが、この本のことを知ったのは最近です。 旧約編をお書きになっている並木先生の授業を履修したことがありますが、「なるほどこれが『教養』というものかと、非常に面白いと感じたのを覚えています。旧約編「聖書は教義の書物ではない」とか、新約編「イエスの言行録たる四つの福音書(マルコ・マタイ・ルカ・ヨハネ)のうち最初の三つは『共観福音書』と呼ばれおおよそ共通の題材を扱っている。マルコの福音書が最初に書かれているが、クリスマスの話が始まるのはマタイとルカからである」とか、興味深い話がどんどん飛び出します。 ーーー A5判 ソフトカバー 239ページ 送料:300円
-

自由に生きるための知性とはなにか ――リベラルアーツで未来をひらく
¥2,420
自分のモヤモヤを問いに変え、他者とともに考えはじめたとき、自由な未来への扉がひらく。第一線で活躍する専門家が集結、学問領域を越えて、自由に生きるための知性を語り尽くす。 ーーー 目次 はじめに(立命館大学教養教育センター) 【第1部】シンポジウム(立命館創始150年・学園創立120周年記念シンポジウムより) 01 基調講演 わたしを発見する知――リベラルアーツと当事者研究(熊谷晋一郎) 02 スピーチ リベラルアーツの現在・過去・未来 02-1 東工大リベラルアーツの挑戦(上田紀行) 02-2 文系と理系の歴史から考える、リベラル・アーツのこれから(隠岐さや香) 02-3 アジア発、“未来の共通言語”となる知とは(山下範久) 03 パネルディスカッション 「能力主義」を越えるリベラルアーツ(熊谷晋一郎×上田紀行×隠岐さや香×山下範久/モデレーター:松原洋子) 質疑応答 「自由」とは、どういうことなのでしょうか? 注の引用・参照文献、ウェブサイト 【第2部】トークセッション(オンライン企画「SERIESリベラルアーツ」全10回より) 【パート1】社会を生きる 01 差別ってなんだろう?――#BlackLivesMatterを通して考える(坂下史子×南川文里) 02 なぜ人はあいまいさを嫌うのか――コントロールしたい欲望を解き放つ(小川さやか×美馬達哉) 03 わたしの“モヤモヤ”大解剖――わがまま論・つながり論を切り口に(飯田豊×富永京子) コラム1 〈自由〉な空間で生きる、学ぶということ(瀧本和成) 【パート2】人間を考える 04 人間関係のデモクラシー――“家族”から思考する(柳原恵×横田祐美子) 05 食のミライ――フードシステムとヴェジタリアン運動から考える(北山晴一×新山陽子) 06 わたしの“好き”を見つける――映画と音楽を切り口に(大﨑智史×小寺未知留) 07 まちあるきのすゝめ――迷える身体に向けて(加藤政洋×原口剛) 08 経済乱世を生きる――成長と分配と(熊澤大輔×田中祐二) コラム2 自由に生きる知性とはなにか(田中祐二) 【パート3】学びを続ける 09 その相談、あの本なら、こう言うね。――本が答える人生相談(瀧本和成×山本貴光×吉川浩満) 10 本を読む、ものを書く、編集する――本づくりの現場から(坂上陽子×瀧本和成×山本貴光×吉川浩満) おわりに(松原洋子) ーーー A5判 ソフトカバー 454ページ 送料:300円