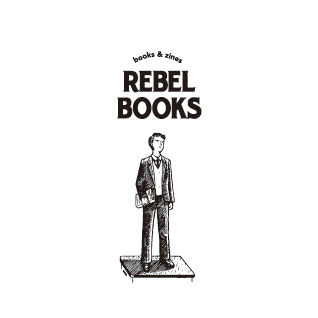-

『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』と『お金信仰さようなら』セット
¥3,520
ヤマザキOKコンピュータさんの著書二冊のセットです。 1540円+1980円=3520円 送料:300円
-

お金信仰さようなら | ヤマザキOKコンピュータ
¥1,980
「投資」というものの本質に迫り、それまで投資に興味がなかった(僕みたいな)人が目からウロコを落としまくった(投資を始めた人も多くいた)本『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』のヤマザキOKコンピュータさんによる待望の二作目。 ーーー 働いて働いて働いて働いて働いて、 収入を伸ばし、貯蓄を増やし、経済最優先の社会の中で、 成長と労働ばかりが求められてきた。 私たちは、「お金信仰の時代」に生まれ育った。 どれだけの資産があれば人は幸せになれるのか? 売れないものには価値がないのか? 経済成長すれば私たちの暮らしは豊かになるのか? 投資家やバンドマンとして、金融界のみならず国内外のパンク・シーンや多種多様な地下カルチャーを渡り歩いてきた著者が、 そこで培ってきた独自の視点でひとつひとつの疑問を解き、 貯蓄でもなく、選挙でもない、新しい選択肢を提示する。 『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』(6刷)で話題をさらった、 ヤマザキOKコンピュータの最新作。 今度こそ、くそつまらない未来は変えられる。 お金信仰が終わったあとの時代で、 何を指針に生きるのか? まだ名前の付いてない、新たな時代へと突き進む私たちのための入門書。 ー ◆目次 この本を書くにあたって 第1章 自分の〈いま〉に名前を付ける お金を信仰する時代/退屈で残酷な、グローバル資本主義社会/お金の大小しか見ない、一次元的な世界観/①市場信仰/②貨幣信仰/お金ではなく、お金信仰に別れを告げる 第2章 未来に不要なものは置いていく 新しい時代の歩き方/ハードコアパンクバンドが示してくれたアンサー/お金持ちになったら幸せになる?/国が豊かになったら貧困問題は解決する?/〈見えざる手〉は人々の理想を実現できる?/私たちの暮らしは本当に豊かになっている?/お金がここまで強く信仰される理由 第3章 新しい価値観に名前を付ける 新たな世代の、新たな価値観/アメリカのFIREムーブメント/中国の寝そべり主義者宣言/パラレルワールドをいまからやる/欧州パンクの共同体における知性あふれる価値観の共有/昔の商店街に見る、活気主義の世界/自分が本当に価値を感じるもの/接続性=人や社会とのつながり×文脈としてのつながり/①社会的接続価値/②文脈的接続価値/お金信仰は終わらせる力、接続性はつなぐ力/お金信仰に別れを告げるときが来た さいごに 私が出した、ひとつの答え ーーー 四六判 ソフトカバー(ビニールカバー) 224ページ 送料:300円 === くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話 https://rebelbooks.theshop.jp/items/32944059 『お金信仰さようなら』と『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』セット https://rebelbooks.theshop.jp/items/135117696
-

そいつはほんとに敵なのか | 碇雪恵
¥1,870
本書で著者の碇さんが参政党支持者に会いに行く章があるのですが、ここに大きなヒントがある気がしました。つまり、話してみないとわからないということ。 ーーー SNSを捨て、喧嘩を始めよう。 “合わない人”を遠ざける人生は、心地いいけどつまらない。 もっと沸き立ちたいあなたに送る、現代人必読の〈喧嘩入門エッセイ〉誕生! 駅でキレているおじさん、写真を撮りまくる観光客、理解できない政党と支持者、疎遠になった友だち、時にすれ違う家族や恋人……。 「敵」と決めつけて遠ざけるより、生身の体でかれらと出会い直し、逃げずにコミュニケーションをとりたい。 ZINE『35歳からの反抗期入門』が口コミで大ヒット中の書き手・碇雪恵による、待望の商業デビュー作。 憎みかけた「そいつ」と共に生きていくための思考と実践の記録をまとめた14編を収録。 ー 【目次】 喧嘩がしたい 純度の高い親切 友情の適正体重 悪意に顔があったーー映画『ルノワール』を観て 反抗期、その後 誰の場所でもない 身内をつくる(ひとりで考えてみた編) 身内をつくる(実践スタート編) 対戦じゃなくて協力モードで ティンプトンから始まるーー映画『ナミビアの砂漠』にみる恋愛と喧嘩 自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(準備編) 自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(実践編) ほんとは敵じゃない 時折自分を引き剥がすーー映画『旅と日々』を観て ーーー 四六判 ソフトカバー 176ページ 送料:300円
-

置き配的 | 福尾匠
¥2,310
ーーー コロナ禍以降、社会は置き配的なものとなった―― 「紀伊國屋じんぶん大賞2025 読者と選ぶ人文書ベスト30」の1位に輝いた気鋭の批評家が放つ最初にして最高の2020年代社会批評! 群像連載の「言葉と物」を単行本化。酷薄な現代を生き抜くための必読書! 「外出を自粛し、Zoomで会議をし、外ではマスクを着け、ドアの前に荷物が置かれるのに気づくより早く、スマホで通知を受け取る。個々人の環境や選択とはべつに、そのような生活がある種の典型となった社会のなかで、何が抑圧され、何が新たな希望として開かれているのか。そうした観点から、人々のありうべきコミュニケーションのかたちを問うこと、それがこの本のテーマです。(中略) つまり、狭義の置き配が「届ける」ということの意味を変えたのだとすれば、置き配的なコミュニケーションにおいては「伝える」ということの意味が変わってしまったのだと言えます。そして現在、もっとも置き配的なコミュニケーションが幅を利かせている場所はSNS、とりわけツイッター(現X)でしょう。保守とリベラル、男性と女性、老人と若者、なんでもいいですが、読者のみなさんもいちどは、彼らの論争は本当に何かを論じ合っているのかと疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。 (中略)置き配的な社会を問うことは、書くことの意味を立ち上げなおすことにも直結するはずです。」(本文より) 【目次】 序文 第1回 郵便的、置き配的 第2回 出来事からの隔離生活、あるいは戦争の二重否定 第3回 「たんなるパフォーマンス」とは何か 第4回 ネットワークはなぜそう呼ばれるか 第5回 フーコーとドゥルーズの「言葉と物」/青森で石を砂にした話 第6回 いま、書くことについて 第7回 置き配写真論、あるいは「コンテンツ」時代の芸術作品 第8回 ポジションとアテンション 第9回 サイボーグじゃない、君は犬だ、と私は言う 第10回 私でなくもない者たちの親密圏 第11回 暴力的な平等性と創造的な非対称性 あとがき ーーー 四六判 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

問いつめられたおじさんの答え【サイン本】 | いがらしみきお
¥2,420
SOLD OUT
ーーー ・耳の聞こえないひとは、どうやって聞くの? ・どうしてみんな、携帯ばっかり見てるの? ・家族って、なんですか? ・どうして嘘をついちゃいけないの? ・どうしてこんなに暑いの? ・友だちって、必要? ・勉強って、役に立つの? ・人はどうして死んじゃうの? ――子どもに聞かれたら困るその質問、おじさん=漫画家・いがらしみきおが答えます! 「webちくま」(筑摩書房)の人気エッセイ連載、待望の書籍化。 東日本大震災とコロナ禍を経て、『ぼのぼの』『I【アイ】』の漫画家・いがらしみきおがまっすぐ、そしてユーモラスに、素朴な疑問への答えと世界への向き合い方を綴ります。 子どもの「人生最初の疑問」に寄り添い、いがらしさんの作品に繰り返し描かれてきた「生まれてくること、生きていることの不思議さとよろこび」に大人を立ちかえらせてくれる一冊です。 各界の大人たちからの書き下ろし質問への回答を併録。 【書き下ろし=大人からの質問】 イ・ラン(シンガー・ソングライター/作家/映像作家) 牟田都子(校正者) 辻山良雄(書店「Title」店主) 大森時生(テレビ東京プロデューサー) 穂村弘(歌人) 水野しず(POP思想家、文筆業) 金子由里奈(映画監督) 玉置周啓(MONO NO AWARE) 根矢涼香(俳優・写真家) 佐々木敦(思考家/批評家/文筆家) 乗代雄介(作家) 品田遊(小説家) 榎本俊二(漫画家) 上田信治(俳人) ぼく脳(アーティスト) ーーー 四六判 ソフトカバー 送料:300円
-

絶望と熱狂のピアサポート 精神障害当事者たちの民族誌 | 横山紗亜耶
¥2,970
ーーー 東畑開人さん推薦 「最終章まで読み通してほしい。必ず震撼するから。 障害者とは何か、健常者とは何か、そして「対等」とは何か。 ユートピアが描かれ、ユートピアが崩壊し、そして剥き出しの「対等」が現れる」 絶望的なまでに健常者中心の社会を、熱狂的な〈お祭り〉でかき乱す、横浜ピアスタッフ協会(YPS)。「ピアになる」瞬間を追い求める当事者たちの活動、法人化への葛藤、それを「書く」ことの政治性……10年間の調査に基づくノンフィクション。 【はじめにより】 本書は、対等になるための行動のひとつのやり方として、YPSの人々が編み出した〈お祭り〉に迫る。YPSの〈お祭り〉とは、絶望的なまでに不平等な社会をかき乱し、教科書にあるような前提を壊すことで、対等な関係を築こうとするピアサポートのあり方である。社会をかき乱すことには、責任がつきまとう。こうした責任を引き受けることでこそ、〈お祭り〉は熱狂的なまでの盛り上がりを見せていた。 私たちは対等ではない。それでも私は、あらゆる差異が生み出される仕組みを直視することを通して、対等になりたい。たとえそれが叶わぬ願いであったとしても、私はそのために考え、行動し続けたいのだ。 ーーー 四六判 ソフトカバー 302ページ 送料:300円
-

明るい部屋 写真についての覚書 | ロラン・バルト
¥3,080
哲学者・記号学者・批評家であるロラン・バルトが写真の本質を掘り下げる。写真論の古典として広く読まれている一冊。 ーーー 《狂気をとるか分別か? 「写真」はそのいずれをも選ぶことができる。「写真」のレアリスムが、美的ないし経験的な習慣(たとえば、美容院や歯医者のところで雑誌のぺージをめくること)によって弱められ、相対的なレアリスムにとどまるとき、「写真」は分別のあるものとなる。そのレアリスムが、絶対的な、始源的なレアリスムとなって、愛と恐れに満ちた意識に「時間」の原義そのものをよみがえらせるなら、「写真」は狂気となる》(ロラン・バルト) 本書は、現象学的な方法によって、写真の本質・ノエマ(《それはかつてあった》)を明証しようとした写真論である。細部=プンクトゥムを注視しつつ、写真の核心に迫ってゆくバルトの追究にはまことにスリリングなものがある。 本書はまた、亡き母に捧げられたレクイエムともいえるだろう。私事について語ること少なかったパルト、その彼がかくも直接的に、母の喪の悲しみを語るとは! 本書は明らかに、著者のイメージ論の総決算であると同時に、バルトの『失われた時を求めて』となっている。《『明るい部屋』の写真論の中心には、光り輝く核としての母の写真の物語が据えられている》(J・デリダ) ーーー 四六判 ハードカバー 194ページ 送料:300円
-

私が間違っているかもしれない
¥1,870
ーーー これは悲観ではなく、物事を的確にとらえる思考。 あらゆる摩擦は「自分が正しい」という前提に立ってしまっていることに由来する。 著者ビョルン・ナッティコ・リンデブラッド氏の生涯を通じて、静謐で穏やかな心に変わる教え。 【本書のあらすじ】 ビョルン氏はスウェーデンでエリート教育を受け、経済界で若くして成功を収め、26歳でCFOに就任するなど華やかなキャリアを築く。しかし、心の空虚感と違和感に耐えられなくなり、すべてを手放して出家。タイの森の中の僧院で17年間、厳しい戒律のもと修行に打ち込む。金銭、あらゆる欲、娯楽、自由といった一切を断ったその生活で、彼が得た最も大きな学びは「自分の考えが常に正しいとは限らない」という気づきだった。 帰国後は講演や執筆を通じて、内面の静けさと「私が間違っているかもしれない」教えを説き、スウェーデン中で一大センセーションを巻き起こす。晩年にはALSを患い、死と向き合いながらも、執着から離れた心の在り方を静かに説いた。 「私が間違っているかもしれない」と言える謙虚さの中に真の強さが宿ることを示した彼の人生とメッセージは、「生涯の支えになる」「一生の指針」と今も支持を集め続ける。 ー ★33か国で翻訳 ★スウェーデン歴史的ベストセラー! 人口1000万の国で44万部! 2020年から3年連続最も売れたノンフィクション本 ★台湾年間総合1位!(2024年) 海外書として異例の快挙 ★韓国、イギリスなど各国続々ベストセラー! 韓国では特別版を製作するなど異例の熱狂 ーーー #私が間違っているかもしれない #レベルブックス
-

ウォークス 歩くことの精神史
¥4,950
広大な人類史のあらゆるジャンルをフィールドに、〈歩くこと〉が思考と文化に深く結びつき、創造力の源泉であることを解き明かす。レベッカ・ソルニットによる名著。 ーーー (出版社による紹介) アリストテレスは歩きながら哲学し、彼の弟子たちは逍遥学派と呼ばれた。 公民権運動、LGBTの人権運動の活動家たちは街頭を行進し、不正と抑圧を告発した。 彼岸への祈りを込めて、聖地を目指した歩みが、世界各地で連綿と続く巡礼となった。 歴史上の出来事に、科学や文学などの文化に、なによりもわたしたち自身の自己認識に、 歩くことがどのように影を落しているのか、自在な語り口でソルニットは語る。 人類学、宗教、哲学、文学、芸術、政治、社会、レジャー、エコロジー、フェミニズム、アメリカ、都市へ。 歩くことがもたらしたものを語った歴史的傑作。 歩きながら『人間不平等起源論』を書いたルソー。 被害妄想になりながらも街歩きだけはやめないキェルケゴール。 病と闘う知人のためにミュンヘンからパリまで歩き通したヘルツォーク。 ロマン主義的な山歩きの始祖・ワーズワース。 釈放されるとその足でベリー摘みに向かったソロー。 インク瓶付きの杖を持っていたトマス・ホッブス。 ラッセルの部屋を動物園の虎のように歩くウィトゲンシュタイン。 刑務所のなかで空想の世界旅行をした建築家アルベルト・シュペーア。 ヒロインに決然とひとり歩きさせたジェーン・オースティン。 その小説同様に大都市ロンドン中を歩きまわったディケンズ。 故郷ベルリンを描きながらも筆はいつもパリへとさまようベンヤミン。 パリを歩くことをエロチックな体験とみなしたレチフ・ド・ラ・ブルトンヌ。 歩行を芸術にしたアーティスト、リチャード・ロング。 ......歩くことはいつだって決然とした勇気の表明であり、不安な心をなぐさめる癒しだった。 【目次】 第1部 思索の足取り The Pace of the Thoughts 第一章 岬をたどりながら 第二章 時速三マイルの精神 第三章 楽園を歩き出て――二足歩行の論者たち 第四章 恩寵への上り坂――巡礼について 第五章 迷宮とキャデラック――象徴への旅 第2部 庭園から原野へ From the Garden to the Wild 第六章 庭園を歩み出て 第七章 ウィリアム・ワーズワースの脚 第八章 普段着の一〇〇〇マイル――歩行の文学について 第九章 未踏の山とめぐりゆく峰 第十章 ウォーキング・クラブと大地をめぐる闘争 第3部 街角の人生 Lives of the Streets 第十一章 都市――孤独な散歩者たち 第十二章 パリ――舗道の植物採集家たち 第十三章 市民たちの街角――さわぎ、行進、革命 第十四章 夜歩く――女、性、公共空間 第4部 道の果てる先に Past the End of the Road 第十五章 シーシュポスの有酸素運動――精神の郊外化について 第十六章 歩行の造形 第十七章 ラスベガス――巡りあう道 訳者あとがき 注釈と出典 ーーー 四六判 ハードカバー 520ページ 送料:600円(レターパックプラス)
-

猫に学ぶ いかに良く生きるか | ジョン・グレイ
¥3,300
ーーー (出版元による紹介) 「私が猫と遊んでいるとき、私が猫を相手に暇つぶしをしているのか、猫が私を相手に暇つぶしをしているのか、私にはわからない。」これはモンテーニュの言葉。 政治哲学者ジョン・グレイは本書で、何世紀にもわたる哲学や、コレット、ハイスミス、谷崎らの小説を渉猟し、人が猫にどう反応し行動するかを定めてきた複雑で親密なつながりを探究している。 その核心にあるのは猫への感謝の念だ。なぜなら、どんな動物にもまして猫は、人間という孤独な存在にもそなわっている動物本性を感じさせてくれるからである。 「しばしば数億円単位の実験室を持っている自然科学者から見ると、哲学者は自分の脳ミソしか持たない、典型的なプロレタリアである。その貧乏人に猫という小さな道具を与えてやったら、立派な哲学書と人生論が生まれた。人生の重荷を感じている人には、本書を読むことが救いにはならなくても、最低〈気晴らし〉にはなると思う。猫好きにとっては面白い上に感動的でもあり、つい読み切ってしまう。」養老孟司 ーーー 四六判 ハードカバー 184ページ 送料:300円
-

人生で必要な決め方はすべて「進路選択」で学べる | 山口大輔/山本尚毅
¥1,760
ーーー --かつて受験生だったすべての大人たちへ。人生の岐路で後悔しないための「進路の教室」開講! -- 仕事でいつも正しい判断ができていますか。人生の節目節目で、つねに後悔しない決断をしてきたでしょうか。おそらく多くの人は、常識とか、慣習とか、前例とか、しきたりといったことを手がかりに、「何となく」「とりあえず」で選択しているはずです。 本書は、のべ1万人の高校生が受講した進路探究プログラム『ミライの選択』を大人向けに完全書き下ろし。 就職、転職、結婚、引っ越し、病気、終活……人生の岐路で後悔しないために、河合塾が編み出した「納得できる意思決定」の公式をお教しえます。 ***もちろん、子どもの進路選び・受験にも役立ちます。*** *「決められない自分」をどうにかしたい/やりたいことが「まだ」わからない/もっとちゃんと考えて決めたい人に!* ~数年前、私たちは河合塾で『ミライの選択』という進路を考えるプログラムを開発し、学校向けに提供を始めました。ただ、「この内容は、大学生や社会人になっても役に立つに違いない」という声をもらうようになったのです。そこで『ミライの選択』を土台にしつつ、あらゆる世代の方たちに「決め方が身につく方法」をお伝えしたいと思ってできたのが本書です。(序章より) 【目次】 序 章 「決め方」を手に入れよう 第1章 「決めること」が難しくなったわけ 第2章 誰も「決め方」なんて教えてくれなかった 第3章 「決め方」に大切な3つのこと 第4章 「自分の頭」で考えて決めよう 第5章 選択は「憧れ」から始まる 第6章 選択は「調べる」ことで広がる 第7章 子どもの選択に大人ができること・してはいけないこと ーーー 四六判 ソフトカバー 260ページ 送料:300円
-

ルッキズムってなんだろう? みんなで考える外見のこと | 西倉実季
¥1,760
昨今日本でルッキズム(=人を見た目で判断あるいは見た目で差別すること)が一層強化されているような気がしています。本書では「ルッキズムとは何か」「ルッキズムはなぜ問題か」「どうすればルッキズムを解消できるのか」の三つについて論じます。「中学生の質問箱」シリーズのなかの一冊。 ーーー (出版元による紹介) ここ数年、何かと話題になっている「ルッキズム」。しかし、そもそも「ルッキズム」とはどういう意味で、どんなことを指すのでしょうか。また、「ルッキズム」は何がどのように問題なのでしょうか。中高生だけではなく、大人にいたるまで、多くの人の心をモヤモヤさせる「ルッキズム」。本書では、「ルッキズム」に関する論点を、社会学を専門とする著者が、学校の校則やミスコン、友だちとの会話など、身近な事例をもとにしながらわかりやすく解説します。読者が社会の中で外見をめぐるさまざまな問題に遭遇した際に、「ルッキズム」やそれにまつわるさまざまな問題を俯瞰的に考えられるようになるための“きっかけ”をもたらす1冊です。 ーーー 四六判 ソフトカバー 216ページ 送料:300円
-

それでも人生にイエスと言う | V.E.フランクル
¥1,870
ナチスによる強制収容所の体験として全世界に衝撃を与えた『夜と霧』の著者が、その体験と思索を踏まえてすべての悩める人に「人生を肯定する」ことを訴えた感動の講演集。 #四六判 ハードカバー 224ページ 送料:300円
-

夜と霧【新版】| ヴィクトール・E・フランクル
¥1,870
強制収容所を生き延びた著者が、その経験を精神科医/心理学者として振り返り、分析する。鋭い観察、深い洞察に満ちた、奇跡的な、20世紀を代表する名著。ドキュメンタリーでもあり、哲学であり、文学でもある。驚くほど読みやすいのも特徴。 ーーー 〈わたしたちは、おそらくこれまでのどの時代の人間も知らなかった「人間」を知った。では、この人間とはなにものか。人間とは、人間とはなにかをつねに決定する存在だ。人間とは、ガス室を発明した存在だ。しかし同時に、ガス室に入っても毅然として祈りのことばを口にする存在でもあるのだ〉 「言語を絶する感動」と評され、人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、日本をはじめ世界的なロングセラーとして600万を超える読者に読みつがれ、現在にいたっている。原著の初版は1947年、日本語版の初版は1956年。その後著者は、1977年に新たに手を加えた改訂版を出版した。 世代を超えて読みつがれたいとの願いから生まれたこの新版は、原著1977年版にもとづき、新しく翻訳したものである。 私とは、私たちの住む社会とは、歴史とは、そして人間とは何か。20世紀を代表する作品を、ここに新たにお送りする。 ーーー 四六判 ハードカバー 184ページ 送料:300円
-

ハンナ・アーレント、三つの逃亡 | ケン・クリムスティーン
¥3,960
ユダヤ人として戦争の世紀に生まれ落ち、現実に向かって“なぜ?”と問いつづける。不世出の政治哲学者ハンナ・アーレントの生涯を描いたグラフィックノベル。 22.2 x 16.5 x 2.3 cm 送料:300円
-

ラーゴムが描く社会 スウェーデンの「ちょうどよい」国づくり | 鈴木賢志
¥2,420
ーーー (出版社による紹介) 自分も他者も尊重しつつ、何ごとにつけ「ほどほど」をよしとする哲学の奥深さ。幸福度ランキング上位国に学ぶ国家像 ー スウェーデンには、人々に愛されてきた「ラーゴム」という考え方がある。自分を大切にしつつ、周りのことも考えて多くを求めすぎない、「ちょうどよい状態」を美徳とする一種の行動規範で、この国の人々のライフスタイルの基本となっている。この「ラーゴム」の精神が、個人だけでなく、スウェーデンという国の政治や経済、社会システムにも力強く息づいているのではないか——そう考え、本書を著すことにした。 スウェーデンは国際的に見ても非常にユニークな国である。「高福祉高負担」という観点からはアメリカの対極に位置するが、経済的な豊かさではアメリカを上回っており、ご存じのように国民の「幸福度」は非常に高い。 日本を含む多くの社会では、「高福祉高負担は勤労意欲を阻害し、働くだけ損だと考えて怠ける人が増える」という通念が根強い。しかしそうした通念をひっくりかえすようなことがこの国では日々起きている。その謎を解くカギが「ラーゴム」にあると断言したい。 本書では、現在のスウェーデンを形づくっている社会システムや政治・経済・ビジネスの仕組み、先進的な環境政策などを「ラーゴム」の視点から読み解くことで、この国を総体的に理解することを目指した。スウェーデンや北欧に関心のある人が、各専門領域に踏み込む前に、まずはこの国の全体像をつかむためのテキストとしても活用できるものになっている。 いま世界的に、社会の中に分断や対立をあえてつくり出し、それを煽ることで支持を拡げるという手法がアメリカを中心に蔓延している。スウェーデンが歩み続ける「ラーゴム」の道は、その有力なアンチテーゼとなるはずだ。むろん、そこには悩みも揺らぎもあるわけだが、それも含めて、日本社会の今後のあり方を考えるヒントともなるだろう。 ーーー 四六判 ソフトカバー 224ページ 送料:300円
-

さみしくてごめん | 永井玲衣
¥1,760
『水中の哲学者たち』『世界の適切な保存』が当店でもロングセラー、永井玲衣さんの哲学エッセイ。 ー 哲学は心細い。さみしい。だがわたしは、さみしいからこそ哲学をしているような気がする。生まれてきたことがさみしい。わからないことがさみしい。問いをもつことがさみしい。問いと共に生きることがさみしい。(本文より) ー ことばが馬鹿にされ、ことばが無視され、ことばが届かないと思わされているこの世界で、それでもことばを書く理由は何だろう。わたしの日記は、戦争がはじまって終わっている。あの瞬間から、日記は戦時中のものとなった。 だが、ほんとうにそうなのだろうか。戦争はずっとあったし、いまもある。わたしが絶望したあの戦争は、いまもつづいている。だからあの日記はすでに戦時中のものだったし、この本も、やはり戦時中のものである。 とはいえ、わたしたちの生活に先立って、戦争があるわけではない。生活の中に戦争が入り込むのだ。どうしたって消すことのできない、無数の生の断片があるのだ。たとえ「対話」ができず、あなたのことばを直接きくことができなかったとしても、決して「ない」のではない。(「あとがき」より) ー 四六判 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

水中の哲学者たち | 永井玲衣
¥1,760
哲学のおもしろさ、不思議さ、世界のわからなさを伝える哲学エッセイ。じわじわと売れ続けているロングセラーです。著者の永井玲衣さんは若き哲学研究者にして、哲学対話のファシリテーター。 四六判 ソフトカバー 268ページ 送料:300円
-

哲学対話日記
¥1,000
哲学対話をしている11名による対話のあった日の日記18本。表紙デザインも素晴らしいですよね。 ーーー 人と集まって日常とは異なる空間をつくる哲学対話の時間は、それぞれの日常とゆるやかにつながっている。街で、バーで、学校で、オンラインで、家族で。 ーーー ■著者 麻生修司 井尻貴子 江藤信暁 小川泰治 荻野陽太 片柳那奈子 古賀裕也 竹岡香帆 得居千照 堀静香 山本和則 ■企画立案・編集 小川泰治 ■表紙デザイン こやまりえこ ーーー B6/106ページ 送料:300円
-

世界の適切な保存 | 永井玲衣
¥1,870
当店でも前著『水中の哲学者たち』がロングセラー、各地で哲学対話を行う永井玲衣さんの哲学エッセイ新刊。 ーーー (出版社による紹介文) ロングセラー『水中の哲学者たち』で話題沸騰! 対話する哲学者・永井玲衣、待望の最新刊! 見ることは、わたしを当事者にする。 共に生きるひとにする。 世界をもっと「よく」見ること。その中に入り込んで、てのひらいっぱいに受け取ること。 この世界と向き合うための哲学エッセイ。 わたしはどうやら、時間が流れていくにしたがって、 何かが消えるとか、失われるとか、忘れられるということがおそろしいらしい。 ここに書かれたもの。その何倍もある、書かれなかったもの。 でも決してなくならないもの――。 生の断片、世界の欠片は、きかれることを待っている。じっとして、掘り出されることを待っている。 ーーー 四六判 ソフトカバー 288ページ 送料:300円
-

歩くという哲学 | フレデリック・グロ
¥2,640
「世界を変えた思想や哲学、文学、詩は歩行から生まれた」「歩くことは、最もクリエイティブな行為」やっぱり、そうですよね。歩きましょう、歩いて、読んで、また歩いて。 ーーー (出版社による紹介) 世界中に影響を与え、世界を動かした思想家、哲学者、作家、詩人の思索の多くは、歩くことによって生まれてきました。歩くことは、最もクリエイティブな行為なのです。また素晴らしいアイデアを出す歩き方にも様々なものがあります。 歩くことは、単なる機械的な繰り返しの動作以上のものであり、自由の体験であり、緩慢さの練習であり、孤独と空想を味わい、宇宙空間に体を投じることでもあります。 著者のフレデリック・グロが、哲学的な瞑想の連続を読者とともに探索しながら、ギリシア哲学、ドイツ哲学と詩、フランス文学と詩、英文学、現代アメリカ文学等の、著名な文学者、思想家の歩き方について探求します。 ソクラテス、プラトン、ニーチェ、ランボー、ボードレール、ルソー、ソロー、カント、ヘルダーリン、キルケゴール、ワーズワース、プルースト、ネルヴァル、ケルアック、マッカーシーらにとって、歩くことはスポーツではなく、趣味や娯楽でもなく、芸術であり、精神の鍛練、禁欲的な修行でした。 また、ガンジー、キング牧師をはじめ、世界を動かした思想家たちも歩くことがその知恵の源泉でした。 歩くことから生まれた哲学、文学、詩の数々に触れてみましょう。 ーーー A5判 ソフトカバー 340ページ 送料:300円
-

迷うことについて | レベッカ・ソルニット
¥2,640
ーーーーーーーーーー 出版社による紹介文 ーーーーーーーーーー わたしたちはいつだって迷っている。夜明け前が一番暗いと知っているけど、その暗さに耐えられるときばかりじゃない。失われたもの、時間、そして人びと。個人史と世界史の両方に分け入りながら、迷いと痛みの深みのなかに光を見つける心揺さぶる哲学的エッセイ。 全世界を見失うがよい、迷いながら自分の魂を見出だすのだ。ーーH・デヴィッド・ソロー。 いにしえの哲学者は「それがどんなものであるかまったく知らないものを、どうやって探求しようというのか」と問うた。 一見、この問いはもっともだ。でも、いつだってわたしたちが探しているのは、どんなものかまったくわからないものだ。 進むべき道に迷い、〈死の谷〉で帰り道を見失い、愛の物語はガラスのように砕け散る。 脚本はついに一文字も書かれず、囚われ人は帰ってこない……。 旧大陸からやってきて、いつしかアメリカ西部のどこかに姿を消した曽祖母。 たどり着いた新大陸を10年にもわたってさまよった最初期の入植者カサ・デ・バカの一行。 嵐のような10代の冒険をともに過ごし、ドラッグで命を落とした親友。 ルネサンス以来描かれるようになった〈隔たりの青〉。 かつて愛した砂漠のような男。 父との確執。 ソルニット自身の人生と、アメリカを中心とした歴史と文化史に視線を向けて、 メノンとソクラテス、ベンヤミンやヴァージニア・ウルフらとともに、 迷うことの意味と恵みを探る傑作。 ーーーーーーーーーー 送料:300円
-

普通の奴らは皆殺し | アンジェラ・ネイグル
¥2,420
ーーー (出版社による紹介) なぜリベラルは敗北するのか? なぜトランプは大統領になれるのか? オルタナ右翼はリベラルが生み出したモンスターである。オルタナ右翼を正しく理解せずに、リベラルの勝利はない。 ー オルタナ右翼・トランプ主義者研究の最重要書 本書は、2010年代初頭に起こったインターネット文化戦争を忠実に記録し、それが2016年のドナルド・トランプ大統領誕生に大きな役割を果たした「オルタナ右翼」となって発展する道行きをマッピングする。オルタナ右翼の特徴が、60年代カウンターカルチャーに由来する「侵犯的な反道徳スタイル」だとしたら? 本来リベラルであったインターネットのサブカルチャーは、どのように右傾化し、メインストリームを征服していったのか? ー 「中流階級が自己懲罰として自らを鞭打ち、それが危険な荒波となってリベラル左派を飲み込み、道を見失わせる。アンジェラ・ネイグルはそのなかで、灯台守となってわたしたちに出口を示す。彼女の分析は容赦ないが、決して残酷ではない。疎外と敗北に慣れすぎた多くの左派とは異なり、ますます残酷になる世界を変える唯一の方法として政治を信じている。彼女はわたしが待ち望んでいた作家であり社会評論家だ」――コナー・キルパトリック「ジャコバン・マガジン」 「ネイグルは世界でもっとも輝かしい光のひとりであり、知的同調からの独立を宣言した新世代の左翼作家・思想家である」――キャサリン・リュー(作家・アメリカ文化理論家) 「わたしたちの時代の混沌のただなかで、頼るべき人としてアンジェラ・ネイグルのような聡明で恐れ知らずの批評家がいることは救いになる。彼女は右翼のサブカルチャーの出現とその重要性を適切に説明することができないリベラルの陳腐な教義で我慢することを好まず、インターネットの洞窟のもっとも汚れた場所まで降りて、鋭く冷静な分析をわたしたちに与えようとする唯一の存在だ」——アンバー・アリー・フロスト「チャポ・トラップ・ハウス」 「アンジェラ・ネイグルは、有害なレイシズムとミソジニーが先端的なカウンターカルチャーのパッケージとして現れたとき、それに対してダブルスタンダードを用いることを一貫して拒否した、数少ない書き手のひとりである。本書は、ウェブ上のニヒリズムとファシズムがもつ新しい一面に関する見事な解説であり、この新しいニヒリズムとファシズムは、もはや「(笑)」をつけておけばよいのだと言って逃げることはできない」——デイビッド・ゴロンビア(『ビットコインのポリティクス:過激な右翼としてのソフトウェア』著者) ー [もくじ] 序章 希望からゴリラのハランベに 第1章 リーダーなきデジタル反革命 第2章 侵犯のオンライン政治 第3章 オルト・ライトのグラムシ主義者たち 第4章 ブキャナンからヤノプルスまでの保守派文化戦争 第5章 Tumblrから大学キャンパスでの戦争へ:ウェブ上の正しさのエコノミーに飢餓状態を創り出すこと 第6章 マノスフィア(男性空間)に入会すること 第7章 つまらないビッチ、ノーマルな連中、そして絶滅寸前メディア 結論 あの冗談はもう面白くない——文化戦争はオフラインへ [著者] アンジェラ・ネイグル ANGELA NAGLE 1984年、アメリカ・テキサス州生まれ、アイルランド・ダブリン在住の作家・社会評論家。オルタナ右翼の専門家として「ニューヨーカー」「バッフラー」「ジャコバン」「アイリッシュ・タイムズ」ほか多くの雑誌に寄稿している。反フェミニストのオンライン・サブカルチャーに関する研究で博士号を取得。2017年に刊行した『KILL ALL NORMIES』は、白人至上主義のオルタナ右翼の起源に迫るドキュメンタリー『Trumpland: Kill All Normies』の原作となった。著書に『緊縮財政下のアイルランド 新自由主義の危機と解決策』 (コリン・コールターとの共著)など。 ーーー 新書版 ソフトカバー 240ページ 送料:300円
-

愛を貫く タコス・トレス・エルマノスの革命 | 古屋大和(タコス・トレス・エルマノス)
¥2,200
タコス愛好家界隈で大絶賛されている話題のタコス屋、タコス・トレス・エルマノスの店主による著書です。 ーーー (出版社による紹介) 本場メヒコから火が着いた。 なぜ日本のタコスとここまで違うのか? 「メヒコのタコスそのものが食べられる」と、日本よりも先にメヒコ本国で話題になったタコス・トレス・エルマノス。8万人いるインスタフォロワーの7割が外国人で、原宿店は世界各地から集まる観光客の新しい巡礼スポットとなっている。店内はスペイン語が飛び交い、「ストリートフードとしてのタコス」をその文化ごと伝えるスタイルで、連日開店前から大行列、売り切れが続き、代表・古屋大和の愛情あふれる歯に衣着せぬパーソナリティもあり、熱狂的なファンを日々増やしている。メヒコの食材を使い、現地のスタッフを雇用することで「メヒコの人たちに還元する」ことをポリシーとし、アメリカ経由ではない「本場のタコス」を愛をもって伝えている。 ー 脱アメリカ メヒコの道端タコスで「戦後」を終わらせる ー [もくじ抜粋] インディヘナの女の子/「日本人は諦めない」/アメリカの嘘/メヒコの洗礼/エカテペクの日々/お父さんの教え/道端の気遣い/自分でなんとかする/道端タコスの流儀/あの味とスタイルを再現する/死ぬのは怖くない/フレサになるな/メヒコのナマリ/北に近づくな/ニュークラシック/粋と野暮/テックス・メックス/なぜメヒコの食文化は間違って伝わるのか/ソーシャライズを磨く/「知らぬを知る」からはじめる/「メヒコで修行しました」/一瞬一瞬の輝き/「絶対謝んなよ」/水は上から下に流れる/土壌をつくる/メヒコに還元する/ちゃんと嫌われる [著者プロフィール] 古屋大和(Yamato Furuya) 1974年、山梨県富士河口湖町生まれ。富士山信仰の浅間神社・葭之池温泉の家系で育ち、ミュージシャン、広告映像制作などを経て、2015年にメヒコへ移住。2021年にタコス専門店トレス・エルマノスを起業。フードトラックで横須賀、福生、横田などに出店し人気を博す。2022年に山中湖店、2024年に原宿店をオープン。日本より先にメヒコ本国で「メヒコのタコスそのものだ」と話題となり、日本にある唯一無二の道端タコスとして支持されている。愛称はジャミタ(Yamita)。 ーーー 新書判 ソフトカバー 192ページ 送料:300円