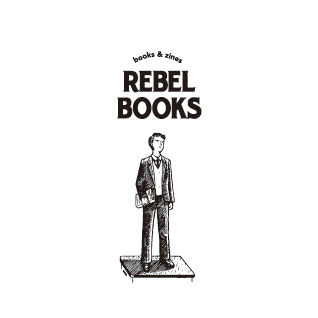-

客になる | 乾隼人
¥1,200
編集者・乾隼人さんによる、「いい客」について考えたzine。このテーマについて、それぞれに考えるきっかけになります。 乾さんは「A GUIDE to KUROISO」(通称黒磯本)などを編集した方です https://rebelbooks.theshop.jp/items/60401480 A6サイズ 送料:300円
-

本をすすめる 書評を書くための技術 | 近藤康太郎
¥2,090
『三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾』 『百冊で耕す 〈自由に、なる〉ための読書術』 『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』 等の近藤康太郎さんによる「書評を書くための技術」 ーーー 書評の愛が深いとき、読み手はその本を買う 「感動!」「涙が止まらない」「ほっこり」を封印して〈熱〉を伝える 朝日新聞記者で名文家の著者が、本の選び方、読み方・書き方まで対話形式でくわしく解説。X、Instagram、note、Amazonでのブックレビュー初心者からプロの書評までに対応。 ーーー 四六判 ソフトカバー 316ページ 送料:300円
-

本当にはじめての遠野物語 | 富川岳
¥1,980
私自身『遠野物語』は随分昔に買ったものの文語体の文章になかなか入り込めず、序盤で何度も挫折していたのですが、このビジュアル的にも楽しいオールカラーの素晴らしいガイドがあればもう大丈夫だと思いました。 ーーー 構想7年。河童、ザシキワラシ、天狗。日本民俗学の夜明けを告げた歴史的名著『遠野物語』を、かつて10ページで挫折した著者がおくる、絶対にくじけず、楽しく深く明快に学べる、はじまりの一冊。さぁ、めくるめく物語の世界へ! 「いま手にとっていただいている『本当にはじめての遠野物語』は、そんな僕のように数ページで断念してしまった人をはじめ、なんとなく知ってるけど読んだことのなかった人、またこの先もひょっとしたら読む予定のない人にこそ、読んで欲しいと思って書いた本です。読み方のコツや楽しみ方さえわかれば、絶対に『遠野物語』は面白い本、教材になる。そう確信しています。さあ、食わず嫌いは今日でおしまい。めくるめく物語の世界をのぞき込んでみましょう。」(「はじめに」から引用) ーーー 【内容】 ◇はじめに ◇遠野とは? ◇『遠野物語』とは? ◇登場キャラクターの紹介 (河童、天狗、山男、山女、ザシキワラシ、オシラサマ、ヤマダチ、魂、狼と猿) ◇『遠野物語』誕生の秘密① 出会い編 ◇『遠野物語』誕生の秘密② 地理編 ◇『遠野物語』に込められた想い ◇おわりに ◇はじめての遠野物語にオススメな本 【概要】 ・1,980円(税込) ・A5サイズ、96ページフルカラー ・オリジナル『遠野物語』マップ付(第2版より) ・著者:富川岳 ・編集:宮本拓海 ・デザイン:白水雄治(CHACO)、切り絵/挿絵:鳩乃羽子(CHACO) ・発行:遠野出版(自費出版) ーーー 送料:300円
-

創作者のための読書術 読む力と書く力を養う10のレッスン | エリン・M・プッシュマン=著 中田勝猛=訳
¥2,970
私も今読んでます。小説・詩・エッセイ、どんな文章を書く人も対象になる本だと思います。 ーーー 「読む」解像度が上がれば、「書ける」ようになる! 作家は他の作品をどう読んでいるのか?──プロの書き手の読み方を知ることで、小説やエッセイ、漫画からウェブメディア上での執筆まで、書く技術を向上させよう 優れた作家になるための第一歩は、優れた読書家になること。プロの書き手が行っている「分析的読み方」を学ぶことで、自分の作品を書き出す一歩が見つかり、さらに書き手としてのスキルを高めることができる──そんな「書く」ための学びとなる読書術を徹底伝授。ジャンル、ナラティブアーク、キャラクター造形、語りの視点など、執筆術の使われ方をひもときながら、現代の小説やノンフィクション、詩、SNS、ブログなどの豊富な引用例を繰り返し読むことで、創作に役立つ効果的な読み方=精読が自然と身につく一冊。 【本書のポイント】 ・すべての「書く」人に役立つ「読み方」がわかる ・創作理論が実際の作品にどう使われているかを学べる ・言葉にする力を育て、自作の文章に応用できる ・引用作品を多角的な視点から何度も読み込むことで、分析的読書の訓練ができる ・各章末に引用作品の考察のポイントと自作のための執筆のヒント付き ーーー A5判 ソフトカバー 416ページ 送料:300円
-

問いつめられたおじさんの答え【サイン本】 | いがらしみきお
¥2,420
ーーー ・耳の聞こえないひとは、どうやって聞くの? ・どうしてみんな、携帯ばっかり見てるの? ・家族って、なんですか? ・どうして嘘をついちゃいけないの? ・どうしてこんなに暑いの? ・友だちって、必要? ・勉強って、役に立つの? ・人はどうして死んじゃうの? ――子どもに聞かれたら困るその質問、おじさん=漫画家・いがらしみきおが答えます! 「webちくま」(筑摩書房)の人気エッセイ連載、待望の書籍化。 東日本大震災とコロナ禍を経て、『ぼのぼの』『I【アイ】』の漫画家・いがらしみきおがまっすぐ、そしてユーモラスに、素朴な疑問への答えと世界への向き合い方を綴ります。 子どもの「人生最初の疑問」に寄り添い、いがらしさんの作品に繰り返し描かれてきた「生まれてくること、生きていることの不思議さとよろこび」に大人を立ちかえらせてくれる一冊です。 各界の大人たちからの書き下ろし質問への回答を併録。 【書き下ろし=大人からの質問】 イ・ラン(シンガー・ソングライター/作家/映像作家) 牟田都子(校正者) 辻山良雄(書店「Title」店主) 大森時生(テレビ東京プロデューサー) 穂村弘(歌人) 水野しず(POP思想家、文筆業) 金子由里奈(映画監督) 玉置周啓(MONO NO AWARE) 根矢涼香(俳優・写真家) 佐々木敦(思考家/批評家/文筆家) 乗代雄介(作家) 品田遊(小説家) 榎本俊二(漫画家) 上田信治(俳人) ぼく脳(アーティスト) ーーー 四六判 ソフトカバー 送料:300円
-

本屋の人生 | 伊野尾宏之
¥1,870
ーーー 新宿・中井の親子二代にわたる本屋の記録と営み。 昭和三十二年開店、 令和八年閉店。 材木屋をたたみとりあえず本屋を開いた父。 フリーターからとりあえず本屋を継いだ息子。 伊野尾書店は、ただそこにあるだけの店だった。 ーーー 四六判 ソフトカバー 224ページ 送料:300円
-

感情労働の未来 脳はなぜ他者の“見えない心”を推しはかるのか? | 恩蔵絢子
¥2,090
ーーー AI時代、人間が持つ最大の能力は、感情になる! 感情を抑圧し“他者にあわせる“ストレスフルな現代から、“他者を理解する“感情的知性の未来へ。人間の可能性に話題の脳科学者が迫る。 ーーー 四六判変型 ソフトカバー 244ページ 送料:300円
-

改元【サイン本】 | 畠山丑雄
¥1,980
ーーー 【第38回三島由紀夫賞候補作!】 マジック・リアリズム的手法と豊かな物語性、確固たる強度を持つ文体を具えた新星による、抵抗と革命の二篇を書籍化。 ー 「君は今回の譲位についてどう思うかね?」 「龍の話じゃありませんでしたか?」 「そうだよ」久間さんは目を細め暗い光を溜めた。「ずっと前から私はその話しかしていない」 龍の夢が「私」を通過するとき、この国のもうひとつの姿があらわれる―― 現代日本小説屈指の剛腕による、抵抗と革命の二篇。 ー 改元の年の異動で山奥の町に着任した公務員「私」は、集落に伝わる惟喬親王が見たという龍の夢の伝説を追って、この国のもうひとつの姿を目撃する。(「改元」) 山あいの地主の一族に生まれた少年は、日猶同祖論を唱える父によって「世界の救い主」となるべく「十(じゅう)」と名付けられた。第二次世界大戦をまたいで繰り広げられる、めくるめく年代記。(「死者たち」) ーーー 四六判 ハードカバー 送料:300円
-

〈わたし〉からはじめる地方論――縮小しても豊かな「自律対話型社会」へ向けて | 工藤尚悟
¥2,200
ーーー (出版元による紹介) 人口、産業、文化……縮小するなかで地域は何を持続していくのか?都市と地方の二項対立から脱し、地域が自らの「言葉」で豊かさを語り直したとき、本当の意味での「地方創生」につながる──。 秋田県五城目町で研究する「地域✕サステイナビリティ」の論客、20年の集大成。 ー 【目次】 はじめに 縮小するなかで「地域が続く」とはどういうことか? 第1章 地域の縮小に向き合う〈わたし〉はどこにいるのか ――「地域活性化」という言葉で見えなくなるもの 第2章 人口減少社会の現在地を探る ――縮小する社会をどうデザインするか 第3章 「地域が続いていく」とはどういうことなのか ――流れのなかの〈あいだ〉として地域を見る 第4章 五城目町は、なぜ〈わたし〉を取り戻せたのか ――つながりと企てが頻発するまちづくりのための5つの仕組み 第5章 自律対話型社会にむかって ――地域ごとの豊かさをつくりだす「風土のサステイナビリティ」 おわりに 〈わたし〉を起点に、対話をはじめよう ーーー 四六判 ソフトカバー 280ページ 送料:300円
-

奇奇怪怪 | TaiTan,玉置周啓
¥2,750
唯一無二のポッドキャスト番組書籍化第二弾!小口に塗りが施された造本から既に楽しいです。音声と書籍、合わせてぜひ。 ーーーーー ラッパーのTaiTan(Dos Monos)、音楽家の玉置周啓(MONO NO AWARE / MIZ)の二人が、映画・音楽・小説・漫画などのコンテンツから、生活の中で遭遇する違和感とワンダーの裏に潜む経済の謎まで縦横無尽に語り尽くす、Spotify Podcastチャートで最高順位第1位を記録した、超人気ポッドキャスト番組『奇奇怪怪』。 2022年にポッドキャスト番組としては異例の500ページ越え・本文三段組み・函入りという造本で書籍化され大反響を呼び(国書刊行会より刊行)、版元史上最高予約数(当時)を記録。同年秋にはアニメ化やTBSラジオでレギュラー番組『脳盗』が開始されるなど、領域を超えて広がりを見せる同番組が満を持して刊行する書籍版第二弾! 第一弾の百科事典的装いから漫画雑誌的オブジェクトへと変貌を遂げ、書き下ろし序文、語り下ろし跋文、そして巻末解説にギャグ漫画家・藤岡拓太郎氏の短編漫画を併録! 文化と経済の森羅万象を「強引に面白がる」ための言葉と思考の実弾が詰まった異形の対話篇。 ーーーーー B5 392ページ 送料:300円
-

ふつうの人が小説家として生活していくには | 津村記久子
¥1,760
夏葉社の島田潤一郎さんが聞き手となり、小説家・津村記久子さんがどのように暮らし、どのように小説を書いてきたのかを、共通の趣味である音楽やサッカーの話を交えながら根掘り葉掘り聞いた本。 「元気が出て、なにかを書きたくなる、ロングインタビュー。名言がたくさんです」 四六判 ハードカバー 208ページ 送料:300円
-

子どもたちによろしく【サイン本】 | 長崎訓子
¥2,800
ーーー 人気イラストレーター長崎訓子が23年間描き続けた子どもが登場する映画たち。 この本は、かわいい絵本ではありません。 子どもは社会を映す鏡です。 時には戦争下で、時には貧困で、歯を食いしばって親を恨み、仲間たちと悪さをする子どもたち。映画のなかの子どもたちの眼差しを、長崎訓子が鋭い視点で描いています。 ーーー A5変形、上製、144ページ、オールカラー 送料:300円
-

日々のあわあわ【サイン本】 | 寺井奈緒美
¥2,200
歌人でエッセイストで土人形作家の寺井奈緒美さん、オノマトペがキーワードとなる最新エッセイ集が入荷。初回分はサイン本です。 47のエッセイと短歌にくわえて、オノマトペをテーマにした〈あわあわ短歌〉32首も収録。 土人形も48体カラーで収録。 ーーー 四六判 ソフトカバー 220ページ 送料:300円
-

おめでたい人&生活フォーエバー 寺井奈緒美おもしろセット
¥4,070
寺井奈緒美さんのたいへんに面白いエッセイ&短歌集2冊をセットにしました。 おめでたい人 2090円 生活フォーエバー 1980円 送料:300円
-

おめでたい人 | 寺井奈緒美
¥2,090
短歌&エッセイの『生活フォーエバー』が当店でベストセラーになっている寺井奈緒美さんの新作エッセイ&短歌本がついに刊行。日々の生活を淡々と書きつつユーモアを表出させる筆がもはや名人芸の域に達してます。仕事が忙しい時期にゲラを送ってもらって読んでいたのですが、ヘトヘトになればなるほど読みたくなるという本でした。「疲れた…でも、いや、だからこそ、寝る前に『おめでたい人』一編読みたい…」みたいな。笑って脳が回復する感じ。 四六判 ソフトカバー 212ページ 送料:300円 ★「生活フォーエバー」とのセットもあります https://rebelbooks.theshop.jp/items/105290313
-
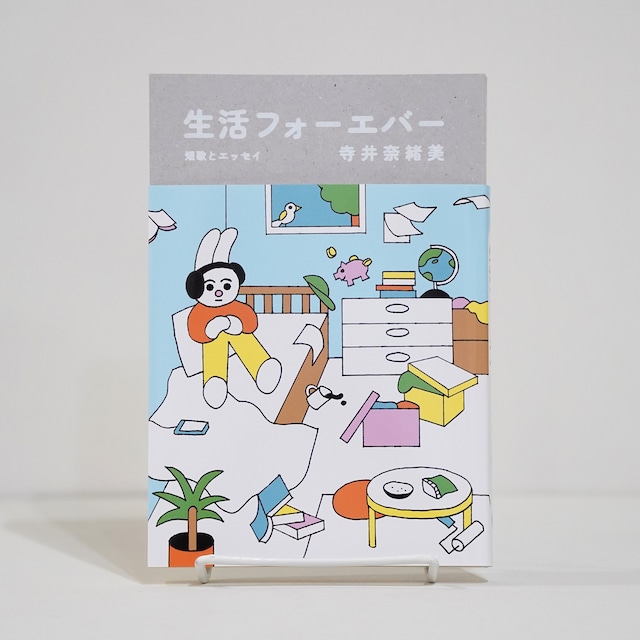
生活フォーエバー | 寺井奈緒美
¥1,980
日常のおかしみをふにゃっと見事にとらえたおもしろすぎる短歌とエッセイ。笑うと心が軽くなる。わたしたちの生活には『生活フォーエバー』が必要だ。 ーーー 収録短歌 ↓ 仕事中ノンアルカクテル飲むような舐めた態度で真面目に暮らす もうわたしログインなんてこりごりよ生きるしか能がないんだから ーーー 歌人として活動するほか、habotan名義で土人形を制作している寺井奈緒美による、初の短歌&エッセイ集。 この愛すべき、くだらなさ。 2019年に書肆侃侃房より刊行された第一歌集『アーのようなカー』では、日常の片隅に忘れられた事物をそっと掬うような、ささやかで滑稽で、どことなく寂しい歌で、多くの読者を獲得しました。 本書には2021年の秋からおおそ1年の間に書いたエッセイ80篇と短歌160首が収録されています。書かれているのは、限られた行動範囲(ほとんどが部屋、そして職場、西友、たまに映画館)と限られた登場人物(私、S、ときどき同僚)の中でのまったく映えない日常。それがなぜだかすこぶる面白い。その想像力とユーモアは、私たちの抜き差しならない「生活」の見え方を変えてくれることでしょう。読めばきっと、明日への活力になること間違いなしの一冊です。 装画は楢崎萌々恵。 ーーー 19cm×12.8cm 224P 送料:300円 ★2025年刊行のエッセイ&短歌本「おめでたい人」とのセットもあります https://rebelbooks.theshop.jp/items/105290313
-

『アーのようなカー』 寺井奈緒美
¥1,870
当店で短歌&エッセイ集『生活フォーエバー』が大好評中の歌人・寺井奈緒美さんによる2019年刊行の歌集です。 【5首】 改札を通るときだけ鳴く鳥をだれもが一羽手懐けている 柴犬の尻尾くるんの真ん中の穴から見える極楽浄土 耳と耳あわせ孤独を聴くように深夜のバスの窓にもたれて 路上にはネギが一本落ちていて冬の尊さとして立て掛ける なくなれば美しくなる でもぼくは電線越しの空が好きです ーーー 四六判 ソフトカバー 144ページ 送料:300円
-

カメラじゃなく、写真の話をしよう | 嵐田 大志
¥2,200
『「良い機材で撮る=良い写真」ではない』『「画質」と「写真の良し悪し」には相関性がない』写真を撮っていくなかでついつい陥りがちな、「自分はどんな写真が撮りたいのか」に向き合わずにカメラやレンズのことばかり考えてしまう問題にバサバサと切り込み、写真との向き合い方を正すきっかけを与えてくれる本。技術自慢・画質自慢ではない著者の作例が良いので説得力があります。 ーーーーー 【目次】 ■opening gallery ■第1章 カメラ沼にハマった先で僕が考えたこと episode1 「良い機材で撮る=良い写真」ではない理由 episode2 カメラ選びの基準 episode3 デジタルカメラとフィルムカメラ episode4 写真歴が長い人にこそスマートフォン撮影をすすめる理由…ほか gallery 定点観測 東京の空 column_01 僕がカメラに費やしたお金の話 ■第2章 「押せば写る時代」の撮影技術を考えてみる episode7 僕がオートで撮る理由 episode8 撮影技術は均質化し、重要性が低下する episode9 テクニックは手段であって目的ではない episode10 「好き」の正体を言語化しよう…ほか gallery 僕たちの夏休み column_02 スマホ編集のススメ ■第3章 もっと写真と向き合うために episode16 テーマを決めて撮ること episode17 定番写真集を読むべき理由 episode18 家から300m以内で撮る episode19 とにかく枚数を撮れ! の罠…ほか gallery 愛しきハワイ column_03 僕の好きな写真集 ■第4章 写真の本質を考える episode31 写真とは何か(1) episode32 写真とは何か(2) episode33 写真によって異なる時間感覚 episode34 間口が広く、奥が深い写真道…ほか gallery 大切な人 ーーーーー 送料:300円
-

「手に負えない」を編みなおす | 友田とん
¥1,980
ーーー 『『百年の孤独』を代わりに読む』著者・友田とんさんによる待望の新作。地下鉄の漏水対策の観察から始まる、暮らしと探究のクロニクル。予測不能な脱線の果てに目にした景色とは――。 「ユーモアも文章力も本当にすごい。でも何より、なんでもなさそうなものにまなざし、愛でる感性に胸打たれ、嫉妬しました」 ――星野概念さん(精神科医)も推薦! ーー 十年近く前に「地下鉄の漏水対策」に心を奪われ、極私的なフィールドワークを続けてきた著者。その過程で気づいたのは、人が手当てをすることで維持されている「手に負えない」ものに、なぜか心惹かれてしまう自身の性質だった。 「手に負えない」ものたちとのちょうどいい向き合い方を見つけたい。だが、解決の糸口をつかむたびに新たな「手に負えない」が発生し、圧倒されてしまう。果たしてこの本を、無事に閉じることはできるのか! 予測不能な脱線の果てにある、謎の感動をあなたに。 ーー 【目次】 まえがき 第一部 地下鉄にも雨は降る 第一回 探しものはなんですか? 第二回 上を向いて歩こう 第三回 この恍惚を味わいたかったのかもしれない 第四回 管理台帳の姿を想像しながら 第五回 地方の地下鉄も見に行く 第六回 手に負えない 第二部 手に負えないものたちと暮らしてみる 第一章 さかのぼる 第二章 見る 第三章 作る 第四章 編みなおす あとがき ーーー 【著者略歴】 友田とん〈ともだ・とん〉 作家・編集者。一九七八年京都市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、同大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士(理学)。企業で研究開発に従事するかたわら、二〇一八年に『『百年の孤独』を代わりに読む』を自主制作(二〇二四年にハヤカワ文庫NFより再刊)。同書を全国の本屋さんへ営業したのを契機に、ひとり出版社・代わりに読む人を立上げる。日常や文学に可笑しさを見つける作品を発表しながら、独特の視点を持つ様々な著者の小説やエッセイを刊行する。著書に『ナンセンスな問い』(エイチアンドエスカンパニー)、『先人は遅れてくる』『パリのガイドブックで東京の町を闊歩する』(代わりに読む人)、『ふたりのアフタースクール』(太田靖久氏との共著、双子のライオン堂)などがある。 ーーー 四六判 ソフトカバー 248ページ 送料:300円
-

いきなり知らない土地に新築を建てたい | 徳谷柿次郎
¥2,000
「サーバー借りて独自ドメイン取ってワードプレスを立ち上げてブログを書く(アイキャッチ画像なし、SNSシェアボタンなし)」、これってもはや「クラフトインターネット」なのでは?というひらめきを機に書き続けた日記をもとに生まれた本。いま序盤をちらっと読んだだけですが思考と文章のグルーヴにかなり牽引力ありです。 ーーー ーーおすすめポイントーー ① 「SNS疲れ」を感じる現代人への処方箋 「おすすめ」や「いいね」に踊らされるインターネットに違和感を持つ層へ。自分の言葉を取り戻す「クラフトインターネット」という新しい(けれど懐かしい)概念は、ZINEや日記本ブームとも共鳴し、強く刺さります 。 ② 「ローカル×編集×生活」のリアルな実践知 長野県信濃町での集落暮らし。きれいごとではない「除雪」や「近所付き合い」、「店舗づくり」の泥臭い描写は、地方移住や二拠点生活に関心がある層にとって、単なるガイド本以上のリアリティを提供します 。 ③ 豪華巻末対談:徳谷柿次郎 × 家入一真 インターネットの黎明期を知る家入一真氏を迎え、「なぜ今、クラフトインターネットなのか?」を深掘り。カウンターカルチャーとしてのインターネット論は、WEB業界やクリエイター層にも訴求力抜群です 。 ーーー 送料:300円
-

編集の編集の編集!!!!
¥1,500
編集とは何か?編集者たちの書いた文章と、集まって話した座談会。「美しい答えではなく、思考のプロセスそのものを記録」とありますが、そういうところからにじみ出るものが大事なんじゃないかと、最近特に思ってます。 ーーー 『編集の編集の編集!!!!』は、単なるビジネス書でも、従来の編集ノウハウ本でもありません。効率化と正解が最短距離で求められる現代において、あえて「手間」と「摩擦」と「混沌」の中に身を投じた、4人の編集者による「編集という営みの再定義」を試みるドキュメンタリーです。 発端は、2025年5月、京都・亀岡で行われた「ZINE制作合宿」でした。長野、京都、函館から集まった4人の編集者が、京都・亀岡の土を掘ってインクを作り、瓦を削って版を作り、徹夜でリソグラフ印刷機を回して製本する――。デジタル全盛の時代に逆行するような身体的な狂気と熱量。その夜に生まれたわずか28部の幻のZINEを、より広く、しかしその熱を冷ますことなく届けるために再編集したのが、この『編集の編集の編集!!!!』です。 雑誌・Webメディアの「狭義の編集」から、まちづくり・ブランドづくりといった「広義の編集」まで。どこまでが編集で、どこからが編集ではないのか?そして編集者は何を信じて、どんな身体性で仕事を続けているのか? 本作では、編集者自身がその“不明瞭さ”や“葛藤”を引き受け、美しい答えではなく、思考のプロセスそのものを記録しています。 焚き火の前でぶつかり合うような生々しい座談、ZINE制作合宿で起きた衝突と迷い(なぜあの夜、全員がキレたのか?)、「わかりやすさに抗う」「京都スーパー三国志」「亜流編集」など、独自概念が飛び交うコラム。 編集という言葉が便利になりすぎた今だからこそ、行き過ぎたDIY精神と、人間の清濁をそのまま抱え込み、もう一度 「編集とは何か」 を考え直す一冊になりました。 ーーー 106 × 184 mm ソフトカバー 送料:300円
-

都市と路上の再編集 – LIVE NOW DEVELOPMENT –
¥2,200
まずタイトルが素晴らしいですよね。 「トップダウンで都市開発をする人々と、ボトムアップでまちづくりに参加するプレーヤーが手を取り合うには、どうすればいいのか?」という問いに基づき、「大企業や自治体とも手を取り合って、まちづくりに関わっているプレーヤーたちの話」を集めた本。 早速読み始めてますがとてもいいです、各事例深く掘り下げていて刺激満載。 たくさん発注し、先行入荷してます、みなさんぜひお読みください! ーーー 【目次】 ◆LIVE NOW DEVELOPMENTとは p4 はじめに──まちづくりの思考、手法、関係性を“再編集”する p10 HOME / WORK VILLAGE 小野裕之/まちづくりはビジネス or カルチャーじゃない ◆今、くらしに求められていること p24 建築家 山本理顕/変えるべきは「働く」と「住む」の分断 p36 解剖学者 養老孟司/脳化された現代にこそ「田舎」が必要 ◆今、再編集への期待が高まるもの p50 グランドレベル 田中元子/論理性に偏った社会に、非論理性の文鎮を乗せたい p62 Dprtment 佐々木大地/ストリートの心×パブリックの視点 p70 SHONAI 山中大介/“個”の自由な往来が、地方都市をおもしろくする p78 西村組 西村周治/ロマンとそろばんの両輪を駆動するために p86 真鶴出版 川口瞬/心を入れて、残したい風景を言語化する p94 加和太建設 河田亮一/まちづくりが「映画制作」にまで発展 ◆手を取り合って生まれている新たな動き p106 さとゆめ 嶋田俊平/「ふるさと」と「情緒」の関係性を言語化し、実装する p116 創造舎 山梨洋靖/まちづくりは究極、人づくり p126 いまでや 小島雄一郎/自宅の1階に、好きな店を誘致できた理由p136 アメリカヤ 千葉健司/横のつながりを最大化し、目的地になる町にリノベーション ◆おわりに 互いに必要とする間(あいだ)の存在 p148 n’estate 櫻井公平 × ジモコロ 徳谷柿次郎/今、求められる「価値観の反復横跳び」 ーーー 価格:本体2,200円(税込) 仕様:A5 変型/160 ページ 発行:風旅出版(株式会社Huuuu) ーーー 送料:300円
-

A GUIDE to KUROISO
¥3,000
栃木県黒磯のガイドブック。『ジモコロ』や長野県の移住サイト『SuuHaa』を手がける編集の会社Huuuuが丹念に取材して制作。驚くほど良いお店が多数掲載されていて読んでるだけで刺激を受けるし、若い人が引っ越してきて仕事が生まれていて、その循環すごいなと感じます。黒磯に行ってみたくなること間違いなし。「街のあり方」と「街の見せ方」を考える人の、大いに参考になるであろう一冊でもあると思います。 送料:300円
-

チュコトカ 始まりの旅 ユーラシア大陸最東端へ | 後藤悠樹
¥2,200
ーーー 「チュコトカ」――そこはしばしば「地球の果て」とも称される極北の地で、星野道夫(1952-1996)が急逝する直前に訪れていた場所の一つである。 1996年夏、アラスカの対岸とも言えるチュコトカへの旅で、星野道夫はひときわ印象的な先住民の家族と出会い、その家族の写真を撮影し、日誌に残していた。しかし、一連の旅でまとめる予定であった作品は、彼の突然の逝去により、未完のまま歳月は過ぎていった。 それから20年後の2016年夏、偶然の積み重ねにより、ひとりの写真家が、星野の遺した一枚の家族写真を手に、チュコトカへ向かい、新たな旅を始めた。 きらめくツンドラ、吹きさらしの海獣の骨、先住民チュクチやエスキモーの人々の暮らし、そして星野が写したミーシャの一家との出会い……。 旅はまだ、続くはずだった。 2026年現在、アメリカとの国境に位置するチュコトカは、ロシア・ウクライナを巡る国際情勢の悪化により、事実上、渡航不可能となった。 かの地に生きる人々や自然を、写真と日誌で記録にとどめた、奇跡のような一冊。 ーーー 【著者略歴】 後藤悠樹〈ごとう・はるき〉 1985年大阪生まれ。2006年よりライフワークとしてサハリン(樺太)の取材を始め、長期滞在を繰り返す。2018年には『サハリンを忘れない――日本人残留者たちの見果てぬ故郷、永い記憶』(DU BOOKS)刊行。代表的な写真展に「Всматриваясь в Сахалин(邦題:サハリンを見つめて)」(ロシア・サハリン州立美術館、2018年)などがある。その他の著書に、写真を担当した、『サハリン残留――日ロ韓100年にわたる家族の物語』(高文研)がある。 ーーー A5 ハードカバー 128ページ 送料:300円